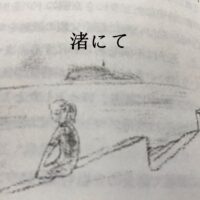■前回までのあらすじ
かつて大学で考古学を学んだ憲二は、恩師の吉田教授と鎌倉小町裏通りのスナック[段葛]で歴史談義に及び、段葛の女将(ママ)が鎌倉時代を見てきたかのように語りだす。
疱瘡を患った実朝は、熱にうなされながら、首を切られる悪夢を見、自身も兄や父のように殺されるのではないかという疑念を抱く。やがて疱瘡が癒え、鏡に映った自分の顏を見て失望する。そんな失意の孤独な実朝を癒してくれたのは、師の栄西から授かった『大唐西域記』だった。未知の西域に想いを馳せているとすべてを忘れることができた。
* * *
廂(ヒサシ 注)に侍女がひとり控えているだけ。ほかにだれもいない対舎(タイノヤ 注)で、実朝はひとり白粉(オシロイ)を糸瓜水(ヘチマスイ)に溶いていた。それを箆(ヘラ)ですくい、鏡を覗きながら顔に塗りつける。顎から頬へと撫で上げてゆく。まるで白塗りの仮面をつけるような心情にも近い。京の公家たちにとってはごくあたりまえの嗜みであっても、この鎌倉の武士たちで化粧をする者は少ない。どちらかといえば女子(オナゴ)の嗜みといって嫌う者すらいる。実朝も京の公家たちの真似をしようとしたわけではなかった。
病が癒えたあと、自分を見る周囲の目が以前と変わった。
だれもが自分を見たとたん一瞬目を見張る。言葉にすることはなくとも、何と見苦しい、という顔色を隠せない。だが次の瞬間、それが実朝とわかり、はっとして目を伏せる。会う者、会う者がみな同じような顔をする。もちろん将軍の顔を直に見るのは無礼ではあるが、それでもひとたびは顔をうかがって将軍と認め、おもむろに頭を垂れたものだ。それが今は違う……。
そんな自分を見る目をなんとかしたくて化粧をするようになったのだった。
だが、溶けた蝋が垂れ、それが固まったかのような痘痕(アバタ)の肌は白粉の乗りが悪い。何度も重ねて塗らないと痘痕を塗り込めるのは難しい。かといって厚くなりすぎると罅(ヒビ)や皺ができる。うまくいかなくて苛立ち、箆を投げつけたくなる。が、堪(コラ)える。そして、じっと鏡の中の自分を見つめる。
本当は僧になって宋へ渡るつもりだった。そして西域、天竺へと……。だがあの変事が起きた。祖父、時政が比企一族を滅ぼし、二代将軍となっていた兄、頼家を伊豆に幽閉してしまった。まだ十二歳だった千幡は実朝と名を改め第三代将軍となった。いや、させられたといってよい。宋へ渡る夢はほぼ潰(ツイ)えた。
京から正室の信子を迎えたものの、実朝にとっては妹ができたような気持だった。その信子にようやく女を感じ、室という意識が芽生え始めたころ疱瘡の病に罹った。瘡蓋のあるうちはうつるということもあって互いに近寄ることを避けていた。その瘡蓋もとれたころ、そっと信子の床に入った。実朝と感づいたようすはある。だが背を向けたまま身を固くしている。まるで蛹(サナギ)になったかのようだ。手を触れる、と微かに震えている。哀れになり、やがて自身の行為が情けなくもなる。燃えかかった気分も萎え、身も心も冷たくなった。その夜以来、口をきくことも少なくなった。将軍は世継ぎを求められる。だがおそらく自分は子を成すことはないだろう。その予感はしだいに確信になっていった。やはり兄、頼家のほうが……。実朝にとってもそのほうがずっと良かった。なのになぜ……。
兄は強すぎたのだ。齢(ヨワイ)二十一で将軍となり、その若さで重い任を背負いながら父の頼朝と同じようにふるまわねばならぬ、という気持もあっただろう。いや、父を越えようとしていたのかもしれない。それが御家人たち、とくに北条家の人間に疎まれたのだ。
坂東武者の棟梁は武に長けているだけでなく神仏の加護を引き寄せる霊的能力をも求められる。どんなに武に秀でていても出陣の日和を読み誤り、運を呼び込むことができなければ棟梁としては見限られる。父、頼朝はその両方の資質を備えていた。だが兄は武に偏り過ぎていたのかもしれない。
「殿は八幡様をお守りする任に努め、お力を注がれるが宜しい。政(マツリゴト)のほうはこの相州にお任せあれ」
叔父である北条義時は実朝が十二歳で将軍に就くなりそう言った。たしかにそれは鎌倉の棟梁として重要な仕事であることに違いない。
「千幡、いや殿。そなたはまだ若い。執権殿の言われるとおり日々の政はお任せし、大事についてのみ断を下せばよいのじゃ。なにも案ずることはない」
母の政子もそう言った。
――ならば、そうしよう。
兄の二の舞は御免だ。あのようなことにならぬよう鶴岡八幡宮をお守りする任に努め、政で出過ぎるのは控えよう。
実朝が齢十五のとき、兄、頼家の忘れ形見で二男の善哉が養父の三浦義村に付き添われて政子の邸へやってきた。幼子から一人前の男子となる着袴(チャッコ)の儀を行うためだ。(参考:関係者系図)
「善哉君はいくつになられましたか」
政子は目を細め、笑みを浮かべた。やはり血のつながった孫は可愛いのだろう。
「はい尼御台(アマミダイ)様、六歳になりましてございます」
まだあどけない口述にも健気さがにじむ。親を亡くしたとはいえ、かつては将軍であった貴人の子。大事に育てられているはず。だが……。
――この子は父の死にざまを知っているのだろうか。だとすれば私を恨んでいないだろうか。
実朝は真新しい袴を着て居住まいをただす子供を見つめた。あどけない顔の中にも頼家の剛直さがにじみ出ているように思える。つぶらな瞳の中に何か怪しい陰りがあるのではないか、と。
――兄を殺したのは祖父の時政。とはいえ自分が次の将軍に就いている。となれば、この子がものごころついたころには……。
――いや、この子が父を亡くしたのはまだ乳飲み子のとき。そのような想いは……。
不安と疑心に心が揺れる。
「ほれ、殿。なにか言っておやりなさい。そなたにとっても甥子ですよ」
政子がたしなめるように横目で見る。
――穢れのないきれいな肌をしている。
まるで餅のような少年の肌を見て、つい鏡に映した自身のそれを思い浮かべ、比べてしまう。とたんに心が波立つ。
「そ、そなたは何になりたいのだ」
かける言葉が見つからず、つい口をついて出たのだが、まずいことを聞いたと思った。
「はい、強い武士になりとうございます」
子供ながら凛とした声で応える。
一瞬、兄、頼家の顔と重なる。その顔が毅然と自分を睨みつけたように感じた。すると養父の義村が慌てて善哉にすり寄る。
「なりませぬぞ、いずれは僧侶になるといつも申しておるではありませぬか」
声をひそめるかのように耳打ちするものの実朝と政子にははっきりと聞こえてくる。源氏の血をひく男子を預かっている手前、遺児を祭り上げて謀反を企てていると勘繰られてはまずいと思ったのだろう。
「そうか、やはり武将の子であるな」と政子は半ば感心したような顔をしながらも「三浦殿のおそばには武士ばかりおるでな」と落胆の顔になってため息をついた。そして、
「そろそろ八幡宮別当に預けるころかのう」
穏やかな顔をしたまま冷徹につぶやき、そして、
「いずれはこの子を別当にさせたいと思うておる」
哀れな子を見るような目で静かに言った。
源氏と自身の血を継ぎながら、嫡流から外れた者。いや、敢えて外した、ということかもしれない。とはいえ、この子供自身に罪はない。それなりの地位を与えてやりたいということだろう。ならば源氏の守護神を祭る宗教者としての道を歩ませるのがよろしかろう。そう宣言しているようでもあり、また実朝にそうするよう迫っているかにも聞こえた。
鶴岡八幡宮は神仏いずれも祭る宮寺のため僧侶と神官の両方に守られている。別当はそれを束ねる最高位の職だ。
このとき、源氏の血を引く二人が同じ場に居合わせていた。ひとりは望まずして将軍になった者。もうひとりは、やはり望まずして宗教者としての道を与えられようとしている者。出家させられ、公暁の法名を受けて受戒のため京へ上ったのは、この六年後、齢十二のときだった。
*
「近侍(キンジ)の兵衛清綱が京より持参しました」
そう言って信子は『古今和歌集』をさし出した。夫婦の営みはすっかり冷えていたが普段交わす言葉は前と変わらぬかに見える。正室の実家では実朝の病後を案じているらしい。将軍家との繋がりを保とうとする下心はあるにせよ、少しでも気を紛らわすものをという配慮だろう。書物とともに文を添えることもできる。京の公家の間で噂されていた頼家暗殺の真相を伝えてきたのも信子の実家からだった。
――歌のどこが面白いのだ。
もともと興味はなかった。
執権でもある叔父、義時は、二言目には「武芸に精を出せ」「坂東武者の嗜みは弓馬」とうるさく言う。
実朝は、じつは馬も弓も嫌いではない。だが敢えてその思いを口にしないようにしていた。できれば馬に乗って山野を駆け巡りたい。そのまま宋まで行って国中を駆け抜け、玉門関を越えて西域に飛び出してゆきたい。そうして騎馬の民とやらと草原を駆け巡る。そんなことができたら……。
だが義時の言葉どおり武芸に励んで屈強な武将になったらどうなるだろうか。御家人たちからもいち目置かれ、大殿のような、とまで思われたら……そう、執権をさしおいて……。
――兄の二の舞は御免だ。
だから、流鏑馬(ヤブサメ)の鍛錬のときも……。
馬に乗って駆けながら弓で的を射る流鏑馬は坂東武者の嗜み。馬は好きだ。弓矢も面白い。本当はこんなに楽しいものはないと思っている。風を切りながら手綱を放す。弓を握りながら腰を浮かせ、揺れる馬の背中で鐙の上に立つのは勇気がいる。揺れを膝の屈伸で吸収する。上下動の調子がほんの一瞬でも狂えば馬の背中から放り出される。だが、その一方で空を飛んでいるかのような爽快さもある。弓を握る。背負った空穂(ウツボ)から素早く矢を引き抜き、揺れに合わせながら弦に掛ける。近づく的を睨む。目を離さぬようにして弓を引き絞る。矢先を的に向ける。狙いがぴたりと定まった刹那、そのまま放てば間違いなく当たると確信する、が、このとき、狙いを的から下の砂地にずらす。
敢えてそうする。というのも、実朝にとっては下の砂地が的の中心なのだ。
――ここだ!
矢を放つ。空を切る音がし、矢は的の下の砂地に突き刺さった。
――よし!
空を飛ぶように駆けながら気持だけ拳をふりあげる。同時に爽快な気分がこみ上げる。だがこのとき満足感に浸っているのは実朝だけだ。
「また外しましたな、殿」
もどってくるなり義時が渋い顔で待っていた。
「狙いが甘うござる」
馬の乗り方は悪くない。だが的への集中力が欠けている。義時がこんこんと狙いの定め方について指南してくる。おとなしく聞くふりをしながら胸の中でつぶやく。
――わかっておるわ。
実朝としては狙ったとおり。的に中(アタ)ったも同じだ。
――今の将軍は前の二人と違って武芸下手。相州よ、そう思っておけ。
正室の実家から送られた歌集を手にしながら思う。
京の公家のように歌を嗜むのもよいかもしれない。貴族趣味の歌好きで武芸は苦手。よい隠れ蓑になるやも……。
はじめのうち『古今和歌集』は『大唐西域記』のように実朝を熱くさせることはなかった。広大な未知の世界を感じさせるものはなく、身の近くにあるものへの細やかな想いが窮屈な短文で綴られているだけのように思えた。ところが胸の内を明かすことのできる人間が傍にいないということもあってか、歌が密かに自身の心を吐露する器になることを見つけた。そしてしだいにその魅力にのめり込んでいくことになったのである。
「のう文章博士殿。これまで詠んできた歌を定家卿に見ていただこうと思うが、いかがなものか」
実朝は侍読で京の事情にも通じた源仲章にためらいつつ尋ねた。藤原定家といえば勅撰集の選者でもある当代随一の歌人である。そんな人に京から遠く離れた田舎者の習作を送るなど、まだとても早い、と言われるかと思った。ところが、
「それはよいお考えです。ぜひそうなさいませ」
と言って送り状の手ほどきを始めた。おそらく、定家卿とはいえ、鎌倉の将軍が自ら詠んだ歌ならば、たとえ拙くとも足蹴にすることはなかろうと思ったのだろう。
ひと月ほどして、
「なんと、ご丁寧に評していただいたうえ、詠歌口伝の書まで添えていただいているぞ」
思っていた以上の評価と丁寧な歌論指南に熱いものがこみあげてくる。
どんなに説いて言い聞かせても伝えられぬ想いというものがある。それを、わずかな言葉を綴るだけで奥深く表すことができる。それも想いの通じる者の心にだけ響き、心を異にする者には解せない。これほどまで心踊るとは思っていなかった。
やがて実朝は歌に夢中になっていった。宋に渡り、西域に飛び出すという夢は胸の奥にしまい込んだが、その虚しさを埋めるに足るもの、とすら思うようになっていた。
――そうだ、あれを歌に詠んでみよう。
そのあれとは実朝が齢十三となった建仁四年二月のことだった。
北の空が赤く燃えたような光を放っていた。夕焼けならばとうに消えている刻限である。やがて濃い桃色の羽衣が空をうねるように流れてゆく。陽でも月でもない、ましてや星でもない、今まで見たことのない不思議な光の大河が天空を流れてゆく。実朝には天女が羽衣をなびかせて飛んでゆくかのように思えた。
――妖しく、美しい。
あれは、いったい……。