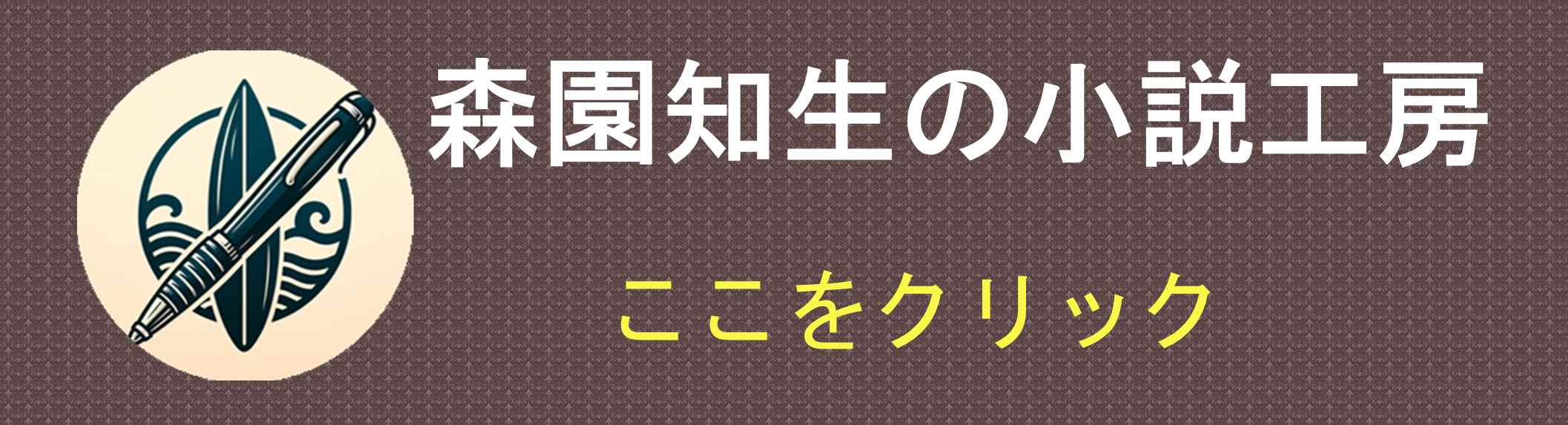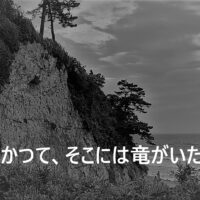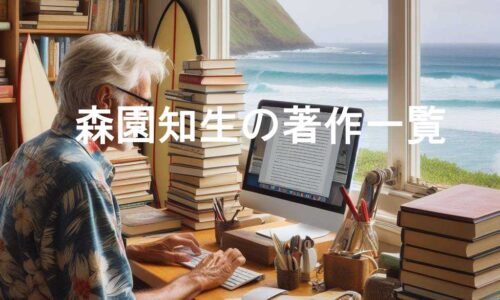■前回までのあらすじ
疱瘡を患った実朝は、熱にうなされ、自分の首を切られる悪夢を見て、自身も兄や父のように殺されるのではないかという疑念を抱く。やがて疱瘡が癒え、鏡に映った自身の顏を見て失望するが、師の栄西から授かった『大唐西域記』を読むことで、未知の西域に想いを馳せ心を癒した。弓矢や乗馬の武芸も、本当は好きで得意だったが、義時の前では、敢えて武芸下手の和歌好きを演じた。
建仁四年二月、北の空が赤く燃えたような光を放つ。
* * * 
実朝の目に、天空を流れてゆく、不思議な光の大河が映った。
胸の奥が震えるような感慨。
ところが、そばにいた者たちは不吉だとか恐ろしい、としきりに口にしていた。御所付きの陰陽師は凶兆と言っていた。
だが、実朝にはそうは思えなかった。美しい、面白い、なぜあのような不思議なことが起きるのか、知りたくて胸が騒いだ。
あのとき見た不思議なありさまとそれを見たときの心踊る想いを歌に詠みこみ、定家卿に送った。だが……。
しばらくして返ってきたその歌の評はあまり芳しいものではなかった。
定家自身もおそらく同じころ似たようなものを見たという。京ではそれを赤気(セッキ)と呼んでいたらしい。
定家自身、歌は広く求め、遠く聞く道にあらず。心より出でて自ら悟る物なり、と実朝に教えた。詞(コトバ)は古きを慕い、心は新しきを求めよ、とも言った。そう認めたうえ、赤い気、あれは怨霊の気であり、そのような不吉で邪悪なものは、たとえ実朝が「新しい」と心に感じたことであっても歌に詠むべきではないという。(赤気に関する参考情報)
――不吉……。
たしかにあの年、兄の頼家が伊豆で殺された。しかしそれは夏のことで、あの不思議な天空の出来事があった後のことだ。となれば怨霊というより凶兆であったのかもしれない。
――坂東の田舎者の感じ方とは違う、ということか……。
実朝が感じ、心震えたものが定家の心には響かなかった。
このとき、実朝は歌を詠むということについては自身の感性を封印した。
心は新しきを求めよとしながら、向けられるものはだれもが目にしているもの、感じるものであり、それを新たな心で詠むのが歌というものらしい。そうであれば、だれも目にしたことのなかったもの、不思議なこと、面白いことをもっと見てみたい、探ってみたいという熱い想いのほうは胸の奥に閉じ込めておくしかなかった。いつか開けるかもしれない玉手箱のように……。
――芳しい香りがする。
――いつか、どこかで出会ったような気がする。そうだ、永福寺に咲いていた梅の花……。
――これは夢の中なのだろうか。
自分が殺される夢。熱病に苦しむ夢。そんな厭わしい夢ばかり見てきた。なのに今……。
瞼に薄明りが射しこむ。まだ夜の明けきらぬころだろう。障子に細い木の枝が影を落としている。それは永福寺から御所に移し植えた梅の木だ。昨夜見たとき細枝に点々と蕾がついていた。
――ああ、ようやく花が咲く。
そう思いながら床に就いたのを思い出した。
心より出でて自ら悟る。
――定家卿の申されていたのは、こういうことか……。
梅が香を夢の枕にさそひきてさむる待ちける春の山風
夢うつつの枕元に梅の香を誘って来てくれた春の山風は、吾の目が醒めるのを待っていてくれたのだ、と。
そう一首詠んで間をおかず、また一首浮かぶ。
この寝ぬる朝けの風にかをるなり軒ばの梅の春のはつ花
移し植えた梅が、初めて館の軒端で花を咲かせたときだった。定家の教えで育まれた感性が、短い言葉を紡ぐ。このとき実朝は、いずれこの梅の木に深い想いを託すことになることを、まだ知らなかった。
*
実朝は牛車に揺られながら寿福寺へ向かっていた。忍びの出向きゆえ、立烏帽子に狩衣という公家の平服を装う。そして今日は白粉の化粧はしていなかった。顔を人にさらすこともなく、誰に気兼ねすることもない。
寿福寺は勝長寿院や永福寺のような公(オオヤケ)の寺ではない。政子が夫、頼朝を弔うために建てた、どちらかといえば源家の菩提寺のような寺であった。だから執権の義時にも手の及びにくいところであって、実朝が忍びで来るには好都合だった。
実朝が寿福寺を訪ねるのは栄西禅師の教えを請うためだが、禅師は鎌倉と京を頻繁に行き来しているので実朝は禅師と会えないこともある。だが、それでも行く意味はあった。
牛車の物見(モノミ)を少しだけ開けて外を覗く。あたりは武家屋敷なので実朝にとって珍しい景色ではない。ふと禅師の言葉が思い出される。
「なにも宋へ行かずとも、この鎌倉にはあなた様が見ておくべきものがたくさんあるはずですぞ」
宋へ行く夢が潰えたと禅師に愚痴をこぼしたときのことだった。
「鎌倉の民がどのような暮らしをしているかご存知か?」
それも知らずに宋へ行って民の暮らしを見て何の違いがわかろうか。宋の優れているところも見えず、わざわざ行く意味もない、とまで言う。
実朝は物見をそっと閉めた。前簾(マエスダレ)に透けて寿福寺の山門が見えてきたからだ。車輪(クルマノワ)から伝わる揺れが止まり、牛車が前に傾く。前簾が巻き上げられる。と、僧衣の者がひとり轅(ナガエ)の横に土下座している。だが笠をかぶったままだ。常ならば将軍の前では笠を取るのが作法。だが実朝は薄く微笑みかけてうなずくと山門の中へ入った。すぐ後ろに笠をかぶったままの僧侶がつき従う。
方丈へ上がると実朝は勝手知ったる館のごとく庫裏(クリ)のひとつに入った。そこは、この寺へ来たときいつも使っている部屋だった。
「三郎、しばらくであった」
ふり向いてつき従ってきた僧侶に言葉をかける。
「はい、先月の歌会以来でございますな」
三郎と呼ばれた男はそこで初めて笠を取った。すると、剃髪であるはずの頭に、まるで民の使うような萎え烏帽子がのっている。その烏帽子の脇から髪も見え、おそらく髷(マゲ)も結っているのだろう。
和田三郎朝盛(トモモリ)は、源平合戦時代からの頼朝の忠臣で実朝が祖父のように慕っている和田義盛の孫である。実朝とは同年輩で歌詠みの仲間ということもあるが、幼いころから心を許せる間柄だった。
「今日は栄西禅師もご不在ですので、いつものように殿もお出かけになるかと思いまして、このように先回りしてお待ち申し上げておりました」
言葉つきはへりくだっていながら、表情は友に向けるように気さくだ。源平合戦時代のいかつい荒武者と違って、いかにも鎌倉育ちらしい細面の若武者だ。
「うむ、そのつもりであった」
笑みを返しながら実朝は着替えを始めた。御所にいるときであれば付きの者に委ねるのだが、この寿福寺では栄西禅師から手ほどきを受けて身の回りのことはすべて自らやっていた。もし宋へ行けることになったときは何事につけそうしなければならないからだ。
「そうだ三郎、私の笠を取ってきてくれまいか」
すでに立烏帽子を外(ト)り、朝盛のような萎え烏帽子を被っていた。その格好で戸口の笠掛けまで行けば、すでに寺の僧たちには周知のこととはいえ、奇妙な出で立ちの者が寺内をうろつくことになり宜しくない。栄西禅師の何事も自分で、という教えには背くが朝盛に頼んだ。
網代笠(アジロガサ)をかぶり、墨染めの衣に脚絆を付けた雲水姿で二人は山門を出た。どこから見ても寿福寺の僧が托鉢に出かけるかのようだ。実朝を乗せてきた牛車の牛飼童(ウシカイワラワ)や侍従たちも、目の前を歩いてゆく雲水姿の男が実朝とは気づいていない。
将軍の衣を脱ぎ捨て、一介の人となって鎌倉の市中に飛び出した。縛られていた心が解き放たれる。目の上の瘤である執権も侍従も侍女もいない。自らの足で歩き、自らの目で見る。実朝にとってこの上なく心浮き立つ時が流れ始めた。
――なんと心地よい。幼きころにもどったようだ。
実朝は由比の浜に腰を下ろして海を見ていた。
笠の廂(ヒサシ)を押し上げる。陽の光が眩しい。水平線には霞のかかった大島が浮かぶ。右手には甲羅のこんもりした亀の子のような江嶋が浮かび、その背後には墨絵に描かれたような伊豆の山々が連なっていた。
広大な海が広がる。平らな海面(ウミモ)が遥か遠くまで続く。空と海の際が一線で分けられている。
――あの向こうには何があるのだろう。
幼いころ、初めて浜に立ったときから、ずっと思っていた。その想いは今でもずっと続いている。いや、想いの強さは増しているだろう。
空と海の際、そこから雲が湧きあがるように浮かんでいる。
――象とはあのような形の獣だろうか。
夏の盛りであれば仁王が立ち上がったような峯雲。それが今日はまだ見ぬ異郷の獣の形を思わせた。
「のう三郎。象という獣を知っておるか」
実朝は隣に腰を下ろしている僧形の男に顔を向けることなく、峯雲を見つめたままつぶやいた。
「はて、ぞう……にございますか? 存じませぬが……」
「宋の国のさらに西にある西域なるところにおる獣なそうな」
「西域、にございますか。では知るはずもございませぬな」
「あのような形をしているのかもしれぬ、と思うてな」
実朝は水平線から立ち上がる峯雲を指さした。
「ど、どれにございますか」
笠の前をかざして実朝の指した先を探す。絹糸が絡み合ったような峯雲は陽に照らされて銀白色に輝き、朝盛は眩しそうに目を細めた。
「あの大島に覆いかぶさるように立ち上がったあれじゃ。ほれ、大蛇のような長い鼻が見えるであろう」
実朝が言っても朝盛はぽかんと口を開けたままだ。
「体は山のように大きく、足は仏殿の柱のように太いらしい」
「で、鼻は大蛇のよう、でございますか。私にはようわかりませぬが、殿にはそう見えるのでございましょう。それにしても、ずいぶんと奇怪な獣のようにございますな」
「たしかに奇怪かもしれぬ。しかし、その奇怪なものを見てみたいとは思わぬか」
「ううむ、見てみたいような気もしますが、獲って食われるのも嫌にございますな」
「獲って食われる、か……」
――もし西域へ行けば、そういうこともあるやもしれぬ。
何に出くわすかわからぬ危うい旅となろう。
――しかし……、それでも……。
「それでも、やはり行ってみたいものだのう」
胸の中が沸き立つ。
「宋、でございますか……」
二人して水平線の向こうを見つめる。
風の音がする。波が寄せ、引くときに砂を引き摺るざわめきが聞こえる。それでも、ここは静かだ、と実朝は思う。
――まるで時が止まったようだ。
と、視界に小舟が滑るように入ってくる。
漁を終えて帰るところか、それともこれから漁場へ向かうところか、煌めく海面を静かに滑ってゆく。櫂を漕ぐきしみ音は打ち寄せる波音にかき消されて聞こえない。
――のどかだ……だが切ない。
切ないのは景色か、それともそれを見る実朝の心か……。
世の中は常にもがもな渚こぐ海人(アマ)の小舟(ヲブネ)の綱手かなしも
実朝は胸の中でひとりつぶやくように詠んだ。
「さて、今日は物作りの民たちを見てまわろうと思うが」
立ち上がりながら朝盛を見る。
「はい、では前浜へ行ってみましょう」
前浜とは、三方を山に囲まれ一方が海に面した鎌倉の海側一帯を言う。山側には入りくんだ谷戸のそれぞれに武家の屋敷があり、前浜には物作りの民や、物売りの民が暮らしていた。
「なにやら騒々しいのう」
「この辺りはいつもこうです」
武家屋敷では見ることのない大勢の人がひしめき蠢いている。着ているものはみな寝衣のように心もとなく、実朝の目には薄汚れて見えた。
通り沿いには、板きれを屋根の形に組み、そのまま地べたに覆いかぶせたような小屋が並んでいる。武家の屋敷は高床に設えてあるが、この前浜の小屋は逆に地べたを掘って住まいにしているらしい。実朝にはおよそ人の住む家とは見えなかった。鶏小屋かと思っていたら板戸が開き、中から汚れた顔の童が顔を出したのを見て、ああこれも人の住む家だったのだ、と思ったくらいだ。
(歴史探訪社『鎌倉地図草子』より)中世の竪穴式住居についての参考情報
荷を背負って忙しそうに歩きまわる者。路べたに莚(ムシロ)を広げて物を売る者。牛や馬の皮を剥いで干している所では何やら異様な匂いがした。見ると小屋の横に皮を剥がれた牛の屍が転がっていて蠅がたかっている。実朝はつい袖で鼻を覆った。
「革なめしの民にございます」
実朝のようすを見て朝盛が言う。
「革なめし?」
「はい、馬の鞍や革紐にする革を作っているのですが、牛や馬の皮は剥いで干しただけでは固くなって使い物になりませぬ。この者たちがいろいろ手を加えてようやく柔らかな革が出来上がるのです」
「ほう、そちはよう知っておるな」
「はい、前浜は子供のころからよく遊びまわっておりましたゆえ」
同じ武士でも将軍家とは違って御家人の子となるとずいぶんと縛りがないらしい。実朝は朝盛が羨ましかった。
(歴史探訪社『鎌倉地図草子』より)
「あそこに鍛冶師の仕事場がございます」
朝盛が指さした方から金物を叩く音が聞こえてくる。
「鍛冶か。聞いたことはあるが……」
太刀がどのように作られるのか話に聞いたことはあるものの、おのれの目で見たことはなかった。
「あれは見ていて飽きませぬぞ。さあ、行ってみましょう」
朝盛の足取りが軽くなった。実朝はその後をついてゆく。
小屋は他のものより少し大きく間口が開いている。そこから甲高い金槌の音が漏れてくる。
「なにやら暗いな」
「はい、火の色を見るため、とかで……」
暗闇の中で赤々と火が燃えている。白い衣の男が二人で槌を叩く。その音とともに火花が水しぶきのように散る。男たちの顔が火に照らされて、赤々と鬼のように……。
槌を振りかぶる男の顔が一瞬……。
――お命頂戴つかまつる!
無言の叫びを聞いたかに思えた。
――うむ、刺客か!
暗闇の中に燃える炎を見たとたん、疱瘡の熱に浮かされながら悪夢を見たときのことがよみがえった。
火照った体の熱気を逃がすよう、寝衣の襟元を開くと醜い水疱が胸いちめんに浮いていた。
傘の中でそっと頬に手をあてる。その感触で、あれがたんなる悪夢でなかったことを思う。
「いかがされました?」