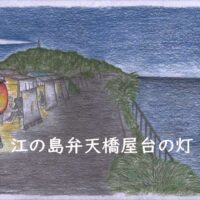■前回までのあらすじ
疱瘡を患った実朝は、熱にうなされて自らの首を切られる悪夢を見、自身も兄や父のように殺されるのではないかという疑念を抱く。やがて疱瘡が癒え、鏡に映った自身の顏を見て失望するが、師の栄西から授かった『大唐西域記』に、未知の西域への想いを馳せた。武芸も好んで励んだが、義時の前では武芸下手の和歌好きを演じる。幼友達の和田朝盛とともに托鉢僧の姿に身を隠し、鎌倉市中を視察。庶民の目線で歌を詠む。鍛冶師の仕事場へ来たとき、暗闇に燃える炎を見たとたん、疱瘡の熱にうなされながら見た悪夢がよみがえった。
「いかがされました?」
朝盛の声で実朝は我に返った。
「いや、なにも、ただ、暗うてあれが何か……」
鍛冶師の叩いているものを指さす。
「あれは、まだ太刀の形をなすまえの鋼(ハガネ)の塊です」
「鋼、とな? だが赤々と燃えておるぞ」
このとき実朝は鉄(クロガネ)が燃えるはずはない、と思った。
「熱くした鋼を叩いて鍛えているのです。あれを何度も繰り返すことで折れにくい太刀の芯を作るのです」
朝盛は何も知らない実朝に鍛冶の仕事を説明しはじめた。
「あの鍛冶師は出雲の国からやってきたそうですが、この鎌倉には鉄の砂が豊かにあると申しております」
「鉄の砂? それは……」
「この鎌倉の砂浜は黒ずんだ色をしております」
「そういえば、伊豆の浜に比べると……」
実朝は将軍に就いてから頼朝以来の恒例行事である二所詣に出向くため伊豆の海を何度か見ている。伊豆山権現と箱根権現に参詣するためだ。
箱根路を我が越えくれば伊豆の海や沖の小島に波のよる見ゆ
あの歌を詠んだときの浜辺が目に浮かぶ。
――たしかにあの砂浜は白く輝いていた……。
「鎌倉の黒い砂は、じつは鉄(クロガネ)なのです」
「なんと、ならばいくらでもあるではないか」
「げに」
朝盛はうなずいてにたりと笑った。
「となれば鎌倉は鉄に困ることはないな」
「ですのでこの鍛冶師も鎌倉に居を構えたと申しておりました」
どうやら朝盛は子供のころから前浜の民に馴じんでいて知り合いも多いらしい。
――それにしても。
と実朝は思った。鉄の砂を鋼に鍛えあげ、太刀にするというのはなんと骨の折れる仕事……。
「あの宋の国ではどうしておるのだろう……」
ふと、つぶやいた。そして西域では……。象という恐ろしい獣を飼いならし、黒い泥のような油を井戸から汲み上げて火を焚いているという。そんな民ならば鋼の作り方もまた違うやもしれぬ。目の前に幻の大地が浮かびあがる。
「宋?」
朝盛が笠を押し上げ、笠に隠れた実朝の顔を窺がい見る。
「いや、なんでもない」
朝盛が知るはずもない。幻の大地への想いを断ち切るようにその場を離れた。
路地に莚を敷いて物を売る者たちがいる。干した魚、柿の実、梅干しなどの食べ物を売る横で茶碗、皿などの陶器を並べる老人がいた。みな素焼きで艶のない陶器ばかりだった。
「青磁はないのだな」
肩を並べて歩く朝盛に小声で言った。
「このあたりで青磁を売る者はおりませぬ」
笠に隠れて見えないが、朝盛は苦笑するような声で言った。
「さもあろうな」
実朝もわかっていながら言ったまでだ。あの青みががかった艶のある磁器が実朝は好きだった。うすく雲のかかった空のような色。美しい、というだけではない。その器が宋からもたらされたものだと思うと、それが焼かれた場所の景色も目に浮かぶような気がした。
「あのような艶のある器は鎌倉では作れんのだろうな」
「はい。惜しいことですが、そう聞いております。いろいろ試した者もいるようですが……」
「うむ、あれを焼いているところを見てみたいものだな」
無いものねだりと知りながら、つい口から漏れた。
「殿はやはり宋、なのでございますね」
朝盛の言い方にはどこか憐れむような響きがあった。
路地を歩いていると、どこからか子の泣き声が聞こえてくる。と、小屋の軒下で立ちすくんだまま大きく口をあけ、涙を流す子の姿があった。袖のないうす汚れた衣、藁縄(ワラナワ)を腰に結び、泥だらけの足をむき出しにしている。道行く者はちらりと見るだけで通りすぎてゆく。
「どうしたのであろうの」
実朝の足が止まった。
「おおかた親に叱られてしめ出しを食らっているのでございましょう」
朝盛はどうということのない言いぶりだ。
「そうであろうか」
子の泣く姿は珍しいものではない。だが、武家の館ではあのようにいつまでもしゃくり上げるように泣きつづける男(オ)の子を見たことがない。涙を流すことはあっても、いつまでも声をあげて泣くことは許されなかった。
「ならば、少々お待ちを」
言って朝盛は泣く子に近づいていった。笠をあげ、子に顔を見せて何やら問いただしている。だが、子はしゃくり上げるだけでまともに応えていないかに見える。朝盛は、あきらめたように子を離れ、こんどは路の向かいで蓆を広げて商いをする男に声をかけた。しばらく話をしてもどってくる。
「どうやら親を亡くしたようにございます」
「二親ともか?」
「いえ、つい先ごろ母親が病で死んだそうですが、父親は行商に出たまま、もう幾年ももどらないとか……」
「では、あの子はどうなるのじゃ」
実朝の問いに朝盛は応えない。が、ひとつため息をつくと、
「よくあることにございます」
捨ておくようにつぶやく。
「よくあること……」
朝盛の言葉をなぞるように言い、ふと思った。
自分も、幼くして父親を失った。だが、母親はいるし、住む館もあった。だが……兄、頼家の子、あの善哉は……、父を殺され、母親も……。それでも養父がつき、住む館もある。暮らしに不足はなかったはずだ。だが……、血のつながった親がいないことに、ふと気づいたとき、恐ろしいほどの寂しさに襲われ、夢の中で声を上げずに泣いたことはなかっただろうか。
軒下で立ちすくんで泣く子を見たとたん。あの善哉の顔が浮かんだ。
強い武士になりとうございます。
幼いながら凛とした声で応えていたものの、人知れず泣いたことはなかっただろうか。
「なんとかならぬのか。誰か引き取る者はおらぬのか……」
妙案のないまま朝盛の顔を笠の上から見つめた。
笠に隠れた朝盛の顔が大きくため息をついたのがわかった。踵を返し、また陶器の商いをする男のもとへもどってゆく。蓆の前にしゃがみ、男と何やら話している。僧衣の懐から何かを出して渡したようだ。商いの男の顔がほころぶ。その顔を見届けたかのようにしてもどってきた。
「あの子を石切り場の親方のところへ連れてゆくと申しております」
「石切り場?」
鎌倉は谷戸の奥を切り崩して壁を作り、切り崩した石で崖の前を整え、そこに館を建てる。そうして守りの固い武家の屋敷を造ってきた。山から切り出した石は館の土台になるとともに、塀、石段、路の普請、とあらゆる造り物に使われる。そういった普請用の石はいくらでも要り用があった。
「石切り場ではいくらでも人手がいるそうです」
「あの子供が石切りをすると申すのか」
実朝の頭に崖の上での危うい作業風景が浮かぶ。
「まあ、幼ければ幼いなりの用事があるのでしょう」
なだめるような朝盛の言い方に、実朝もようよううなずくしかなかった。自分は望まずして将軍という地位に就いた。そして兄、頼家の面影のある幼子も……。
おそらく、あの善哉も望まずして僧侶になるのであろう。ならば、あの子も……。
実朝は振り切るように泣きじゃくる子に背を向けた。
いとほしや見るに涙もとどまらず親もなき子の母をたづぬる
胸の奥がしめつけられる。御所での暮らしでは決して湧くことのない想いだった。
木戸を開け閉めするような音がとぎれとぎれ聞こえてくる。
実朝の足が音のする方へ向かってゆく。朝盛はあとからついてくる。ここはもう何度も来た路だった。やがて音は足踏みするような定まった間隔で響いてくる。それは機織りの筬(オキ)を引き叩く音だ。
小屋の戸口がわずかに開いている。音はそこから漏れ出てくる。
実朝の足が止まる。朝盛もすべて承知しているかのように無言で止まる。
通りすがりの僧侶が二人。托鉢の僧であれば路で立ちつくしていてもそう不自然ではない。
開いた戸口から明かりが漏れ、小屋の中が見える。そこに機を織る娘の後ろ姿があった。前に来たときは夜だった。月の明かりに照らされた横顔を垣間見たとたん胸の中が熱くなった。化粧で飾ることもないのに透き通るような肌。御所にいる侍女たちにはない白菫(シロスミレ)のような清廉さ。それがそのまま胸の中に残像となって刻まれ、忘れられなくなった。
――こんな想いは初めてだ。
蜜柑のように甘く酸いのに、胸がしめつけられるように苦しい。その顔を思い浮かべれば息をするのも忘れてしまう。
実朝が齢十三で正室を迎えるとき、最初は足利義兼の娘を薦められた。だがそれを拒んだのは父や兄と同じことになる、という直感だった。御家人の娘を迎えれば、その家は外戚となって力を増し、やがて必ず争いの種になる。ならば京の公家のほうが……。
正室を迎えるということは政(マツリゴト)のひとつであって、当人への気持とは係わりがなかった。はるばる京からやってきた信子を初めて見たとき、ときめくものが露ほどもなかったと言えば嘘になろう。だが、それは離れて育てられていた妹と初めて対面したかのような気持に似ていた。それがようやく女として見るようになったころ、疱瘡の病に襲われた。病が癒えたと思い、いや、少なくとも実朝自身は癒えた、と思った。なのに信子は、あからさまではなかったものの、忌み嫌うような気配を漂わせた。ほんの微かな態度の移ろいではあったが二人の間にするりと垂れ幕が降りたかのように感じた。透けて見えるほど薄い幕ではあっても、それは心と心を遮る壁になった。鏡に自身の顔を写してみれば、それもうなずける。だがあのとき、実朝の心は凍てついた滝のごとく冷え固まった。夫婦とはいえ、それは形だけ、気持は通っていない。そう感じたとたん陶の器が手からすべり落ち、音もなく砕け散った。それでも日々の暮らしは変わらない。将軍とその正室という関わりは誰の目にも前と同じに映っているだろう。この朝盛をのぞいては……。
「こうしているだけで宜しいのでございますか」
背中から朝盛がそっと声をかけてくる。
「うむ、これでよい」
本心とは裏腹の言葉が口をつく。
「せめて歌など届けましょうか」
朝盛が懸け橋になると申し出ている。だが、
――せめて歌、だと?
歌のやり取りならば顔を見られることがない、ということか。
捻じれた腹立たしさがじわりと湧く。心を許しあっているはずの朝盛にまで……。
「歌を嗜まなければいかがする」
返事がなければ、嗜みのせいなのかどうかも分からず、ただ悶々とするだけだろう。
「そのときはそのとき。何事も試してみなければ……」
煮え切らない男に匙を投げた、というような顔をしたに違いない。笠に隠れていても幼友だちの言葉つきで分かった。
――三郎。そちには分からぬ。
試して、もし女の気持が自分に傾くようなことがあれば、会わずにいることがかえって苦しくなる。そうなれば……。
気持が通じていると思っていた朝盛に、やりどころのない苛立ちを覚えた。
ふと機織りの音が止まった。それにつられて小屋の中を窺がう。と、女が立ち上がったのが見えた。
――また、あの横顔が見えるやもしれない。
心が浮き立ち、面がぽっと熱くなる。耳の奥で心の臓の脈打つ音が聞こえる。と、小屋の中に、もうひとつの影が現れた。萎え烏帽子の……職人だろうか。それとも父親だろうか。あるいは兄弟か。この小屋になぜいる。見つめていると顔の子細が見えてくる。若い……男、だった。
女が戸口に寄ってきて、待ち焦がれていたあの顔が、見えた。そして戸が閉まる。月は一瞬輝き、そして雲に隠れた。
そのまま機織りの音は聞こえてくることはなかった。
月影のそれかあらぬかかげろふのほのかに見えて雲がくれにし
源実朝。このとき齢十九の春だった。