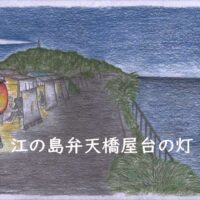この記事は前回からの続きです。
■前回までのあらすじ
宮崎で幼少のころからサーフィンに明け暮れていた智志(サトシ)は、プロサーファーになったとたん、自身の人生はこのままで良いのかと悩みだす。テレビで災害救助に励む自衛隊員の姿を見て自衛隊員になろうと思い立ち、かつて海軍予科練に入隊した祖父に相談するが、なぜか色よい返事がなかった。
大波サーフィンのメッカ、鎌倉稲村ヶ崎を訪ね、波待ちをしているとき、地元(ローカル)の裕二と知り合い、二人で稲村ヶ崎の洞窟を探検する。洞窟の暗闇で波乗りに明け暮れる生活について語り合い、打ち解ける。
行き止まりと思った洞窟に横穴が続き、そこで見たことのない円筒形の金属缶のような物を見つける。智志は、それが祖父、吉次郎の話してくれた、ある物ではないかと、祖父の予科練時代の話に想いを馳せる。吉次郎は愛国の想いと飛行機への憧れから予科練に入り、難しい課業と厳しい罰直に耐え、晴れて飛行練習生となった。だが、飛行訓練の始まる直前、総員整列がかかり、分隊長から、戦況の悪化から飛行訓練は中止と宣告される。それからは「土科練」と揶揄される土方作業に明け暮れる毎日であったが、ある日、極秘の危険な作戦への志願打診があり、吉次郎は志願する。作戦の内容を知らされないまま久里浜対潜学校へ転属となったが、そこで見たのは、不審な死を遂げる兵たちだった。
***
鼻から吸って口から吐く。鼻から吸って口から吐く……。
それを頭の中で念じながら、息を吸い、そして吐く。
――これを誤れば……。
命はない。
ここまで潜ると陽の光はわずかしか届かない。夕暮れから夜の闇に包まれるころのようだ。その暗がりの中を、水の抵抗をかき分けるように前かがみになって歩く。
寒い、冷たい。下腹部が膨れ上がるような圧迫感。
――小便がしたい。
管が尿袋に繋がっていて排泄はできるようになっている。出したいのにどうしても出ない。どうやら水圧のせいらしい。その違和感がしだいに大便のほうに変わってゆく。「大」のほうは排泄装備がない。どうしても我慢できなくなったら……。まだそこまでの覚悟はできていなかった。

暗がりの中にゆらゆら揺れる黒い帯のようなものが絡み合って塊になっている。海藻の森だ。藻は背丈よりも高い。今日の訓練計画ではそこを突っ切っていかねばならない。藻に手を掛け、かき分ける。その奥は何も見えない暗黒の世界。ふと、噂に聞いた話が頭を過る。訓練で潜ったまま上がってこなくなり、そのまま行方不明となった者がいるらしい。行方不明といってもすでに生きているはずはない。この海底のどこか、もしかしたらこの海藻の森の中に……。ふと、先日訓練中に救助されたものの死亡した隊員の顏が浮かぶ。隈取のような青筋を立て、目を剥いて苦しそうに死んでいった……。そのときのことが頭から離れない。そのまま暗黒の森に踏み入る。と、闇の奥から、ぬっ、と何かが顔を突き出してきた。
うっ、と声にならない叫び声をあげ、息をのむ。顔を背けようとしたが装備のせいで急には体が動かない。が、どうやら、海藻の影で休んでいた魚かタコが驚いて飛び出してきたようだ。ほっとした。だが、ふと気づくと決められた息の仕方を忘れていた。
――落ち着け。鼻から吸って口から吐く。
念じながら、吸って吐き、呼吸を整えた。
――危くおいも死ぬところじゃった。
飯を食う時以外はふだんからいつもその呼吸法をするように口うるさく指導されていた。
「俺は整備に回されたよ」
訓練が始まって間もないころ、同僚のひとりが肩を落として言った。
「鼻から吸って、が出来ないと言ったら検査に回されて、軍医に蓄膿症と診断されたんだ」
鼻ではなく口で息をしたのでは致命傷となる。
――鼻から吸って口から吐く。
暗く、冷たい海底で、いったい俺は何をしているのだろう。
予科練に入ったのは飛行機に乗って大空を飛びたかったからだ。青い空、眩しいほど輝く太陽。足の下に真っ白な絹綿のような雲が広がる。
今日も飛ぶ飛ぶ 霞ケ浦にゃ でっかい希望の雲が湧く
空を飛ぶ夢と希望を抱きながら、予科練のあの歌を何百ぺん歌っただろう。なのに……。
「貴様たちは帝國海軍の切り札だ!」
久里浜対潜学校に着任してすぐ座学の開講にあたって先任士官の訓示があった。
「すでに敵は目前に迫っている。神風特攻隊は敵に甚大なる打撃を与えることはできたが、全ての軍艦を沈めることはできない。いずれ敵機動部隊は本土上陸を狙ってくるだろう。今、海軍はそれを水際で殲滅する作戦を計画している。その成否は貴様たちの双肩にかかっている!」
夏なのに海軍士官の軍服は白の第二種軍装はあまり見られなくなった。声高に話す先任士官は新たな軍装である第三種、つまり青褐色の一見陸軍の軍服に似たものを着ている。あの粋な海軍が外見をかなぐり捨てて本土決戦の構えを示威しているようだった。
「おそらく敵は艦砲射撃を仕掛けてくるだろう。それには地下壕の中で耐えるしかない。だが軍艦に積める砲弾にも限りがある。弾切れになるまでじっと待つのだ。そしていずれ上陸用舟艇が向かってくる。そのときこそ貴様たちの出番だ」
短期間ではあるがここで訓練を積み、その時に備えよ、という言葉に続き作戦名が告げられた。
「伏龍(フクリュウ)作戦である!」
ひときわ力のこもった言葉が響く。
「貴様たちひとりひとりが伏龍の隊員だ。頼んだぞ!」
先任士官の訓示はその言葉で終わった。
――フクリュウ、じゃと? いったっちゃそいは何だ。
先任士官が退室すると、そばにいた白い事業服の教員が立ちあがった。
「これからおまえたちに伏龍の装備を見せる」
言い終わるやいなや、廊下のほうから何かを引き摺るような重い音が響いてきた。車輪の音ではない。地に響くような足音。重く、硬い……。ふと、巨人や化け物の類が頭に浮かぶ。背筋に冷たいものが走った。
戸が開く。まず入ってきたのは事業服の男だった。おそらく整備兵だろう。ふり向き、何かを招き入れるように合図する。重く、硬いものを引き摺るような音。その響きで戸のガラスがびりびりと震える。とても人間の足音とは思えない。得体のしれない黒い影が戸の曇りガラスに映る。吉次郎は自身の心臓の音を耳の奥で聞いた。
―― 伏龍……、そいは……。
はたしてそれは人間か、それとも……、思わず身構える。
姿を現したのは厳つい装備を纏った……人間、だった。黒いゴムのような服が異様な雰囲気を醸しだす。怪物のようなものが現れるのかと身構えたが、見慣れない装備を纏っているものの、胴体の上から出ているのは人間の坊主頭だ。それを見て少しだけほっとする。
「黒岩一飛曹、兜(カブト)を被ってみろ」
教員の言葉で異様なゴム服の男は、抱えていた円筒形の金物を頭に被ろうとした。横についていた整備兵が向かい合って補助する。頭から顏全面を覆う兜なるものが載ると、それはやはり異様としか言えない姿だった。金属で出来た重そうな円筒形の兜には丸いガラス窓がついていて、まるで金属缶の一つ目小僧が潜水服を着ているようだった。

「あんときは化け物でん出て来るんかと思ったじ」
吉次郎は、その時を思い出すかのような目をして小さく笑った。
「今ならばアクアラングというんかな」
祖父がそんな言葉を知っているのに智志は少し驚いたが、
「スクーバダイビングちゃか? でん、あん時代じゃったら、船の上からホースで空気を送るやつ。ごっつい覆面鉄兜みたいの被った」
いわゆるヘルメット式潜水具ではないかと思った。だが、
「いや、そげんなもんじゃあん。酸素瓶(ビン)と言ってな、酸素を入れたボンベを背負うじゃっとよ」
「スクーバじゃったら圧搾空気ちゃが」
「じゃっど、そこがまこち違う」
そのボンベからホースで潜水兜の後頭部に酸素を送り込む。吐く息は兜の中にある排気口に口を付けて吐き出す。
「その排気口の先にあんもんがくせ者さ。清浄缶と言ってな」
薄い金属の缶に苛性ソーダの顆粒を詰めたものを腰につけて、排気が中を通ると二酸化炭素が吸収され、再び吸気へつなげる。通常は外へ排出しないで循環させるので水中に気泡を出すこともない。だから敵に発見されにくい。そこが空気のボンベを使って排気が泡となって出るスクーバダイビングとは違う。

「じゃけんど、やっかいなこつに、口元の排気口から間違って息を吸い込むと苛性ソーダを吸いこんでまう。じゃあなったら喉や肺がただれて息ができなくなる」
いわゆるチアノーゼの症状を呈し、場合によっては死に至る。
「おまけに清浄缶の缶が薄くて、少し岩に擦っただけで破れちまう。そうなったらたまらんちゃが」
苛性ソーダが海水に反応して沸騰し、管を逆流して口元の排気口から噴出する。口から喉、肺まで爛れて息ができなくなって死ぬ。
「ほとんどの事故はそいじゃった」
吉次郎は暗い闇を見つめるような目をした。
「そうか、だから鼻から吸って口から吐く、じゃったんね」
智志は青紫色に爛れた顔でチアノーゼに苦しむ若者を想像して目に浮かべた。
「海底を歩かにゃなんねえんで、鉄わらじを履くのさ」
重く硬いものを引き摺るような足音は鉄わらじのせいだった。片足だけで1キロある、鉄とはいっても長さ30センチの鉛厚板を潜水ズボンの上から足に縛り付ける。そしてその重装備で水中を浮上したり沈降したりできるよう訓練しなければならなかった。腰にある吸気弁を開き潜水服内に酸素を満たしてゴム毬のように膨らませ浮上する。逆に、潜水兜の内側についている排気弁をこめかみで押すと潜水服内の気体が外へ出て、このときだけは気泡が出るが潜水服は萎んで沈降する。
「浮上する技を使って上陸用舟艇の船底を機雷で突いて爆破しようというわけさ」
五式機雷といって15キロの爆薬が詰まっている。それを5メートルの竹棒の先につける。
「爆発すりゃあ半径50メートルの範囲内は木っ端みじんさ。敵も吹っ飛ぶがこっさもいっしょだ。だから特攻じゃったんだ」
―おまえたちだけ往かせることはしない。こいつの使い方を教え終わったら、俺も往く。だからおまえたち、俺が往くまで靖国の鳥居の前で待っていてくれ―
「あんときの教官はそんげ言うてた」
戦争で死んだ者は靖国神社に祭られ、軍神となる。自分もあとから行くから一緒に鳥居をくぐろう、というわけだ。
「軍神というこつは、神様になるというこつね」
「じゃけんど、そいがどんげじゃっとよ」
死は死でしかない、というようなことを小さくつぶやく。
「棺桶の蓋が閉まるのを、中から見ちょるごつ……」
「棺桶?」
「ああ、あん潜水兜被るときは、そげんな気分じゃった」と暗い目をしてつぶやく。
ブリキのバケツを伏せたような潜水兜。そこには丸窓がついていた。兜を四本のボルトで潜水服の肩に固定する間、まだ窓は開いている。だが、実際に潜水するときに、整備兵が丸いネジ式金属枠のガラスを窓にねじ込む。
「ギュル、ギュル、て音がしてな」
実戦のときであれば、その音とともに丸窓が閉じた瞬間、それまで生きてきた世界と隔絶される。
「まるで棺桶の蓋を閉める音に聞こえたじ」
そのときを見つめるような遠い目をする。
「もう二度と陽の光を見るこつはんじゃろ。そんときは何を想っちょるんかな。お国、天皇陛下……、いや、母さん、父さん、兄貴、友人。故郷の山か……」
冷たい海の中では小便もしたくなる。腹を下すかもしれない。
「じゃあなったら、糞まみれだ。臭えじゃろうな。そげんなんで死なんならんのは、ほんじゃこつやるせんもんだ」
そう言って小さく笑ったものの深い井戸を覗くような目をした。
「そいでも船のエンジン音、スクリューの回る音を聞き逃してはいけん」
敵の上陸用舟艇が近づいて頭上に来るのを見計らって吸気弁を開いて浮力をつけながら海底を蹴って浮上、竹槍の先に付けた機雷で船底を突く。
「敵艦もろとも自分の体も木っ端みじんじゃ」
そうなっていたら自分は軍神になったのだろうか、と吉次郎は暗闇を見つめるような目をした。
「荷台に幌を被せたトラックに乗せられた」
どこへ連れていかれるのか分からなかった、と吉次郎はそのときを思うよにつぶやく。
「荷台にツルハシとモッコも積まれちょったんで、またドカレンかと思ったじ」
トラックを降りてツルハシを担ぐとモンペ姿の女性に、ご苦労様です、と頭を下げられた。それで、はっと思った。
「防空壕掘りじゃったら、民の命の隠れ家作っちょるごつなもんじゃから、そいはそらで意味があん。そげんな仕事でん一生懸命やろう、というごつな」
智志はふと、災害救助で懸命に働く自衛隊員の姿を思い浮かべ、祖父の若き頃の姿と重ね合わせた。
「じゃけんど、そこは防空壕じゃあんかった」
すでにそうとう奥まで掘られていたという。
「切通しの谷間で、山の中かと思ったけんどん、どげんか潮の匂いがしたつ」
崖に掘られた穴から入ると、ところどころに電灯が燈り羨道内は暗いながらも照らされている。まっすぐだが緩やかに坂を下るように掘られている。やがて光の入る口が見えてきた。潮の匂いがきつくなる。それは磯の匂いだった。眩しい。出たところは岩棚になっていて、そのまま海に沈みこんでゆく。

「そいでようやく合点がいったじ」
そこは伏龍の出撃基地だったのだ。
「眩しい磯で、海が光っちょった。遠くにもっこりしたつ亀の甲羅のごつ島が浮かんじょった」
そのときを思い出すように遠い目をする。そして、それが江ノ島という島だということをあとで聞いたという。
「湘南の江ノ島か」
智志は雑誌で何度も見たことのある風景を頭に浮かべた。
「入口は岬の根本にあん切通しの崖にあって」
そこから縦断するように地下トンネルを掘り、岬の突端から海中へ入ってゆく伏龍の出撃基地。主羨道から上方へ逸れて二つの穴が開けられ、そこは銃座となっていた。伏龍の攻撃前線を突破して上陸してくる敵の舟艇を狙い撃つ最後の砦となるのであろう。
「稲村ヶ崎、ちゅうとこじゃった」
吉次郎の言った地名に智志は思い当たるものがあった。
――ああ、あのイナムラか……。
智志の頭に浮かんだのは特攻基地ではない。雑誌やサーフィンビデオで見た大波のメッカ、イナムラだった。
「じゃが、そこで玉音放送を聞いた」
伏龍の装備を稲村ヶ崎基地に運び込み、待機し始めて間もないころだったという。
敵の上陸用舟艇に突撃して身は粉々になって軍神となる。
「そんつもりじゃったけんど、結局戦争は終ってしもた」
「命拾いした、てこつだ。よかったね」
そうでなければ自分もこの世に生まれ出なかった。そう思うと智志自身までほっとした気持になる。
「だけんどん、すぐにはじゃあいう気持にはならんかった」
吉次郎は果てしない虚空を見つめるような目をした。
「母さん、父さん、ほいでみんなを守るために予科練に入った。痛え罰勅も我慢してかいよ、乗りたかった飛行機にも乗れんかったけんど、みんなを守るために、あんげな伏龍の訓練にも耐えてきた。頭の中はみんなを守るため、それだけじゃった。なち、ぜんぶすっぽり無くなっちまって……」
自分は何のために今まで生きてきたのか。これから何のために生きてゆくのか。わからなくなって、頭も心の中も空っぽになったという。
終戦から数日たった日の朝、稲村をはじめ相模湾一帯に突如、薄い灰色の軍艦がびっしり沖を埋め尽くすように現れたという。まっ黒な帝国海軍の艦ではない。米国の太平洋艦隊に間違いなかった。

「まさか上陸して来なるのかと思ったじ。伏龍の出撃もあんかと思った。だけんど、すぐにいなくなっちまった」
勝ち誇った者が自身の威厳を見せつけて見得(ミエ)を切り、くるりと背を向けて去っていったようなものだった、と吉次郎は言う。
「あれを見たときは、とても伏龍では太刀打ちできねえ、て思ったじ。爆弾抱えて突っ込んだって、あん大きな船と数にはとても……」
言って目を伏せ、首を横にふる。
「今思えば、まこち馬鹿なこつ考えたもんだ。力で国を守ろうとすっと、そん力が尽きたときには、あんげなとんでもねえこつ考える。破れかぶれ、ちゅうこつだ」
竹槍の先に機雷を付けて浮上して当てにいっても走航する船に当てるのは至難の業。それより機雷を施設したほうがよほど確実に当てることができたはず。命を無駄にすることもない。
「そげんな馬鹿げたこつにもおかしいと気づかん精神状態になっちょった……」
ため息をつき、虚ろな目で遠くを見た。
―ハナカラステ、クチカラ…… ―
ときどきわけの分からない言葉を口走っていた吉次郎は先月亡くなった。だが、けして呆けていたのではなかった。
眩しい。
智志は裕二と並んで洞窟前の岩棚に立ち、沖を眺めた。
陽が西に傾いて江ノ島の展望灯台にかかっている。
「なあ、この海の向こうから敵が攻めてきたらどうするよ? おまえ」
智志はライトグレーの戦艦が沖をいっぱいに埋め尽くした景色を想像してみた。
「え、敵? 戦争になったら、てこと? んなこと……」
裕二は一瞬、馬鹿々々しいというような顔をしたあと、ふと考えるような顔つきをした。が、
「そうだな、やっぱ逃げるっきゃないでしょ」
言ってハハハと笑った。
「おまえ、そげんこつで……」
智志は言いかけて口をつぐんだ。
「あ、だから、おまえ自衛隊に? でも、鉄砲で撃ち合えばどっちかが死んじまうじゃん。だったら逃げまくったほうが……そのほうがお互いのためさ」
そう言った裕二はもう笑っていない。
「どげんかこへ逃げると言じゃっとよ」
言っても無駄な奴……。そう思って吐き捨てた。
波が岩棚に打ち付けて白い飛沫が飛び散る。
「それよか、潮が動き出したぜ。今日は大潮だし、これからよくなりそうだぜ、波。夕方もう一回やるか」
裕二が沖を見つめて言った。いついい波が来るか。そのとき自分が波乗りできる状態にしておくこと。それが今の裕二の最大の関心事なのだろう。
俺は……。
智志は上げ潮の入った気配のある海面を見、そして遠い水平線に目をやった。
おわり