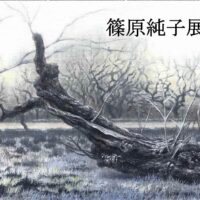■前回までのあらすじ
大学で考古学を学んだ憲二は、恩師、吉田教授と小町裏通りのスナック[段葛]で歴史談義する中、[段葛]の女将(ママ)は鎌倉時代を、まるで見てきたかのように語りだす。
実朝は疱瘡を患い、熱にうなされて自らの首を切られる悪夢を見、自身も兄や父のように殺されるのではないかという疑念を抱く。やがて疱瘡が癒え、鏡に映った自身の顏を見て失望するが、宋への憧れは抱き続けた。和田義盛が乱を起こすが、幼なじみの和田朝盛からの手紙で、和田に謀反の心はなく、義時への抵抗だったことを知るも和田は滅んだ。
陳和卿(チンナケイ)という宋国出身の僧が、実朝に面会を求めてやってくる。義時は、よく思わなかったが、実朝は喜んで和卿を受け入れる。唐船があれば宋に行けるという話になり、和卿は船の模型を作って、帆走の実験をしてみせた。

横から見ていた和卿が笑みを浮かべる。
「いかがてすや?」
「これは驚いた。いや、じつに驚いた」
小さな船の雛形は木の葉のように風下の吹きだまりに流れてゆくかと思っていた。なのに……。
いちどはこわばったもののやがて実朝の顔に笑みが浮かんでくる。
「あれが竜骨の働きなり。竜骨があれば船はどこへても行けます」
「どこへでも?」
「はい、もし風が行きたい場所、つまり真向かいから吹いていれば、はす向かいに風を受けながら進みますなり。行きたい場所を斜め前に見ながら進むことになりますなり。それてもこんどは舳先を転じて反対側から風を受けながらまた斜め前に進むなり。それを繰り返せば、風上の正面でも行けるのでありますなり」
「なるほど……」
実朝は和卿の説明を頭に描き、そして得心した。
「そちの言う、横に受ける力を止めると前に進む、という辺りの道理はいまだようわからぬが、その竜骨のある船が風をはす向かいより受けながらも進むことができる、ということはこれを見てようわかった」
腕を組んで大きくうなずき立烏帽子を縦に揺らした。
「道理のほうも、こんとは絵に描いてご説明しますなり」
いかつい下膨れ顔がほころぶ。
「うむ、これならば風向きにかまわず、どこからでも宋へ行けるな」
この雛形の船と同じ形で大きな船を造ればよいのだ。海の彼方にあるはずのまだ見ぬ宋。その幻影が現実味をおびて実朝の目に浮かび上がってくる。
「はい、この鎌倉から行けますなり」
背の低い和卿は実朝の顔を下から覗き込みながら言った。が、その顔はもう笑っていない。何かを確と見つめている。
「そちの意は宋へ帰ることであろう?」
実朝は獲物を狙う猟師の目に向かって正すように言った。
「この国のために二十五年働きました。もう帰していたたいても……」
――この男の意は[帰る]こと、か。
実朝の想いは[行く]ことだ。想いの方向は違えど、目指すところは一致した。
――よし、行くぞ!
実朝は空を見上げて腹をくくった。
御所の裏手でまた蝉が鳴き始める。鳴き声はひとつでなく、いくつも重なってゆく。その姦しさが増すにつれ、 行け! 行け! と、まるで実朝の気持ちを囃し立てるかのようであった。
*

建保四年十一月二十四日。実朝は寝殿に鎌倉の主だった者たちを集めた。執権の北条義時を筆頭に、政所別当の大江広元、三浦義村をはじめその他の御家人たちが居並ぶ。末席には宋人、陳和卿が侍っていた。
「皆の者よう聞け」
寝殿に侍る御家人たちを見回す。おそらくその声に、いつもとは違う張りを感じた者も多かっただろう。
「吾は宋国の医王山に詣でることとする」
言ったとたん寝殿内に小さなざわめきが起きた。あからさまに声をあげる者はいないものの、将軍が自ら宋へ行く、と言ったかに聞こえたのは聞き違えか。あるいは、[そう国]とは[相州]のことか。つまり正月恒例の行事である二所詣、頼朝の代から続いている伊豆国伊豆山権現と相模国箱根権現に将軍が詣でるあの行事が、来年は少し違う形になるということだろうか、と思った者が多かったようだ。ただ、義時と広元は、案じていたとおり、ついに若将軍が戯言を言い始めたか、と思ったに違いない。
「ついては、ここにいる宋人、陳和卿に唐船の建造を申しつける」
いつになくきっぱりと言った。和卿は平伏したまま、さらに額を床に押し付け、申しつけを拝受した旨を示した。
寝殿内のざわめきが大きくなる。二所詣のことではない。将軍自身が宋へ行くと言っている、ということがようやくわかったらしい。
「殿、お待ちくだされ。船の建造となると、そうた易いことには……」
義時が頭を起こす。
「誰がた易くと申した。大変な事業(イトナミ)と心得ておる」
言って毅然とした顔をする。そして、
「先般、栄西禅師が亡くなられた」
そこで絶句し、神妙な面持ちをしてみせる。が、図らずも禅師の顏が目に浮かび、熱いものがこみ上げる。
「まことに無念ながら、鎌倉に禅を広める志半ばでご逝去され、今、吾らは進むべき道の光を失ったも同じである」
また言葉を切り、無言で一同を見回す。と、大きくうなずく者、苦々しい表情を浮かべる者、様々な表情が目に入る。そこで意を決したような顔をしてみせる。
「ついては、この鎌倉は、宋国より師となる僧を招かねばならない。吾はそのために渡宋するのである!」
目に力をこめ、ひときわ声を大にしてきっぱり言ってのけた。最初は演じていたつもりが、話すうち、胸の中に熱いものが迸った。
禅師は生前、禅は暗闇に灯るただひとつの明かり。この鎌倉に禅は無くてはならないもの。自分が往生した後のことを思うと、真に禅を修めた僧がぜひとも必要。そのような僧は、今は宋にしかいない、と仰っていた。だから禅の高僧を鎌倉へ招こうとする気持に嘘偽りはない。だがその高僧が見つかったときには……、その後自分はそのまま西域へ旅立つかもしれない。その時こそかねてからの想いを叶えるときだ。
――相州よ、いつまでもそのほうの意がままにはさせぬぞ。
胸の中の想いをぶつけるように義時を見つめた。
「船を造るとなれば、あまたの材木、船大工、それに……」
義時が少し慌てたように言いかける。が、その言葉を遮ってたたみかける。
「なまやさしいことではない。寺院を建てるに余る覚悟でやると申しておるのだ。寺を建てるには様々要り用があって然り。だが最も大切なるは多くの僧を導いてくれる老師ぞ。それを武門の棟梁であるこの吾が自ら請いに出向くと申しておるのだ」
胸の中に疚しい気持も無いことはなかった、が、それを吹き払い、自らの気持を鼓舞するごとく強い言葉を吐いた。これまでの実朝を知る誰もがおそらく気圧されたことだろう。一同の表情を見ても、それは確(シカ)と認めた。武門の棟梁と明言したことで、執権義時としても御家人たちの手前、将軍を諫めるような物言いはできない。それに幕府の棟梁として神仏を祭ることについては執権ではなく将軍の任という暗黙の了解もある。これはまさに祭にかかわることだった。
「はは……」
義時が皆には聞こえぬほど小さな声で頭を下げた。
広元も何か言いたそうな顔をしたが、そのまま下を向く。
――よし! 勝った。ようやく……。
実朝は袖の中で拳を握りしめた。
ただの一歩に過ぎない。しかし初めて将軍として、その補佐役である執権の上に立ったような気がした。
和卿は平伏したままだが、床を見つめながらほくそ笑んでいるに違いない。
こんなことは、おそらく将軍となって初めてのことだろう。言い終えた今も心の臓がはちきれんばかりに高鳴っている。
――これですべてうまく事が運ぶわけではない。
これからも様々な抵抗があるだろう。
――だが……。
実朝の想いはいつになく強く固かった。
*
「宋へ行くために船を造るとか。まことにございますか」
御所の向かいに居を構える政子がやってきた。おそらく義時が姉に告げ口したに違いない。あなたの息子である若将軍をなんとかしてくれ、と。叔父の言うことは聞かなくとも母親ならばなんとか説得できるかもしれないと思ったかもしれない。ただの母親ではない。尼将軍と言われている北条政子なのだから。
「母上、いえ尼御台様ならばお解りくださいましょう。この鎌倉を導いていただく老師が必要なのです」
正論である。自信をもって言った。が、いたしかたないこと、という顔をしたときは少々心苦しい気持もあった。
「なにも宋ではなくとも京にも高名な僧があまたおられるでしょうに」
夫、頼朝を亡くして十七年。すっかり白の尼頭巾(アマズキン)が板につき、姿だけ見れば生来の尼僧と見まがうほどだ。だが、この鎌倉の政の実権はこの尼将軍が握っていると言っても過言ではない。
「母上、あ、いえ尼御台様……」
いつまで経っても親子の関わりが先にきてしまう。
しつけには厳しく、夫の女への嫉妬は燃え盛る炎のように激しい女ではあった。が同時に実朝には優しい母の一面を見せたこともあった。
そう、あんなこともあった……。
「このように美しく愛おしいものが他にありましょうか」
御所の南庭に咲いた梅の花を見上げて母がそう言ったのを思い出す。
「やはり梅は赤よりも白のほうが美しい。白は源氏の色ですからね」
そう言って幼い実朝を見下ろしながら微笑んだ。
「母上、なぜ源氏は白なのですか」
「はて……」
幼子の唐突な問いに不意打ち食らったような顔になる。
「そうですね……、白は神の宿る清廉な色。武士に相応しい色……、だから、ではないでしょうか」
あまり自信のなさそうな顔になる。
「平家も武士でございましょう。なぜ赤なのですか」
母を困らせようと思ったわけではない。ごく素直な疑問だった。
「千幡は難しいことを聞きますな」と困り顔に笑みを浮かべ「きっと平家は公家の性分が抜けなかったのでしょう。お公家衆のお好きな色は赤ですからね」と応えた。そしてまた梅の木を見上げる。
「でも道真公はお公家様ですけれど、あの歌はきっと白梅を詠んだものでしょうな」
愛おしいような、そしてどこか哀しむような目をした。
「道真公?」
それは初めて聞く人の名だった。
「京のお公家様ですけれど、政(マツリゴト)トの諍いに負けて大宰府へ行かされることになって、そのとき詠んだ歌が」
東風(コチ)吹かば匂ひをこせよ梅の花 主なしとて春な忘れそ
白梅を見つめながら、そう口遊(クチズサ)んだ。
「世の人はみな、京を離れて大宰府へ行かねばならないお心の傷みを詠ったものと言いますけれど、それだけではないと思いますよ」
言って遠い目をする。
「京を去ることにはなったけれど……、それは哀しみだけではなくて……」
そう言って遠くを見つめ、微かな笑みを浮かべていた母の顔が目に浮かぶ。まだ長い黒髪だったころの……。
まだ歌に目覚める前のことであったが、道真公の詠んだ歌が実朝の胸にしっかりと刻まれたのはあのときだった。
ふと、昔の想い出が浮かび、また今にもどる。
「いえ、尼御台様……」と言い直して見たのは尼頭巾をかぶって少し老いた母の顔だった。
「ご存知の通り、栄西禅師はもともと天台密教を修められたお方。ご自身ですら禅は未だ道半ばと仰せでした。その禅は仏法の中でも最も新しく、そして吾ら武士に最も相応しい法(オシエ)なのです。残念ながら今の京には禅に通じたお方はおりませぬ。ですのでなんとしても宋からお連れする必要があるのです」
今の京に真に禅に通じた僧がいないのは確かだ。
――そうだ、絶対に宋でなければならぬのだ。
「宋、宋と、まことはそなたが宋へ行きたいだけではないのですか」
扇子で膝をぴしゃりと叩いたような声が響いた。
――見破られていたか、やはり……。
母、政子は、実朝が栄西から宋の話を聞き、『大唐西域記』なる書物に興味を持っていたのをよく知っている。
「宋へ行ってみたいという気持はたしかにございます。しかし本意は鎌倉のために老師をお連れすることです。それが将軍としての役目と心得ております」
嘘と見破られても、それでも嘘をつきとおす強い想いが今の実朝にはあった。
「将軍が船で旅に出て、何かあったらどうされます。世継ぎもまだというのに……」
最後のほうは袖で口を押え、聞き取れない声になっていた。
「そのときは、そのとき、養子でも迎えて将軍に立てれば……」
実朝も語尾を濁した。が、とたんに政子の表情がこわばる。
「よいですか。大殿の血筋はもうそなたしかおらぬのですよ。将軍は誰にでもなれるものではありませぬ。清和天皇の血をひく清和源氏でなければならぬのです。もしそなたに何かあれば……」と、そこまで言って絶句する。あってはならぬことを口にするのを恐れたのだろうか。
「源氏の血筋は絶えるのですぞ」
声が震えている。
――源氏の血筋が絶えるだと?
いったい、どこの誰が絶やそうとしているのだ。
実朝も抑えていた感情がむらむらと沸きあがる。がそれを押し殺してつぶやく。
「まあ、中将殿がご健在ならば……」
兄、頼家が生きていれば、と当てつけた。
それは母、政子の前では禁句だった。が、あえて口にする。と、みるみる政子の顔色が変わった。
「あれは……、あの二代鎌倉殿は比企の家の者じゃ」
憎しみに燃えた目を宙に向ける。その視線の先にあるのは、おそらく頼家の乳父、比企能員(ヨシカズ)であり、その母、比企の尼だろう。政子にとっては夫が乳母である比企の尼に執心なのがずっと気に入らなかった。それが子までも比企家に盗られたという心持に違いない。
――だから比企を討ったというのか。
討ったのは政子の父、時政だが、じつは政子の怨念が父に伝わって爆発したのかもしれない。
――比企を滅ぼせ、と。
たとえ血のつながった我が子であっても他家へ婿に出てしまったかのようなありさま。であればその一族とともに消え去れ、と。
尼頭巾の中に射るような険しい目がある。まるで腹を痛めた我が子ではなく、頼朝が他の女に産ませた子を見るような目だ。そう思ったほうが気も休まるのかもしれない。あれは我が子ではなかった、と……。
――だから源氏の血筋は自分しかない、というのか? だが、まだおるではないか。兄、頼家の遺児、善哉が……。僧名を得て公暁となったが、頼朝の嫡男のその嫡男という、本来であれば善哉こそが嫡流ではないか。
「善哉、いえ公暁がおるではありませぬか」
ふて腐れた顔は隠し、懇願をこめてつぶやく。
――怒りを買うことになるやもしれぬ。
実朝は恐るおそる政子の顏をうかがう。
「あれは……、あれには可哀そうなことをした」
うつむいてため息をつく。とたんに背が丸まったかのように年老いた女の姿になった。
「せめて、心静かに生きて欲しいと思うておる」
伏せた目に涙が光ったかに見えた……。
だから僧にさせたというのか。我が子を我が子でないと言いながら、その子である孫は違うというのか。
実朝はふつふつと怒りが湧いてくる。もとより自分のほうが僧になりたかった。そして宋国へ行きたかった。本来であれば頼朝の嫡流であった子が僧になり、嫡流ではなかったはずの自分が将軍になっている。
――おかしいではないか。
そう口にしたいのをようやく堪える。口にしたところで北条政子という女の意を変えることはできない。ここは嘘でも取り繕うしかない。
「わかりました。私自身が行くかどうかは考えることと致します。ただ、唐船は造ります。鎌倉にとって宋と繋がることは必要なのです」
――嘘だ。吾はなんとしても宋へ行く。いや行ってやる。
禅の老師を請い、鎌倉へ送り出したあと、源実朝は死んだことにすればよい。そして今度は自身のための旅に出よう。
そうなれば、三代将軍は死んだ。では鎌倉はどうなる? みなそう言う。だが……何も案ずることはない。鎌倉を北条の手中に収めたい義時ならば、喜んであらゆる手段を講じるだろう。表向きは別にして、鎌倉をじきじきに治めるのは源氏でなくともよいのだ……。
尼頭巾の老女の顏を見る。実朝が自身の想いに耽っている間も、さきほどから口だけはずっと動き続けている。が、言葉は実朝の耳を素通りしてゆく。
「……船を造るにはあまたの富をつぎ込むことになりましょう。今の鎌倉にとってそれがよいことやら……」
あとからあとから諫めの言葉は続いたものの、減速し、しだいに収束してゆく。だが、それで納得したわけではないだろう。ただ、実朝自身が行くことを考え直すと言ったことで、今日のところは刃を鞘に納めようとしているようだ。おそらく渡宋の計画が消えるまで何度でもやってくるに違いない。北条政子とはそういう女だ。ときに母として優しさを見せることもあった。が、たとえ我が子であっても……。ひとつ間違えれば兄と同じように……。
無いとはいえない。それが北条政子。
――だが、吾は負けんぞ。
【ご参考】『吾妻鑑』に記された実朝の唐船建造計画