■前回までのあらすじ
大学で考古学を学んだ憲二は、恩師、吉田教授と小町裏通りのスナック[段葛]で歴史談義する中、[段葛]の女将(ママ)は鎌倉時代を、まるで見てきたかのように語りだす。
実朝は疱瘡を患い、熱にうなされて自らの首を切られる悪夢を見、自身も兄や父のように殺されるのではないかという疑念を抱く。やがて疱瘡が癒え、鏡に映った自身の顏を見て失望するが、宋への憧れは抱き続けた。和田義盛が乱を起こすが、幼なじみの和田朝盛からの手紙で、和田に謀反の心はなく、義時への抵抗だったことを知る。しかし和田は滅んだ。
陳和卿(チンナケイ)という宋国出身の僧が、実朝に面会を求めてやってくる。義時は、よく思わなかったが、実朝は喜んで和卿を受け入れる。唐船があれば宋に行けるという話になり、実朝は和卿に唐船の建造を命じ、周囲の反対を押し切って渡宋を決意する。唐船の建造は着々と進み、実朝は和卿から唐船の構造やさまざまな知識を教えられる。
* * *
闇の奥から大勢の影が歩いてくる。まるで石地蔵が化野に群れているのかと思いきや、それは鎧を纏った武者たちだった。袖に折れた矢が刺さったままの者もいる。顔に血のりのついた者。片目のつぶれた者。そして群れの中心にいるのは和田義盛だった。その横には嫡男の常盛、そして義氏、義直がいる。だが三男の義秀、孫の朝盛の姿はない。
――許せ……左衛門尉。
言ったつもりが声にならない。
義盛がゆっくりと近づいてくる。いつもの優しい老人の顔とは違う。青ざめ、どこか遠くをみるような目をしている。
――殿、お許しくだされ。吾らは決して謀反では……。
義盛が平伏すると背後の武者たちもみな地べたに手をついて土下座した。一斉に甲冑のこすれ合う音がする。
――わかっておる。
自身の祖父のような義盛が土下座している。今にも折れてしまいそうな枯れ枝のような体が不憫だった。
――あのとき、なぜ直( ジカ)に話しに来なかった。
顔を合わせて話せばわかりあえただろうに。だが、義盛は平伏したまま頭をあげない。
――左衛門尉、どうした、何か申せ。
義盛の体は動かない。
何か言ってくれ。実朝は頭を垂れる義盛を見つめた。
――そうだ、三郎はどうした。
返事がない。
――左衛門尉、三郎は……。
声が出ない。
やがて武者の群れが平伏したまま闇の中に溶けてゆく。
――待て。行くな、左衛門尉。
――三郎……。
闇に向かって何度も叫んだが声にならない。
「三郎……」
ようやく喉の奥から声が出、その自身の声で目が覚めた。
じっとりと油のような汗にまみれている。
「またあの夢か」
和田の乱以来、実朝は同じような夢を何度も見ていた。
*
「相州、親衡(チカヒラ)はまだ見つからぬのか?」
謀反の張本人と目される泉親衡は義時の遣わした捕縛の使者と合戦に及び、その混乱に乗じて逐電したと聞いてから、ずいぶんと時が経っている。
「いえ、いまだ」
目を伏せ、小さな声でつぶやくように応える。
「和田を罰しておきながら親衡を取り逃がしたのでは片手落ちであろう。そもそも安念坊の言うことは信じられるのか?」
ことの発端は、御家人の千葉成胤(ナリタネ)のもとへ泉親衡の郎党であった安念坊が訪ねてきて、頼家の妾子、千寿丸を将軍に祭り上げての挙兵に協力を求めてきたのだった。成胤はただちに安念坊を捕縛し、義時のもとへ連行したが、その安念坊が、和田義直、義重、そして義盛の甥、胤長も協力を約束したと証言したことから騒動が始まったのだ。
今となっては遅きに失したとはいえ、実朝は泉親衡を捕えて真相を白状させ、和田への疑いを晴らすことができれば、和田一族を手厚く弔うつもりでいる。そしてもし三郎朝盛が存命であれば和田家を再興させることも考えられる。
――そうなれば、あの乱はいったい何だったのだ……。
泉親衡を捕えても、そう簡単に白状することはないだろう。だが当人への処罰は許すわけにはいかぬものの、一族への処罰を赦免することと見返りに謀反を認めさせることはできるやもしれぬ。しかし、うしろで義時が糸を曳いていたとしたらそれも難しくなるかもしれない。
実朝は、目を合わそうとしない義時を、追い打ちをかけるようにじっと見つめた。
「いきさつはどうあれ、和田が御所に弓引いたのは紛れもない事実にござる」
言葉はへりくだりながら上目づかいで睨みつけてくる。その視線に実朝は威圧を覚えた。政は執権に任せるという暗黙の了解がありながら、思い切って言ってみたことではあった。
――弓引いた先は本当に御所か? 相州よ、まことはそちに向けられた矢だったのではないのか?
「では、火を放ったのも本当に和田か」
――和田の攻めを受けながら御所に火を放つこともできる。
気を奮い立たせて言葉をぶつけてみる。扇子を握る手がじっとり汗ばむ。
「殿は何を申されたいのでござるか」
静かなもの言いではあったが睨みつけるような目を向けてくる。恫喝の気が漂っていた。
――ここまでか。
実際に和田の軍勢と対峙したのは義時たちで、実朝は法華堂にこもっていた。和田を落とし入れるための義時の陰謀だという確たる証拠はない。口惜しさと恐ろしさが入り混じったまま、抜いた言葉の刀を鞘に納めるしかなかった。
義時が勝ち誇ったような目を向けてくる。
「それより、渡宋の船のことにござる」
和田の件を切り返した勢いで話を転じてきた。悔しいが、まだ義時には敵わない。
「殿御自ら宋へ向かわれることはない、ということで宜しいですな」
おそらく、政子から聞いたことの念押しだろう。
「まだ、決めたわけではない……がの」
扇子を広げてあおぐ。が、外は雪が降りそうなほど寒い。
「まだそのようなことを」
顔がこわばり眉がつり上がる。
実朝は義時の視線を避けるよう横を向いて扇子であおぐ。
――吾は絶対に宋へ行ってやる。
これだけは絶対に譲れない。だが、うまくやらねぼ元も子もなくなる。
「行くと決めたわけでもない」
のらりくらりと風に煽られる柳のごとく、相手をかわしながら……、
「どうすれば栄西禅師にかわる老師をお連れすることができるか、だ」
嘘、ではない。
「よろしいですか。将軍が鎌倉を離れるということがどういうことなのか」
将軍にもしものことがあれば鎌倉は、いや武家による政権は瓦解する、と母、政子と同じようなことをくどくどと言い続けた。
――相州よ、それは本心か? 本当は吾に何かあったほうが手間が省けるのではないか。兄、頼家のように消えたほうが……。
そう言いたくなるのを扇子を握って堪える。
「それに、宋という国との関わり、交渉となれば、それは院の司る政にござります。将軍とはいえ勝手なことはできませぬぞ」
――なんと、それも本心とは思えぬ。意の中は、武門の治める世にして、院は形だけに追いやろう。そう思っているのではないか? 都合のよいときだけ院を持ち出すではない。相州!
「あいわかった。よう考えることにする」
腹の中では義時に強く抗いながら、表では打ってくる太刀を受け流すのみ。
――今打って出るのは危うい。ここは折れぬよう耐えるのが得策。嵐の中の柳のごとく……。
実朝は義時の言葉攻めを受け流しながら胸の中で一首浮かぶかと思った。だが、やはり歌を詠む心情にはならない。そういえば和田の乱以来歌を詠んでいなかった。
*
寒さも緩み、梅の咲く季節に入った。唐船の建造も順調に進んで完成に近づいている。和卿を伴って浜を訪れれば子細にわたって状況はわかる。だが実朝は少し離れた場所で、ひとり唐船を眺めてみたいと思った。民の目にはあの唐船がどう映っているのかも気になったので、いつもの托鉢僧姿で寿福寺を出た。
――東大寺の大仏殿とはこれほどもあろうか。
前浜まで来たときだった。笠を押し上げると、民の家々の屋根上から、ぬっと大きな建造物が見えた。それは少々異様な眺めともいえる。寺院であれば大きさはともあれ見慣れた屋根の形にそう驚くこともない。だが、今、並ぶ屋根の向こうに突如現れたのは巨大な竜のようにも見える。じっと動かない。だが、ひとたび目覚めれば、それは大きな鳴き声をあげて立ち上がりそうだった。
――見よ、三郎。
そう言いかけて、今はひとりであったことを思い出し、胸をしめつけられるような寂寞を感じた。
――そちとともに宋へ行きたかったのう。
和田朝盛があの乱で死んだという証はない。だが、生きているという証もまた無かった。
「どでかいのう。あれが唐船というものか」
萎え烏帽子を被ったひょろりとのっぽの若い男が屋根の上を指さす。
「おう。鎌倉の将軍様がお造りになってるというあれだな」
ずんぐりした年嵩の男が応じる。
「ずいぶんと銭もかかろうに」
どうやら六浦から塩を運んできた行商の民らしい。
「だが、何のためにあのような船を造るのじゃろうな」
「なんでも遠い南方に金銀財宝のあまたある島があるそうじゃ」
「そのお宝を漁りにいくってか?」
――違う!
実朝は二人の中に入って釈明したかった。
「金銀財宝ではなく、不老不死の薬だ、という噂もあるぞ」
――それも違う!
「南の海には女人だけの島がある、という話を聞いたことがある。おおかた女子でも漁りに行くんでねえが?」とのっぽの若い男が言うなり二人して大笑いした。
――違う、違う、そのようなことではない。老師を迎えに行くのだ!
二人に割って入ってそう言ってやりたかった。だが、……。
――しかし。それだけではないこともたしかだ……。
少々後ろめたい気分に襲われる。老師を迎えに行くことに嘘はない。だが、自身の願望のために鎌倉の富を注ぎ込んでいるのではないか? そう言われたら反論できぬやもしれぬ。はたして、これでよいのだろうか。もし栄西禅師がご存命であられたら、なんと仰るか……。お叱りを受けるやもしれぬ……。
「それにしても、あんな船に乗って遠い旅をしてみたいのう」
のっぽの若者が遠い唐船を見ながら大きなため息をつく。
「そうか? わしはごめんだな。海の沖には何があるかわからん。大だこの化け物に出くわすかもしれん。嵐もまっぴらだ」
ずんぐりした年嵩は首を横にふったが、のっぽの若者は唐船を見やったまま遠い目をしてつぶやいた。
「何にでくわすかわからんだと? 面白いではないか」
――そうか、おまえもそう思うか。
実朝は同志を得たような気持で胸がときめいた。
「金銀財宝などなくっとも、まだ見たことのねえ遠い異国を旅してみたいもんだのう」
――そうだ。そうなのだ!

実朝の胸に熱いものがこみあげてくる。見たことのない遠い異国。そこを旅したいという、どうしようもなく抑えがたい気持。
この若者の夢を自分がかわりに叶えてやるのだ、と……。

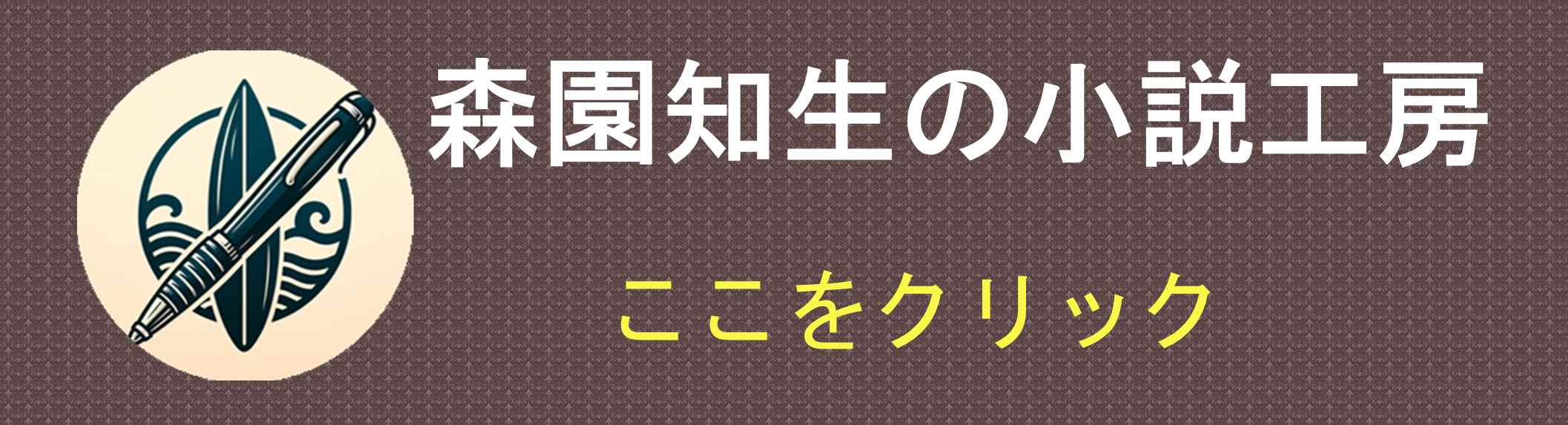




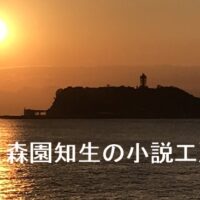
-200x200.jpg)





