■前回までのあらすじ
大学で考古学を学んだ憲二は、恩師、吉田教授と小町裏通りのスナック[段葛]で歴史談義する中、[段葛]の女将(ママ)は鎌倉時代を、まるで見てきたかのように語りだす。
実朝は疱瘡を患い、熱にうなされて自らの首を切られる悪夢を見、自身も兄や父のように殺されるのではないかという疑念を抱く。やがて疱瘡が癒え、鏡に映った自身の顏を見て失望するが、人前では公家のように化粧をし、宋への憧れを抱き続けた。和田義盛が乱を起こすが、幼なじみの和田朝盛からの手紙で、和田に謀反の心はなく、義時への抵抗だったことを知るも和田は滅んだ。
陳和卿(チンナケイ)という宋国出身の僧が、実朝に面会を求めてやってくる。実朝は喜んで和卿を受け入れる。唐船があれば宋に行けるという話になり、周囲の反対を押し切って渡宋を決意。和卿に唐船の建造を命じる。唐船建造は着々と進み、実朝は和卿から唐船の構造やさまざまな知識を教えられる。和田の乱の悪夢に苛まれることはあったが、渡宋への想いはますます強くなるばかりだった。
* * *
建保五年の四月十七日。天は晴れ渡り、由比の海は眩しいほど煌めいている。唐船が完成し、今日はそれを海に浮かべる船降ろしの日だった。主だった御家人も勢ぞろいし、前浜の民たちも浜を埋め尽くすほど見物に来ている。唐船建造の是非は別として、浜辺で成長するように巨大化した物体が、いよいよ動き出すという大催事に浜の空気は熱気を帯びていた。
実朝は立烏帽子に狩衣姿で牛車に乗っている。車から降りることはなくとも久しぶりに大勢の人目につくこともあるやもしれず丁寧に白粉の化粧していた。
「いよいよてござりますなり」
陳和卿が車の外から声をかけてきたので実朝は前簾を上げた。
「そうだな。この日を待ちわびていたぞ」
和卿に微笑みかける。
「いつでも始めるがよい」
そう言ってうなずくと、和卿も実朝の目を見返して大きくうなずき、踵を返した。
執権や母、政子の反対を押し切ってようやく今日という日が来た。あの巨大な船が海に浮かび、その勇姿を目にすれば渡宋がいかに偉大な事業かを悟り、見方も変わるやもしれない。実朝の胸の内は高揚し、希望と期待が膨らんでいった。
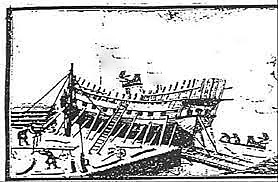
外では和卿が百人はいるであろう曳き夫たちに訓示を垂れる声がしている。曳き夫は水軍を擁する三浦義村の手配した者たちだ。これほど大きな船を扱ったことはないにしても船降ろしには慣れているはずである。
「曳けーい!」
曳き夫の長(オサ)らしい声が浜に響く。と同時に民の見物人からもどよめくような歓声が上がった。
その声を聞いて実朝は前簾を上げた。日が浜に照り返して眩しい。その光の向こうに巨大な唐船の艫(トモ)が見えた。
――行け! 行くのだ!
実朝は声に出さずに胸の中で叫んだ。
曳き夫の長の声が同じ間をおいて響く。百人が息を合わせて力をこめ、次に力を抜く。それを繰り返しながら少しずつ巨大な船が動いていくのだろう。
曳けーい! の声が延々と繰り返される。見物人の歓声もそれに呼応する。曳き夫と巨大な船の双方に声援を送っているかのようだ。
だが、船のほうはなかなか動きださない。実朝は和卿を牛車に呼び寄せた。
「和卿、いかにした」
「はあ、どうもおかしいなり」
顔を曇らせる。
「曳き夫の数が足りぬのか?」
「いえ、私の見立てては充分のはずなり。たた……」
眉を寄せる。
「ただ? ただ、何だ」
口ごもる和卿のようすがじれったかった。
「曳き夫たちの力の入れ方が甘い、というなりや、汗のかきかたが足らぬいうや」
首を傾げる。何か言いたげな顔だが、口をへの字に曲げたまま口ごもる。
「なるほど」
――そういうことか。
実朝は胸の中がむらむらと熱くなり、扇子を握りしめた。
「曳き夫の長はどこの者か」
おそらくそうとわかっていながら敢えて聞いた。
「右兵衛尉(ウヒョウエノジョウ)殿の手の者にござるなり」
――やはり
「犬か」
三浦義村は和田の乱で親族の和田を裏切って北条義時に与した男だ。義時との繋がりは深く、何でも従うだろう。
――相州の奴め。
扇子を牛車の床に押し付ける。腕がわなわなと震え、ぼきりと親骨の折れる音がした。
和卿が一瞬驚いたような顔をしたが、すぐに実朝の意を察したようだ。
「いかがいたしましょうや。そこの牛飼童の鞭で曳き夫たちの尻を叩きましょうや」
和卿も憤慨している。
「いや、待て。気を静めよ」
実朝は努めて冷めた顔をして言ったが、胸の内は熱湯のごとく煮えたぎっている。それは自身に向けた言葉だった。
――堪えるのだ。今は……。
ここで騒ぎ立てるのは得策ではない。事を荒立てれば孤立するのは実朝と和卿の二人だ。それに、唐船はすでに出来上がっている。慌てることはない。こうなれば、じっくり機を見計ることにしよう。
「殿」
見ると牛車の前に義時が立っている。折烏帽子に直垂(ヒタタレ)といういつもの武者姿ながら袴の裾をたくし上げている。おそらく自分も船降ろしの陣頭指揮に精を出している、とでも言いたげだ。
「どうもうまく運びませぬ」
困ったような顔をしているものの、腹の底で笑っているのが見え透いている。
――しらじらしい。
大声で怒鳴りたいところをぐっと抑える。
「今日の曳き夫たちはどうも力が出ぬようだな。しかと飯を食わせてあるのか?」
皮肉を言いながら扇子を広げようとした。が、親骨が折れてしまっていることに気づいてそっと後ろ手に隠す。
「右兵衛尉は強力の者を用意したはずです。ただ……」
言ったところで薄くかすかに笑ったのを実朝は見逃さなかった。
「ただ、和卿殿は、ずいぶんと立派な船を造られましたが、船降ろしのことまで考えておられなんだようですな」
しらっとした顔で和卿を見やる。と、和卿のほうは歯ぎしりせんばかりの顔をしている。
――義時よ、そなたはこの大地と海が丸い玉であることを知っているか?
――風をはす向かいから受けながら前に進む道理がわかるか?
――そんなもの事の道理を誰よりもわきまえている和卿が、船降ろしに抜かりあるはずなかろう!
怒鳴りつけたかった。が、
「まあ、しかたなかろう」
さらりと言ってみせ、波立つ胸中をなんとか抑える。
「では、今日のところはこれまでということに」
上目遣いの目がぎらりと光ったように思えた。表には出さないものの、してやったり、という顔に見えた。
「あいわかった」
とうてい承服しがたいところではあったが、その思いが顔に出ぬよう努めて冷静に応じる。
いっこうに動かない巨大な船。曳き夫もみな浜に上がって帰り支度を始めた。見物人たちの中に静かなざわめきが伝わってゆく。ひとり、ふたりと浜を去ってゆく。希望と期待に膨らんだ浜の空気が萎んでゆく。やがて、ぞろぞろと街中へ帰ってゆく群衆の行列ができた。集まってくるときと相反して興ざめし、心萎えた気に包まれている。
あの行商の若者は来ていたのだろうか。実朝は前浜の町屋で見かけた若者を想った。
あんな船に乗って遠い旅をしてみたい……。そう言った若者の顏が浮かぶ。
――すまぬ。つまらぬものを見せてしまった……。
あまたの富を注ぎ込んだ事業。せめて民たちには希望という糧を与えてやりたかった。なのに、それを抱くことでしか癒されぬ若者たちの心を折ってしまったような気がした。
実朝は、墨絵のような伊豆の山に沈んでいく日を見ながら、その遥か彼方にあるはずの宋に想いを馳せる。寧波(ニンポウ)の港が目に浮かぶ。そして大陸の遥か西にある玉門関。その先に広がる西域……。

――見ておれ。このままでは終わらぬぞ。
胸の奥でつぶやき、折れた扇子を握りしめた。
第四章
「そうか、あのころは八幡宮の石段脇から由比ヶ浜まで見通せたんだね」
女将(ママ)の長い話が一段落したところで、吉田は感慨深げに言った。
「そうね、今より建屋がずっと低かったから、和田様の変事も、御所様の唐船も全部見えていたわ」
まるで見てきたかのような女将(ママ)の話に吉田は調子を合わせてはいるが、『吾妻鏡』を読み解き、そこに豊かな想像力と感性を織り込んだ物語と思っているはずだ。それでも憲二のほうは、語り部のような女将の物語に引き込まれてしまった。女将が銀杏の木の精霊だというのもまんざら冗談ではないような気さえしてくる。

「あの唐船の話はたしかに『吾妻鏡』に書かれてはいるが、じつにあっさりとしたものだよね」
「ええ、建保五年四月十七日の条に、宋人和卿が造った唐船は数百人で曳いたけれど結局由比浦に浮かばなかった、とだけ。その後のことも何もふれてないわ。まるで御所様は周囲の反対を押し切って散財したものの、結局は信用のおけない宋人にいいようにもてあそばれた、みたいな書き方よね」
「まあ、そのあたりが北条視点の文献ということだろうね」
「船を海に出せなかったのは間違いなく相州様の仕業よ」
「でも義時は、なぜそんなに実朝の渡宋に反対したのでしょうね。源氏を追い落としてその後の北条氏支配を確立した彼だったら、実朝が渡宋の途中で難破でもして死んでくれれば手間が省けると思うのですが」
憲二はそこが解せなかった。
「あのときはまだ、相州様としては形だけでも源家の将軍が必要だったの。どんなに執権職に政治的実権があっても清和源氏という天皇家との血のつながりがなければ将軍にはなれない。将軍でなければ天皇に対抗できる幕府の長にはなれない。北条という家柄では限界があったのよ。だから御所様が宋に行ってしまうのは何としても止めなければならなかった。あのときは、ね」
「あのときは?」
吉田と憲二が同時に聞き返す。と、
「ええ」
小さくうなずきながら微笑む。
「ほう、それは物語の続きが楽しみだね。それにしても陳和卿という男はたいしたものだね」
当時の和船は平底だったので、ただ風下へしか行けなかった。しかし唐船の場合、横風を受けた帆が揚力で斜め前に引かれるのと、船底の骨材が横流れを止める力とが合わさって前に進む。
「そんな物理のベクトルの法則を実朝に理解させるのは難しかっただろう」
「当時の日本人にとって大型の唐船は、今でいえば宇宙船みたいな最新鋭の乗り物だったのでしょうね」
憲二は、由比ヶ浜に巨大な宇宙船のような唐船がしだいに形をなしてゆく景色を想像してみた。実朝は、その唐船で未知の大陸へ向かう夢を見たのだろう。
当時の町並みは平屋建てだったので、まるで浜に城郭が建ってゆくかのように巨大な物体が八幡宮からも見えた、と女将も言う。
「しかし船は完成したが出航できなかったわけだ」
おそらく武士から民まで鎌倉中のほとんどの人間がその一大イベントを見物に行ったことだろう。実朝にしてみれば見事に仕上がった唐船が相模湾に浮かぶ勇姿を今か今かと見守ったに違いない。そして自ら船に乗り、大海原を駆けめぐり、やがてまだ見たことのない西の大陸が水平線に浮かんでくるのを想ったことだろう。
だが、その巨大な船体が海に浮かぶことはなかった。人夫たちが汗だくでへとへとになってゆくのを見て、作業を止めさせるしかなかった。
「いったいどんな気持だったかね、実朝は……」
吉田が深いため息とともにつぶやく。若者の夢が破れたその時を想ったのだろう。
ふと、憲二の胸をよぎるものがあった。
――自分もそうだった。
考古学の道をあきらめ、旅館を継ぐ決心をしたときのことだ……。

研究室で鎌倉の発掘現場を見学したあと現地解散となり、新田杏子と二人で和賀江島を見に行こう、ということになった。
『吾妻鏡』の貞永元年(一二三二年)七月十二日の条に、
『今日、勧進聖人往阿弥陀仏の申請に就いて、舟船着岸の煩い無からんが為、和賀江嶋を築くべきの由と。武州殊に御歓喜、合力せしめ給う。諸人また助成すと』とある。
武州、北条義時の長男泰時が勧進僧侶の勧めに応じて港湾施設を造ると決めたときの記述で、実朝の唐船騒動から十六年後のことだ。
唐船が船降ろしに難儀したとおり、鎌倉の沿岸は砂浜のため大型船が着岸できなかった。宋との交流も始まったが、唐船は現在の東京湾側に位置する六浦に入港していた。鎌倉からは三浦半島を横切る朝比奈の切り通しを抜けて行かねばならない。そんな状況から、鎌倉の浜に大型船が着岸できる港湾を建設する必要があったのだろう。
鎌倉の逗子に近い海岸沿いにそれはあった。かつては玉石が整然と積まれ桟橋の体をなしていたのだろうが、長年潮と波に洗われ、今は積み石も崩れて文字どおり小島のようになっている。満潮になれば水没してしまうような浅瀬ともいえ、そのときはちょうど潮が引いて小島が海面に姿を現していた。
沖に大島が霞んで見え、それに覆いかぶさるように入道雲が立ち上がっている。
「なんだか白熊みたい」
新田杏子がぽつりと言った。目は遠く水平線の空を見つめている。
「え? 何が」
憲二は不意をつかれて聞き返した。
「あの雲よ。そんなふうに見えない?」
「ああ、そう言われてみれば……」
白熊にも見えるし、
「縫いぐるみのパンダにも見える……」
ほかのことを考えていたので口から出まかせだった。
「パンダ? そういえば、そんなふうにも……。昔の人も雲を見ていろいろ想像したのかしら」
「うん、でも昔の日本人はパンダなんて知らなかったろうな」
見たことのないものを懸命に想像しようとした人間がいたのを、あのときは知らなかった。
「ここにいて目を閉じると、唐船が桟橋に泊っているのが見えるようだわ」
二人で浜に立ち、玉石の小島を見ていた。その先には現代のヨットハーバー、逗子マリーナがあってマストが林立していた。
「あんな時代に大陸から船が来ていたんだな」
船べりを朱に塗った唐船が憲二の目にも浮かんでくる。
「このあたり、つい最近まで青磁の欠片が拾えたらしいわよ」
酒や茶を青磁の壺に入れて運んだようだ。桟橋で積み下ろししている最中に落として割れたのだろうか。鎌倉は浜からも街中の遺跡からも大量の青磁が出土している。だが当時の日本に青磁を作る技術はなかった。それらはすべて大陸から運び込まれたものだったはずだ。
「私、先生について中世考古学をやるわ。そう決めたの」
四年卒業を前に新田杏子は修士課程に進むことを決めた。
「宮下君は?」
言って遠い沖を見つめた。どこか思いつめた声に思えた。私は決めた。あなたはどうするの? と……。
「俺は……」
あのときすでに兄の四十九日が過ぎ、父と叔父から引導を渡されていた。自分は実家の家業を継がなければならない。だから考古学を続けることはできない。
――彼女は俺を、ともに考古学の道を歩む同志と思ってくれていたのだろうか。それとも、同志というだけではない……。
「おい、宮下君、だいじょうぶかね」
吉田の声で、現実に引きもどされる。が、あのころのほろ苦い余韻はまだぬぐえなかった。
「はい、お水、飲んだら?」
女将がカウンターにグラスを置いた。
「そういえば昔から飲むわりに強くはなかったね」
「いえ、だいじょうぶです。ただ、ちょっと女将の話があんまりリアルなんで……」と笑ってごまかす。
「ああそうか。女将はね、『吾妻鏡』の話になると完璧に入り込んでしまうからね、初めてこの店に来た客はみんな戸惑うよ」
「あら、入り込む、だなんて。あたしはただ昔を思い出してお話ししているだけよ」
どこまでも銀杏の木の精霊を演じきるつもりらしい。おそらく女将はこのキャラクターに徹してこの店をやっているのだろう。
「しかしあの赤気の話、そんな話が『吾妻鏡』にあったかな」
吉田は遠い目で少し考え込むような顔をした。
「『吾妻鏡』には出てないんじゃないかしら」
「たしか『明月記』にはそんな記述があったな」
藤原定家の日記『明月記』の建仁四年正月十九日の条と同月廿一日の条に、京都で定家が「赤気」を見て恐れを抱いたことが記されているという。

「ちょうど女将の話で実朝が見た天空の大河、いや桃色の羽衣だったかな、その時期と一致するね」
「あれは私も見たわ。八幡様の北の空が赤くなって、そう、御所様の言われたとおり濃い桃色の羽衣のような……、とっても神秘的だったわ」
女将はそのときを思い浮かべるようにうっとりしたような目で宙を見る。
「やっぱり、それはオーロラだったのかな?」
「そうだと思うわ。あのときはオーロラなんて知らなかったけど」
「つい最近、新聞で見たよ。国立極地研究所が、中国の歴史書『宋史』に、定家が赤気のことを『明月記』に書いたのと同じ日、太陽に大きな黒点が現れたという記述を見つけたらしい」
「その黒点のことですね。陳和卿が日輪の黒蟻と言ってたのは」
「おそらく、そうだろう」
樹木の年輪の炭素同位体比の測定データからも当時は太陽活動が活発な時期で、大きな磁気嵐が発生する条件がそろっていたことが判って、日本のような低緯度でもオーロラが見られた可能性が高いという。
「オーロラというのはシベリアやアラスカなどの高緯度では緑色で、日本のような低緯度では赤くなるものらしいね」
「『宋史』が編集されたのは元代になってからだから、陳和卿が見た書物というのはその基になった資料かもしれないね」
女将は本当にただのアマチュア郷土史家で『吾妻鏡』に詳しいだけなのだろうか。そんな疑問が憲二の胸の中でいよいよ膨らんでくる。
「じゃあ女将の物語の続きを聞かせてもらおうか」
吉田がカウンター越しの女将を見上げる。
「唐船の騒動があってから二月ほどたったころだったわ。公暁様が京からお帰りになられたのは……」
*
そろそろ梅雨の季節に入るころだったが、外はまだ晴れていた。
僧形の若者がひとり寝殿に正座している。端正な顔つきながら目が大きく、射抜くように力強い目線で前を見据えている。
その横顔を見つめるように尼僧姿の政子と義時が脇にいた。
上座で対峙する実朝はいつものように白粉の化粧をしていた。顔の痘痕(アバタ)を気にしてのことではあったが、素の自分を見せぬよう面をつけるような心持もあった。
「歳はいくつになった」
「はっ、十八になりましてございます」
凛とした声が響く。まるで若侍のような張りのあるそれは宗教者を感じさせない。実朝より八つ下になるが、その堂々とした居住まいは同輩かと思えるほどだ。
「そうか、では今日より八幡宮別当を申しつける」
僧形の若者に向かって言った。
兄、頼家の遺児、公暁を八幡宮の最高位につけると最初に言い出したのは政子である。それは十一年前、公暁がまだ善哉という幼名だったころ、着袴(チャッコ)の儀でのことだった。
――強い武士になりとうございます。
実朝が何になりたいか尋ねると、幼い顔できっぱりとそう言ったのを今でも憶えている。だが、その想いが許されないことは宿命ともいえた。
「ご立派になられて」
政子は公暁を感慨深げに見つめる。曲がりなりにも血のつながった孫との久方ぶりの対面であった。
「尼御台様におかれましては ご健勝のごようす、何よりでございます」
剃髪し僧衣を纏ってはいるが、相手を見据える目線は揺らぐことなく、武将のそれのようである。八幡宮別当を申しつけたものの、実朝は公暁の醸す宗教者に似合わない力強さのようなものが気にかかった。
「そなたを公胤(コウイン)殿にお預けして本当によかった」
政子が微笑む。
その園城寺の阿闍梨、公胤は歌人でもある。
「公胤阿闍梨は新古今集にも選ばれておりましたな」
実朝は、ただ一首選ばれていたその歌を諳んずるほど憶えてはいなかったが、たしか秋の夜の在曙(アリアケ)の月を詠ったものだったな、と思った。
「はて、それは存じあげませんでした。阿闍梨は私にとっては雲上のお方。とはいえお名前を一字いただいているのですが」
屈託なく笑みすら浮かべ、あっけらかんとした物言いに実朝ははっとした。豪放だった兄、頼家の面影がやはりある。
――こやつは本当に僧侶なのだろうか。
「直に仏(ホトケ)の法(オシエ)をいただいたのは貞暁(ジョウギョウ)様にございます」
――ああ、その名を今ここで出すか!
実朝は政子を盗み見るように目をやった、と、やはり一瞬表情が曇ったかに見えた。
貞暁という僧の母親は、かつてこの御所に出仕する侍女であったが頼朝の寵愛を受けて懐妊した。実朝が生まれる六年前のことである。それを知ったときの政子は大変なご立腹だったということを、実朝は伝え聞いていた。政子の怒りを恐れた頼朝は、子を家臣に預けて密かに育てた。実朝が生まれる三月ほど前になったころ、京で出家させることにしたが、その上洛出立の夜、密かに息子の元を訪れ、太刀を与えたという。それが後の貞暁……。
そんな異母兄がいるという話を実朝は人伝に聞いていた。政子にとってはじつに腹立たしく目障りな存在のはずなのに、そのような出自の僧のもとで、あの嫉妬深いはずの政子が自身の孫を修業させ、八幡宮の別当にまでさせようとすることが実朝には不可解だった。
ただ、貞暁という僧は高野山に登って俗界から遠ざかり、それ以後世間と隔絶した中でひとり修行に励み、人々の尊崇を集めたという。頼朝の遺児ということで将軍にかつぎ出して謀反を企てるような者がいてもおかしくなさそうだが、この貞暁に限ってはいっさいそのようなことが無かった、という辺りが政子にしてそうさせたのかもしれない。
「貞暁殿はご健在ですか」
政子がかたまった微笑みを崩さずに公暁を見やる。
「はい。いまだ修行の道は半ばとますます励んでおられます。それとともに源氏一族の菩提を弔い続ける、とも申しておられました」
太い声で言い放つ。と政子は笑みを崩さずに小さくうなずいた。
「それは良いことを聞いた。何よりじゃ」
義時もなんどもうなずく。
――何が、何よりじゃ、だ。大殿の隠れた遺児が謀反の心を持たず、ただ仏道に励んでいることか?
たしかに武士の遺児を出家させる目的はそれしかない。目論見どおりにいって安泰ということなのだろう。その一方で謀反の動きがあれば、それを大義にその勢力を一掃する口実にもなる。執権、というより北条家の当主としてはそのようなことばかり考えているに違いない。
――この公暁とて野心がないとはいえまい。二代将軍の遺児なのだから……。
公暁の養父は三浦義村。その義村を後ろ盾に謀反を起こすこともあり得る。いや待て、義村は義時の犬だ。同族の和田を裏切ってまで義時に与した男。そんな男が義時に反旗を翻すことはあるまい。
実朝は白粉の面の裏で周りにいる人間の裏の顔を探っていた。
「ところで、鎌倉殿におかれましては、先ごろ唐船を造られたとか。宋へ渡るためと聞き及びましたが」
公暁が大きな声であっけらかんと言う。
――今その話をするか、こ奴め。少しは気を遣うことをせぬか……。
船降ろしに失敗したあの日から二月になる。
「そ、それは、宋の国へ禅の老師を招きに参るためだ」
幾たびこの言い訳話をしたことか。
「ほう、それは殊勝なことにございます」
太い声、あっけらかんとした物言い。たしかに宗教者に対しては将軍といえども、いち目置かねばならない存在ではある。だが一歩誤れば将軍に対する態度ではないと叱責を受けかねない。
――なにを偉そうに。そのほうごときに言われてたまるか。
顔には出さず、胸のうちでつぶやいた。
義時は腕を組んでしかめ面をし、政子は手を口にあてて笑いを堪えている。
「だが、風向きが悪うてな。今、ようすを見ておる」
つい口ごもる。扇子を開いてあおぐも半分しか開かず風がこない。
「ほう、唐船でも風向きが差し障るのですな」
また腹から出すような大声だ。
――こやつ、唐船のことをわかって言ってるのか? それとも、ただ思ったことを障りなく口に出す性分なのだろうか。わからん男だ。
「唐船とはいえ、真向かいには進めぬのだ」
――はす向かいに進んで反転しながらなら行けるのだが……。
「ほう、そういうものにございますか。いちど見せて、いやできれば乗せていただきたいものですな」
そう言って高らかに笑った。
ふつうであれば将軍の前で許される言動ではない。だが、この若者には、そういった世の習いなど吹き飛ばしてしまうような豪放さがあった。
――血は争えぬ。やはり兄の子だ。
義時も政子も少々困ったような顔をしながらも笑いを誘われている。人の心を鷲づかみにして、少々の無礼も許させてしまうような不思議な魅力も併せ持っているようだ。
――朗らかなのはよい。だが、腹の中には何か隠し持っているのではないだろうか。
実朝は、もう少しこの若者のようすを見ておかねばならないと思った。
「船もよいが、八幡宮別当としての営みは大仕事ぞ」
ここはきつく釘を刺しておかねばならない。
「はい、諸々の事を整えたのち、千日の参篭に入ろうと思うております」
笑顔が消え、大きく力強い目で実朝を見据える。それまでとは別人の顔のようだった。
「それは良きこと。そうせい」
実朝も公暁を見返すように見つめて言った。













