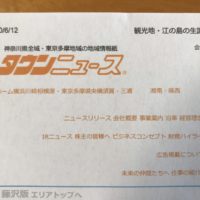海底に蠢くものが見えた。
いや、見えたような気がしただけかもしれない。
智志(サトシ)はサーフボードに跨ったまま陽の照り返す海面の下を覗き込むように見つめた。

この稲村ヶ崎のアウトサイドは日本でも屈指のサーフポイントで稲村クラシックの開催されるところだ。INAMURAはただのサーフィン大会ではない。波のコンディションに関わらず決められた開催日にやってしまう一般の大会と違ってオーバーヘッドの大波の時にだけ開かれる。そのため秋に三ヶ月間のウェイティング期間を設け、台風が接近して良質の大波が立ったときを狙って開催される。出場できるのは名実ともに優れたプロサーファーだけで、この大会に招待されるのはサーファーにとって最高の栄誉だ。
「よお、見かけない顔だな」
パドリングで寄ってきて、すっとボードに跨るなり茶髪の若者が言った。日焼けがしみ込んでコーヒー豆のような肌をしている。
智志は、さっそく来たな、と思った。大自然の中でする波乗りも、現実には人間社会の縮図のような縄張り争いがある。サーフィンに適した波の立つ場所は限られていて、波の数もそう多くはない。その中でサーファーどうしは波を奪い合っている。おのずとローカルと称する地元サーファーが幅を利かせることになる。この稲村ヶ崎ではとりわけそういった雰囲気が色濃いと聞いていた。
「稲村は初めてなんだ」
智志は、つとめて口角を上げ、笑顔を作った。
「へえ、でもさっきからいい乗りしてるじゃん」
おそらく今日の波は稲村としては小さなほうだろう。それでも陸風(オフショア)に撫でられた腰高サイズの滑らかな波がときどき来ていて、智志にとっては散歩でもするような軽い感覚で遊べた。陽射しも温かくウェットスーツを着ていると暑いくらいだ。もっこりとした亀の甲のような江ノ島の背後には富士山も見える。サーフィン雑誌で見た風景がそのまま目の前に広がっていた。
「俺、宮崎から来たんだ」
標準語で言ったつもりだが、自分でも不自然な違和感があった。
「宮崎? て、九州の? そりゃまた遠方からわざわざ。でも宮崎もけっこういいとこらしいじゃん」
茶髪は初めて笑顔を見せた。どうやら、ローカルとのやっかいな諍いは避けられそうだ。ほっと緊張がほぐれる。
宮崎は、四国の高知と並んで太平洋のうねりが直接やって来る。波のサイズならば湘南には負けない。ただ、この稲村だけは特別だ。
「憧れの稲村でやってみたくてね」
偽りのない本心だが、ローカルの心をくすぐる狙いもある。
「まあ、今日はぜんぜんだけどな」
茶髪は、自分はローカルだと言わんばかりに上から目線の言いようだ。本当の稲村はこんなものではない、という意地のようなプライドが透けて見える。
「今年はどうだろうね、クラシック」
「さあ、どうだろうな。台風しだいだからな。去年も中止だったし」
稲村クラシックは大会運営側の目にかなったビッグウェイブという条件が揃わない限り絶対に開催しない。そのままウェイティング期間が過ぎればその年の大会はあっさりと中止にする。それだけINAMURAブランドのプライドは高い。
「いつか出てみたいね」
ため息をつくように、智志はつい本音を漏らした。
「何言ってんの。まずプロになって実績積まないと」
馬鹿にしたような顔で、「ったく十年早えよ」とつぶやくように詰るのが聞こえた。
「プロテストにはこのまえ受かったんだ」
アマチュアの大会では何度も優勝し、半年ほどまえようやくプロテストに合格した。雑誌にも、九州にイケメンプロ誕生と小さな記事で紹介されたが、写真が小さくて濃い眉毛と切れ長なのに瞳が大きいとよく人に言われるまなざしはほとんどわからなかった。それでも九州のサーファー達には、顏と名前はそこそこ知られている。
「ええ! おまえプロだったの? すっげえ」
目を真ん丸に見開いて、ボードからずり落ちそうになる。
「俺、長友智志。よろしく」
少しだけ上から目線に転じて挨拶すると、茶髪は、
「どうりでいい乗りしてると思ったよ。俺、裕二。いつもここでやってるし、まあ何でも聞いてよ」と目線は少し下がったもののローカルのプライドだけは譲らないかのように笑った。
憧れのプロサーファーにはなったが、正直のところ悩んではいた。宮崎のサーフショップでボード修理(リペア)をしながら波乗りに打ち込んでいるが、親はよい顔をしていない。
「プロサーファー? そら職業と言えるのか」
地元の信用金庫に勤める父は、智志の進路の話になったとき、そう言って苦い顔をした。
父が言うのももっともだった。プロとは言っても野球選手やプロゴルファーとは違う。大会の賞金だけではとても生活してゆけない。ほとんどのプロサーファーはサーフショップで働くか他の職業に就くことで生計を立てている。そんな不安定な人生を堅い職業の父は許せないのだろう。
「職業ではないかもしれん。ただ、波乗りと離れては生きていけんだ」
中学のころから波乗りに夢中だった。大学もサーフポイントに近いところにキャンパスがあるのを狙って入った。ボードを海辺のサーフショップに預け、キャンパスから自転車で通い、大学より海にいる時間の方が長かった。やがて大学にいる意味も見いだせなくなり、中退してサーフショップで働きながらプロを目指すようになった。父親からも精神的には勘当されているようなもので、ほとんど口をきくことはなくなった。
ただ、これでよいのだろうか、という思いがプロテストに合格したあとになって、じわりと湧いてきた。波乗りは素晴らしい。初めてチューブライドを決めた時の感動は今でも忘れられない。巻き波が頭上を覆い、水の壁、天井を透かして緑色の陽がゆらゆらと見えた。大自然の海、そして波に抱かれていると宇宙とか神の領域に入ったかのような神秘的な心境になる。だが、それは自分ひとり、きわめて個人的なことであって、他者、社会とは無関係だ。自然に身をゆだねて生きるといっても、ひとりでは生きてゆけない。結局は人間社会で生きていながら、自分はそれに何も報いていない。それでよいのだろうか、とそんな迷いが出たころだった。
「すっげえ。こりゃたまらんちゃが」
店長がテレビの画面を見ながらつぶやいた。いつもならサーフィンビデオを流して店の雰囲気を盛り上げている40インチの画面には一昨日に起きた大雨洪水災害の惨状を伝えるニュースが映しだされていた。
「どんげしました?」
智志はサーフボードリペアの作業をひと休みして店内にもどってきたところだった。顔はボードのウレタン屑で白塗りの舞踏家のようになっていて、防塵マスクを外した口の周りだけ日焼けで黒くなっている。まるでパンダだ。だが、テレビ画面を見て言葉を失った。山肌が大きく削られ、山から溢れた土砂が家屋を圧し潰し、泥の山になっている。瓦礫の山の上では迷彩服を纏った男たちがスコップを手にして蠢いている。

――あの下に人間が埋まっているのだろうか。
男たちの緊迫した動きから、ただ瓦礫を片づけているだけには見えない。
〈災害発生から72時間が迫っています〉
人間が飲まず食わずで生き延びられる限界が七二時間。救助活動成否の分岐点が近づいている。ヘルメットを被ってマイクを握った女性が、かたい表情で語りかけてくる。陸上自衛隊の指揮官という男がインタビューに応える。
全力で救助活動……最後の一人まで……。
画面の中の緊迫感と潮騒の聞こえてくる店内に並ぶカラフルで艶やかなサーフボード。その二つの世界のギャップに智志は眩暈に似た揺らぎを覚えた。
画面は切り替わり、水没したかつての道路上にゴムボートが浮かぶ。腰まで水に浸かった迷彩服の若者が幼い少女を抱きかかえてゴムボートに向かうようすが映し出される。
「ここいら辺は海辺だから、あんげなこつにはならんな」
店長は、どこか異国のことのように遠い画面の奥を見つめたままつぶやいた。
「俺たち、ここでこんげなこつしてていいんですかね」
ボランティアに行こう、といった明確な意図があって言ったのではない。潮騒が聞こえ、温かい陽の光の入る店内とのギャップに罪悪感に似たものを覚えたのだった。
「募金でんすっか?」
店長はそう言ったものの、東日本大震災のときのことを投げやりに話し始めた。
「あんときゃあ、もう店が潰れるかと思ったじ」
津波の映像があまりに衝撃的で、人の命を奪った波と戯れるなど言語道断。サーファーは気の狂った人間だ、というイメージが蔓延した。サーフショップは閑古鳥が鳴いて募金どころではなかったという。
「俺(オイ)だって、しばらくは海に入れんかったもんな」
「店長でん怖くなりましたつ?」
「いや、そげんこつじゃあんさ。波乗りするこつに罪悪感みたいなもんがあったんじ」
それがいつしか薄れ、客ももどってきた。そしてオリンピックの正式競技となってからは再びブームがやって来た。
「喉もと過ぎれば、てやつだな。まあ、おかげでこんげやって商売やってけるけんどな」
画面には給水車に列をなす人々、炊き出しの握り飯を配る風景が映し出されている。そのどこにも迷彩服の男たちがいた。その顔は、ほとんどが智志と同じ年代の若者たちだった。
――俺はここで、こんげなことをしてていいんじゃろか……。
智志は鏡に映った白黒パンダのような自身の顔を見つめた。
「あれも公務員には違いん。安定はしちょる」
自衛隊に入ろうかと思う、と口にしたときのことだ。父は渋い顔で言った。銀縁メガネの奥で小さな目をさらに細める。
「だけんどん、防衛大出の幹部にでんならん限り定年は早いぞ。歳くってからどんげやって生きていくんだ」
堅実な道を歩んできた父は、大学を中退してプロサーファーという道楽商売の世界に足をつっこんだ息子に苦々しい目を向けてくるだけだった。
震災のようすを伝えるニュースを見ながら、これかな、と思った。体力にはそこそこの自信がある。波乗りの他には何の取り柄もない自分が、体ひとつで受け入れてもらえるのは自衛隊かもしれない。自衛隊に入ったからといって波乗りができなくなるわけではないだろう。そんな打算や甘えもあった。
ふと、思い浮かんだのが祖父、吉次郎の顏だった。吉次郎は幼いころから智志のよき理解者だった。父に見放されても吉次郎は智志の生き方を認めてくれた。
「好きなこつ、やりたいこつがあんなら、それを精一杯やればいい」
それで駄目だったら俺の仕事を手伝うなり継ぐなりすればいい、とまで言ってくれていた。
吉次郎は太平洋戦争のころ海軍の予科練に入って特攻隊員になったらしいが、特攻に行かないまま終戦を迎え、地元にもどってからは死んだ兄のあとを継いで農業に就き、今は果樹農園を経営していた。
海軍に入った吉次郎なら、自衛官になろうという自分の気持もわかってくれるだろう。そう思っていた。ところが、
「災害で人助けしなんなら、消防でん海上保安もあん。自衛隊は国防が本職で、しょせん軍隊だ。なんも軍隊に入るこたあねえじゃろ」
最近は口髭も真っ白になった吉次郎は腕を組んで首を横に振る。智志にとっては意外な反応だった。
「でん、爺ちゃんは国を守るために海軍、入ったんじゃろ?」
初夏の陽射しが海面に照り返す。祖父の顏がゆらゆらと海の中に溶けてゆく。宮崎から遠く離れた湘南の海。弱い陸風に撫でられて海面は滑らかだ。波の来る間隔も長いので静かな海面を透かして海の中が見える。この稲村は湘南の中でも水が綺麗なほうで透明度は高い。海底に藻が揺らめいているのが見える。
その海藻の影で、また何か蠢くものが見えたような気がした。智志はボードに跨ったまま、海中を透視するように覗き込む。
「なんかいるか?」
裕二が智志のようすを見て怪しむような目をした。
「今、なんか動いてたみたいなんだ」
目を海中に向けたままつぶやく。
「タコじゃねえか? この辺りけっこう生き物は多いんだ。俺もよく潜ってタコとかサザエなんか獲るよ」
言ったあとすぐに、内緒の話だけどな、密漁だし、と小声で笑った。
「いや、タコじゃないな。もっと大きな……」
何かが海底を這うように…….。

「おい、まさかサメじゃねえだろうな。この辺りでもときたま出るからな。俺の知り合いで足食われたやついるし」
知り合いと言っても友達の友達からの聞き伝てだという。真偽は怪しいものだ。
「いや、気のせいかもしれん」
そう、気のせい、かもしれない。そんな気がした理由(ワケ)もあった。
「この辺はカジメがいっぱい生えてるから、波で揺れて、そう見えたんじゃねえの」
裕二はどうということのない顔でつまらなそうに言ったあと、「俺も潜っていて、でっかいカジメの林に入っちまったとき、化け物にでも絡まれたみたいで、すっげえ気持ち悪かった」と言って笑った。そして、
「そういえば、おっさん達から聞いたことがあるな」と遠い沖を眺めた。
「おっさん達?」
「ああ、この辺りの古株サーファー連中さ。今じゃレジェンドなんて言われてるけど、この稲村、いやきっと日本で最初にサーフィン始めた連中だよ……」
戦後、進駐軍の兵隊たちが捨てていったサーフボードで波乗りを始めたかつての少年達が湘南にサーフィンを根付かせ、今では稲村クラシックの大会運営事務局として台風が来るたびに大会を開催するかしないか寄合で決めているという。そのおっさん達から聞いた話だという。
「終戦直後、進駐軍の兵隊(GI)で西海岸のサーファーだった連中がここの波に目をつけたらしい。そりゃあいい波だもんな。で、波待ちしていると、海の中に何かわけわかんないのがいて、竹槍で突っつかれたんだってさ。ボードに穴開けられたやつもいたらしい」
「海の中から? 竹槍?」
「ああ、GI連中の間じゃ、日本軍の兵隊の亡霊だ、て噂が広がって、みんな怖がって来なくなっちまったらしい。それで、ここがおっさん達の天国になった、てわけさ。それまでは波乗りするの指くわえて見てただけなんだけどな」
「へえ、稲村にそんな伝説があったんだ」
つづく
次回(2)はコチラ