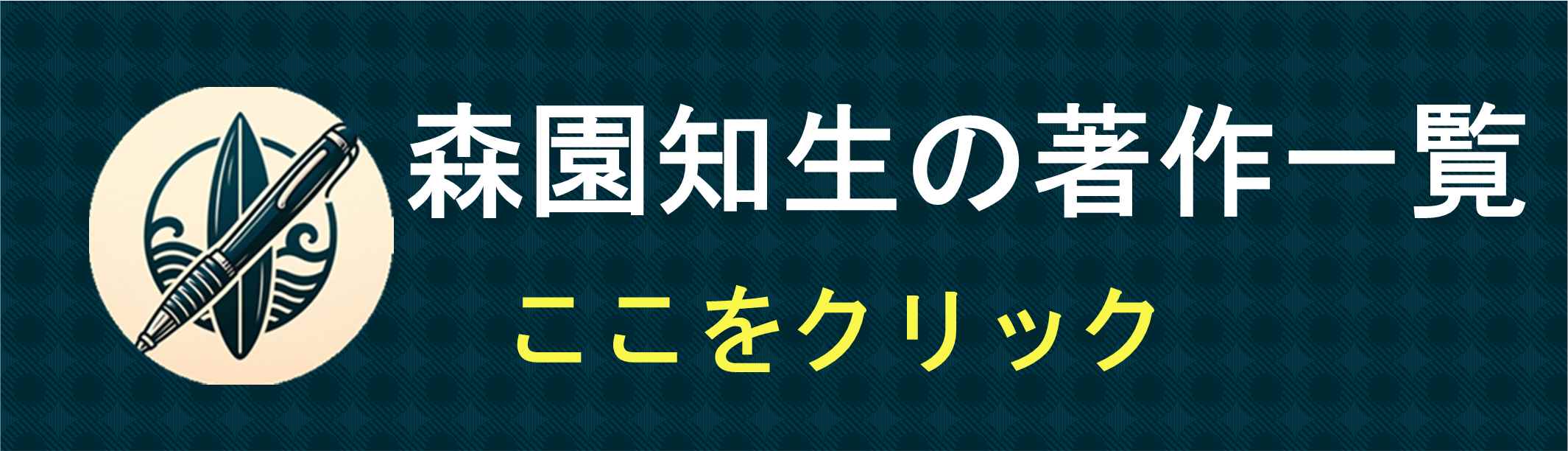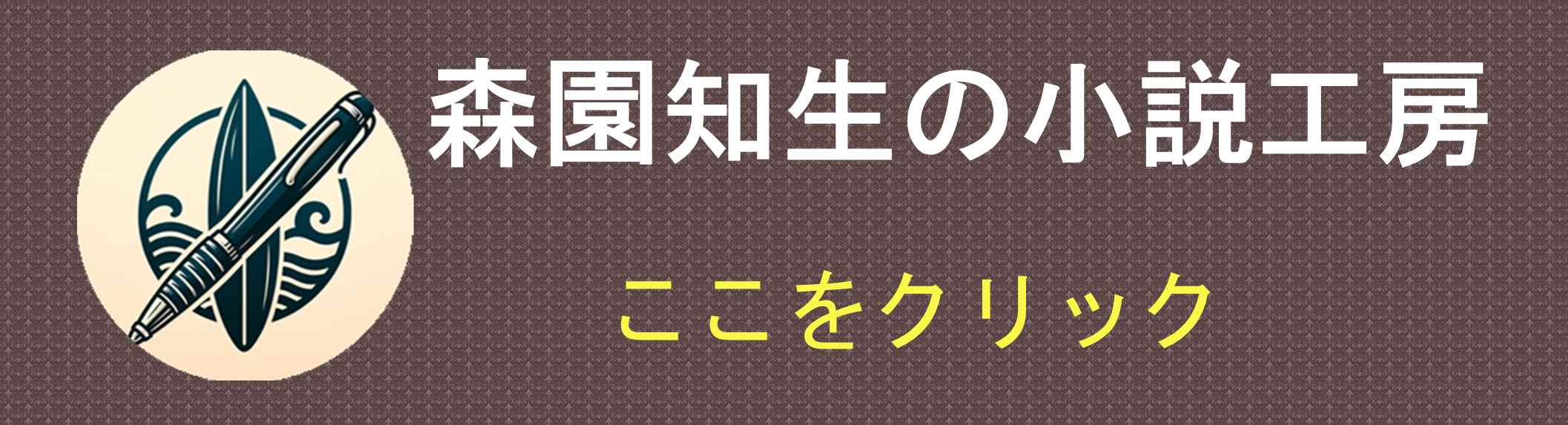化粧坂(ケワイザカ)から銭洗弁天に行くという若い男女を英勝寺の門前で降ろす。携帯を見ると着信が一件入っていた。
《少し暖かくなりましたね。いかがお過ごしですか。私は……》
俊輔(シュンスケ)は小さなため息をつく。そして返信のボタンを押すことなく携帯を閉じた。
梶棒(カジボウ)を左脇へ持ち上げ、右手で支木(シモク)を押して空俥(カラグルマ)を曳きはじめる。鎌倉駅まで戻ってまた客待ちをしなければならない。
まだ冷たさの残る空気に若葉の匂いがまじる。客待ちで道に立っていると肌寒いが俥を曳いていると汗ばむくらいの陽気だ。だから背中に〈爽風亭〉と染めぬいた半被を脱ぎ、鯉口シャツに腹がけだけという軽装になっていた。
脇を走る横須賀線の音を聞きながら寿福寺まで来たときだった。

山門の前は木立に覆われている。その隙間から丹塗りの総門が見える。ふと人影が見えたような気がした。平日なので観光客の姿は少なく、この扇ガ谷のあたりも閑散としている。それでも参拝客の一人や二人いてもおかしくはない。人力車はいかがですか、とひと声かけてみようと思い梶棒を門のほうへ回した。ゆっくり近づいてゆく。と、人影が門柱に寄り掛かるようにしてうずくまっている。どうもようすがおかしい。梶棒を降ろし、支木を飛び越すように跨いで駈けよった。
女が膝をつき、塗りの丹が剝げた太い門柱にしがみつくようにして喘いでいる。濃紺のワンピースがよじれ、その肩が大きく上下に揺れている。
「大丈夫ですか」
背中から声をかけたが返事はなく、早い呼吸を繰り返している。近寄って肩に手をかけながらもういちど呼びかけると、息が、と荒い呼吸の合い間にようやく声の漏れるのが聞こえた。足元にスプレイ缶が転がっている。噴射口に口当てのカップが付いたものだ。それは俊輔もよく知っている。酸素缶だ。かつて何度もそれを使ったことがある。自身にではなく、中継所に駈けこんでくるなり倒れ込んだ選手に宛がうのだ。空気の供給を越えてフル回転した肉体に新鮮な酸素が充満してゆき、しだいに苦しみから解放された表情になってゆくあの駅伝中継所の光景が一瞬脳裏に浮かぶ。
とっさにスプレイ缶を拾ってノズルを押してみる。間違いなく酸素か? 異臭のする気体が噴き出しやしないか確かめたのだ。が、気体の吹きだす手ごたえがない。空? えっ? 動揺する。すぐに何とかしなければ。病院? それとも、どこかで酸素缶を手に入れるか? スポーツショップだったら……、そう、かつてはそこでまとめ買いしていた。だが、そんな店をこの付近で見た記憶がない。頭の中が混乱したまま女の腕をとって肩に載せる。と、首から肩にかけて乳色の肌があらわになり香水の匂いがした。肩から服と同じ色をしたレースフリルのストラップが覗いている。目を逸らせて気合いを入れ、抱きかかえる。そのまま俥に運んで座席に座らせる。
病院は? 思いつくところを頭に浮かべ、道順をイメージする。横須賀線の踏切を渡って川喜多映画記念館前の路地を抜け、若宮大路を南へ下ったところに……。だが、そこまではけっこうな距離がある。背中で荒い呼吸が聞こえる。スポーツショップならばまず間違いなく手に入るのだが……。行き先の定まらないまま梶棒を握って走り出す。ふだん観光客を乗せているときの何倍ものスピードだ。駅が近づくにつれ商店が多くなってくる。ふとコンビニ店の看板が目に入った。祈るような気持で飛び込み店員をつかまえる。口元に向かってノズルを押す仕草をしながら酸素のスプレイ缶、と言うと、ございます、という若い女性店員の笑顔が返ってきた。
「ほんとうにありがとうございました」
女性がようやく口をひらいた。髪がほつれて頬にかかり、まだ呼吸は少し乱れているものの、だいぶ落ち着いた顔色になっていた。
「病院へ行きましょうか」
「いえ、よくあることなんです。もう大丈夫」
言い終えるまえに酸素缶のカップをまた口にあてた。濃い桜色のくちびるがカップに隠れ、細い顎の下に小さなほくろが見えた。身なり話し方からして五十前後とも思えるが、顔つきはそれよりも若く見える。服の胸元を整えたのか、さっきまで肩から覗いていたレースフリルのストラップはもう見えていない。
落ち着いて考えてみれば救急車を呼べばよかったかもしれない。そう反省をしながらも、狭く入り組んだ鎌倉の道を通り抜ける救急車のことを思うと、結果としてはこのほうが早かったのではないか、と胸の中で言い訳した。
「そこの路地を左へ」
背中の声にしたがって角を曲がる。もしや曽賀邸?
「その石垣の門で停めてください」
やっぱり。
黒ずんだ火山岩の石垣に蔦が這う。その葉影から緑青をふいた銅板の表札に〈曽賀〉という文字が見えた。

小学校の校庭ほどもあろうかと思える芝の庭が、なだらかな勾配を登っていく。その向こうに尖った屋根の洋館が見える。このあたりは明治以降、華族や士族の別邸や外国人の邸宅が多く建てられている。観光客を乗せてこの門を通ったときには、鎌倉の数ある古い洋館のひとつだと説明していた。まるで明治時代の探偵小説にでも出てきそうな風情の漂う館をカメラに納めてゆく観光客も少なくない。
「少し寄ってらしてくださいな。お礼もしたいし」
女性は初めてにっこりと微笑んだ。
俥を曳いて庭園内の小路を登って行くと、煉瓦造りのポーチが見えてきた。緩やかな石畳の坂を登ると青い瓦屋根の下が車停めになっている。南国風にソテツの植わった玄関の前まで来たときだった。小柄な老女が扉を重たそうに押し開けて現れた。歳格好は女性の母親ほどに見える。おそらく人力車が門を入ってくるのを館の中から見ていたのだろう。
「どうかされましたか、蓉子(ヨウコ)さん」
「また、ちょっと発作が。で、この方にお世話になってしまって」
「まあ、ですから私がお伴しようと申しましたのに」
どうやら家政婦のような人らしい。仕える立場にありながら歳若の主を諌めるような顔をした。
俊輔はなんども辞退(コトワ)ったのだが、蓉子と呼ばれた女性は頑として聞き入れない。包み込むように手をとられ、玄関にひきずり込まれてしまった。力ずくというより、懇願する彼女のまなざしと柔らかな手の温もりに辞する気持が萎えてしまい、ついふらりと入ってしまったのだ。
吹き抜けの高い天井を仰ぎ見る。天井近くまである縦長の窓はステンドグラスになっていて柔らかな虹色の光が射し込んでいる。玄関の奥から階段が登ってゆく。そこにも床と同じベージュ色の絨毯が敷かれている。
ほとんど下着同然の鯉口シャツに背中が襷がけになった腹がけ、下は脚にぴったりはりつくような股引という俥夫の出で立ちが、およそこの場に相応しくないような気がして、俊輔は顔が熱くなった。
親方はねじり鉢巻きにしている手ぬぐいを俊輔はバンダナのように巻いていた。それをとって首にかけ、上り口に腰掛けて地下足袋を脱ぐ。汚れて綻びの見えるボロ雑巾のようなそれを、モザイクタイル貼りの広い玄関に置いたままにするのが恥ずかしく、なにやら惨めな気分だった。
「ほんとうにあなたがいてくれなかったら、どうなってたことか」
肺に持病があってときどきあのようなことになる、という。自宅には酸素吸入器のボンベが置いてあり、外出時は酸素のスプレイ缶が手放せないという。今日はたまたま残り少なくなった缶を持って出てしまったと、失敗を悔やむように弱々しく笑った。と、濃い桜色のくちびるがほころび、顎のほくろが揺れる。俊輔はついそこに目がいってしまう。
そこはサンルームというのだろうか。居間の一画が庭にせり出したところに白いテーブルが置かれ、蓉子と呼ばれた女性と面していた。

さきほどの老女が紅茶を運んでくる。言葉少なく笑顔も見せない。けして愛想はよくないものの、主への従順がふるまいに滲みでている。
「これ、お口に合うかしら。私は気に入ってるんだけど」
言いながら広口のガラスビンに入った黄色いジャムのようなものを小皿に取り分ける。庭に成った夏蜜柑をママレードにしたものだという。紅茶の湯気に柑橘の香りが混じる。それに誘われてスプーンでひと口、と、思ったほど甘くなく、ほのかな皮の苦みがあった。
「由井さんのお手製なのよ。あっ、由井さんて、さっきのひとね」
家政婦のような老女のことらしい。
そういえば、と思い出したように今さらながらお互いを紹介しあう。
「竜崎俊輔といいます。爽風亭の」
女性は曽賀蓉子と名のった。
「うちでは由井さんにも奥様、なんて呼ばないように言ってあるの。私も由井さんのこと婆やなんて言わないわ。私のお祖母さんでもないのに、へんでしょ。だからあなたも私のこと奥様なんて言わないでね」
奥様と呼ばれるたびに夫の先妻を思い出す、と笑った。
「ではなんてお呼びすれば」
これからさき呼ぶこともそうないだろうと思いながらも問い返したのはただ会話のなりゆきにほかならなかった。
「蓉子でいいわ。私もあなたのこと俊輔さんて呼ばせてね」
さっきまでとはうってかわって、ずいぶんと明るく元気だ。妙にうちとけ過ぎているような気もし、なにやら照れくさい。
夫は五年前に亡くなっていて、今は住みこみ家政婦の由井さんと二人きりだという。蓉子は、何も知るはずのない初対面の客に自分を紹介しているつもりらしいが、曽賀邸の未亡人のことは巷の噂で聞いていて、俊輔もあるていどのことは知っていた。
夫は実父の創業した横浜にある貿易会社の二代目社長で、先代が中華料理の材料にする乾物食品の取引でひと財産を築いたらしい。
「でも、あのひとにとっては仕事より人生を楽しむほうが大事だったみたい」
顔を庭に向け、遠くを眺めるような目をする。その視線のさきに夫の面影が浮かんでいるのだろうか。その夫は、どうやら事業を拡大するより父親の築いた財産で気楽な人生送ったようだ。
曽賀邸の未亡人は結婚まえに銀座のクラブでホステスをやっていた、ということも噂に聞いていた。初対面でありながら、いつのまにかうちとけた会話に相手をひきこんでしまうのも、そのせいかもしれない。ことさら聞き上手なのだろう。そんなつもりのなかった俊輔が、いつのまにかめったにしない学生だったころの話をしていた。
「あら、大学でも陸上競技やってらしたの。それで今、人力車を?」
少し意外そうな顔をする。
たしかにそうかもしれない。あのころの俊輔自身、今の自分を予想していなかった……。
「四年生の中には悔しい思いの者もいるだろう。その気持はじつに……」と、たしか、監督はそこで言葉をつまらせた。
ふと、あの時のことが脳裏によみがえる。
思わずこみあげるものがあったのだろう。けしてポーズではなかったはずだ。監督自身かつては選手だったのだから……。
「じつに、痛いほどわかる。だが、その悔しさを逆の力にして、精一杯チームをサポートして欲しい」
言葉につまった自身をふりきるように目を凝らし、全員を見まわす。
合宿所の食堂に、その声が静かに、そして重々しく響いた。
十人の選手。そして六人の補欠選手の中にも竜崎俊輔の名はなかった。人生の中で箱根駅伝に出場できるチャンスは大学生活の四年間だけ、四回しかない。監督のその日の訓示で、四年生の俊輔にとって箱根駅伝に出場するという夢は完全に終わった。
俊輔は神奈川県の辻堂に生まれ育った。家の前は箱根駅伝の往路三区、復路八区の県道に面していた。そのため、正月といえば、ものごころついたころから、雑煮を食べたあと沿道で旗を振ってランナーを応援していた。

選手がみるみる近づき、目の前を風のように駈け抜けてゆく。その瞬間、叫びにも似た声援が飛び、あたりがどよめく。蝶の群れが飛び立つよういっせいに小旗が振られる。幼少の俊輔もわけがわからないまま興奮し、旗を振って叫んでいた。一年はそうやって始まり、毎年繰り返すうち、やがていつか自分もここを走りたいという気持が芽生え、白バイに先導されて華やかな声援を受けながら走る自分を夢見た。そしていつしかそれが人生の目標になっていた。
中学時代はサッカーと陸上の二股だったが高校からは陸上の中長距離一本になった。しかし県大会で目立った成績をあげられなかったので、一般入試で箱根に出るチャンスのある大学を狙った。高校では日本史、世界史といった歴史科目が好きだったので県内に一二年のキャンパスがある城山(シロヤマ)学院大学の史学科に入り西洋史を専攻した。同じ学科には体育会の学生はおらず、どちらかというと女子が多かった。
三年のときに最初のチャンスが回ってきた。俊輔も参加した予選会で好成績をとり、城山学院大学は五年ぶりに箱根駅伝の出場権を獲った。だがその後の練習中、太腿の筋肉に割れるような痛みが走った。その痛みには覚えがあった。中学のときサッカーの練習中、太腿に痛みが走り、それが肉離れという筋肉の怪我だということを知った。あのときの痛みと同じだ。そう思った瞬間、頭を殴られたような気がした。それでも痛みを隠して練習していたが、走っているフォームを監督に見抜かれ、選手候補から外された。肉離れそのものは1ヶ月ほどで治ったが、いったん落ちたタイムは伸び悩み、苦しんだ。有望体育会学生が受けられる奨学金を二年のときから貰っていたが怪我をしてからは停止された。俥夫のアルバイトを始めたのはそのころだった。
箱根駅伝に出場して高校の教員となり陸上部の顧問として指導者になりたいと思っていた。だが、三年生のときに挫折してからは社会科教員免許状だけはなんとか取ったものの、教員採用試験にも就活にも身が入らず、アルバイトでやっていた人力俥夫を卒業後も続けていた。
つづく
次回(2)はコチラ