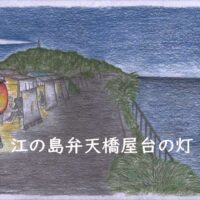この記事は前回からの続きです
■前回までのあらすじ
俥夫の俊輔は、寿福寺の山門前で呼吸不全に苦しんでいた曽賀夫人を助け、人力車で自宅まで送り、もてなしを受ける。曽賀邸の居間には、亡くなった主人が愛でたという青磁の壺と、古の港湾跡、和賀江島で拾い集めた青磁の欠片が飾られていた。後日、俊輔は人力車に蓉子を乗せて和賀江島を訪れ、古の港に想いを馳せる。ところが海辺でバーベキューパーティーをしていた若者が、空き缶を海に蹴り入れたことに蓉子が激怒。俊輔は、その過剰な反応に戸惑うのだった。
爽風亭の親方、松男は、蓉子には男関係で悪い噂がある、と俊輔に忠告する。俊輔は、それを真に受けないながらも悶々とする。
蓉子に文化講座講演会場への送迎を頼まれ、人力車で送った日、俊輔は、着物姿の蓉子に、いつもと違う何かを感じる。その日の講師は俊輔の母校の准教授で、かつて女子学生にも人気のあった江波浩二だった。講演会終了後、俥で迎えに行くことになっていたが、蓉子から、講師を囲んでのお茶会になったので迎えは要らないと連絡が入った。
俥曳き俊輔の逡巡(4)
「俊輔さん、ほら、あそこ。鳥居の下。右の柱のとこにいらっしゃる方よ」
背中から蓉子が声をかけてくる。言われたとおり鳥居のあたりを探す。太い柱の周りを見る。と朱塗りの柱を背に白っぽい上着を着た男が目にとまった。
文化講座の先生と和賀江島へ行くことになったので送迎を頼みたい、と蓉子から連絡が入ったのは五月の中ごろのことだった。もし俊輔の都合がつけば和賀江島の散策もいっしょにつきあわないかという。その待ち合わせ場所が八幡宮の三ノ鳥居ということだった。
「先生ー!」
蓉子が俊輔の背中から、まるで少女のような声をあげる。鳥居の周囲にいる観光客がいっせいにこちらを見る。その中で白っぽい上着の男が手を挙げた。少し恥ずかしそうに肘から上だけを挙げ、小さく手を振っている。きっと蓉子も座席で手を振っているに違いない。
「こちら、竜崎俊輔さん。私の専属の俥夫さん。てことはないか」
そう言ってくすっと笑った。今日の蓉子はブルーストライプのストレッチシャツに白いスリムのデニムという軽装だ。
「爽風亭の竜崎です」
言って頭を下げる。
「こちらは城山学院大学の江波浩二先生。ご専門は日本中世史」
蓉子が江波を俊輔に紹介する。
細面で切れ長だがくっきりした目。縁なしの眼鏡が少々気障な感じに見えるところは俊輔が学生だったころと変わっていない。それでも端整な顔立ちはたしかに俳優でも通用しそうなくらいだ。
「あっ、そういえば俊輔さんは大学で西洋史を勉強されたのよね」
首を横に傾げながら俊輔に微笑む。
ここでその話が出ないことを内心願っていた。なのに、やっぱり言われてしまったか、と小さくため息をついた。
「へえ、そうなの、西洋史ね。で、学校はどちら?」
にこやかな表情のままだが、縁なし眼鏡の奥からまっすぐな視線を向けてくる。
「ええ、じつは……」そこで一瞬つまる、が「じつは先生の大学です」と小さな声で答えた。
「えっ? 俊輔さん、城学だったの? なーんだ早く言ってちょうだいよ」
「ほう、そりゃあ奇遇だな。西洋史、ていうと……」
しばらく教授や准教授の名前を挙げ連ね、お互いうなずいて納得し合う。
「ひょんなとこで盛り上がってしまったけど、まあ、時間のこともあるからそろそろ行きますか」
江波の言う時間とは潮の干満のことだ。今日は大潮で干潮の時刻に合わせて和賀江島へ行くことになっていた。
「先生、お参りのほうはお済ませになりました?」
江波は中世鎌倉を専門としていることもあって鎌倉へ来た時は必ず八幡宮へ詣でることにしているという。それで待ち合わせが八幡宮前となったようだ。
今日の蓉子は着物のときとは違って、軽やかに蹴込へ足を掛け、座席へ上がった。そのあとから江波がやや慣れない動作で上がってゆく。それでも、おそらくまだ30代ということもあって体に弛みはなく、身のこなしは軽そうだ。
「けっこう高いんですね。人力車の上って」
「先生、初めて?」
「ええ、鎌倉や京都でよく見かけて、いつか乗ってみたいとは思ってたんですが、なかなかチャンスがなくて」
「そう、じゃあ今日は私と二人でデートね」
そう言って蓉子が江波に微笑みかける。白いスリムのデニムが年齢にそぐわず若々しい脚の肉感を浮き彫りにしている。その横に江波のスラックスが触れるほど近寄って並ぶ。
俊輔は緋色の膝かけを二人の腿に被せた。その瞬間、座席の空間が二人だけの世界になったような気がした。ふだん客を乗せるときには感じたことのない何かが俊輔の胸の中で靄のように湧きあがってくる。自分だけ疎外されたような、妬みにも似た気持……だが、それをふりきるように前を向き、支木を押して俥を曳き始めた。
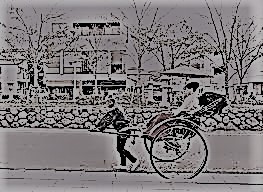
観光客の群れる三ノ鳥居をあとにし、若宮大路をまっすぐ南へ下る。右手には頼朝が政子の安産を祈願して築いたという段蔓が続く。大路の中央を走るいちだん高くなったその石垣の堤は、ひと月前まで桜の咲く並木路だった。やがて大路に桜吹雪が舞い、今はすっかり緑の若葉に覆われている。
自動車も走っているが、段蔓の切れる二ノ鳥居より先は、広く真っ直ぐな道で走りやすい。ついスピードを出してしまう。やがて向かい風に潮の香りがまじりはじめる。石組みの一ノ鳥居を過ぎると由比ヶ浜の海がきらりと光った。
海岸通りへ出ると材木座海岸に陸揚げされた漁船の向こうに逗子マリーナの赤い屋根と椰子並木が見えはじめる。その手前の海に、浅瀬がふだん見ることのないほど広く姿を見せていた。和賀江島だ。中潮のときであれば円形の島がぽっかり浮かぶていどだが、大潮の干潮ともなると海岸とつながって歩いて渡れるようになる。
「これはまるで潮干狩りだな」
〈国指定史跡 和賀江島〉の碑の横に立った江波が眩しそうに額へ手をかざして干上がった浅瀬を見渡す。

「昔は港でも、今はただの磯と変りありませんものね」
蓉子の言う通り、蟹やヤドカリといった磯の生物の生息環境に適しているため、潮が引いたときには小さな子供連れの家族が磯遊びに来るような場所になっていた。今日も黒々とした磯の風景に色とりどりの服が切り絵のように散りばめられている。
潮はほとんど引いていて水の溜っているところはあまりないが、いち面ごろごろした玉石の岩原で歩き難い。三人とも注意深く足を運ぶ。
「今日はかなり干上がっているから水際の辺りには掘り出し物があるかもしれないね」
江波が足場を探りながら講釈する。考古遺物である青磁片はほとんど採り尽くされてしまったが、一年のうちでも潮の干満の大きな春先から初夏にかけての大潮の日だけ海上に顔を出すような場所には、まだ人の目にふれていない遺物が眠っているかもしれないという。おそらく蓉子はそれが目的で江波に声をかけたのだろう。
「じゃあ、私はそれを探しにいってきますわ」
そう言ってひとりでどんどん先へ行ってしまった。

江波は青磁片にはそれほど興味がないようだ。それより和賀江島から稲村ヶ崎や江ノ島、そして鎌倉を囲む三方の山といった中世城塞都市の外観を見ておきたいと言って立ち止った。鎌倉時代の港湾からもきっと同じ風景が見えていたはずだから。そして中世の鎌倉は現存する建造物の中にはなく、その本当の姿は、地形に重ね、想像の中に再現させるしかないという。
「目に浮かべるのさ、中世を」
そうつぶやいて江波はじっと遠くを見た。
俊輔はそのようすを見て、以前蓉子とここへ来たときのことを思い出した。
――彼女もそうしていた。
そう思ったとたん、胸の奥が少しだけ揺れた。
「曽賀さん、なんかはりきってるな」
江波が先へ行ってしまった蓉子のうしろ姿を目で追っている。そして口の横でにっと笑った。
それを見て俊輔はふと思い出した。江波のその冷めた微笑が、どうやら女子学生に人気があったらしい。
「先生はもてましたよね」
事実を言ったまでだ。だが、ねじ曲がった皮肉が入っていたことは否めない。
江波はまたふっと微かに冷たい笑みを浮かべる。
「否定はしないけどね。でも正直迷惑なこともあったよ」
うすい笑いを浮かべたまま稲村ヶ崎のほうを見る。だが目は笑っていない。海風が江波の髪を揺らす。
「もてる男はつらい、てやつですか?」
あてこすり。どうしてこんなに絡むのだろう、と自分でも思いながら江波の目を見ないで言った。
「君は何年卒?」
それを聞いてどうする? だが、応えないのも不自然だ。つとめてさらりと言う。と、少し考えるような間があく。
「そうか、あのころか」とつぶやく。
思い当たることがあるようだ。おそらく例の噂のことだろう。やはり何かあったに違いない。火のない処に煙はたたない。
江波は無言で小さく首をふった。
「曽賀さんて、いい女だよな」
冷ややかな笑みを浮かべたまま俊輔を見る。いい女、という言い方に猥雑な匂いがした。本人が聞いたら不快に感じただろう。唐突に飛び出したその言葉は、ボディーブローのように俊輔の脇腹をえぐった。
「なんですか突然」
軽くかわすように笑いとばそうと思ったが、くちびるでしか笑えない。
「好きなんだろう? 彼女のことが」
さらりと撫でるような言い方。なのに俊輔は、ぐさりと刺されたような気がした。言葉の剣は江波のほうが上手のようだ。
返答につまる。
「なんですか突然」
動揺を顔に出さないようにしながらも、それしか言えない自分が情けない。胸ぐらを掴まれて押し倒されたような気分だった。
「でも、セックスはできないよ、彼女」
表情を変えないまま、さらりと言う。
――なんなんだよ、突然。
あまりにあからさまな言いように言葉も出ず、かたまってしまった。胸の奥まで見透かされているような気がした。
「いいよな、若いって」
小さくため息をつくように言ったあと、これは皮肉じゃないよ、と言い添えてきた。
「なんで、そんなこと、あなたにわかるんですか」
言葉の投げ合いに押しまくられ、受け応えに遅れをとる。動揺で足をすくわれ、思考が釘付けになっていた。
「本人から聞いたのさ。彼女、慢性の呼吸不全の持病があって医者にも止められてるんだってさ」
いったいどんな状況でそんなことを聞いたというのだ。と、喉まで出かかってやめた。かわりに、
「そんなことくらい、ぼくだって……」
見栄をはって言いかけ、やめた。知っているのは呼吸不全ということだけだった。
「ああ、そうだったな。彼女が発作を起こしてるところを助けたんだってね」
目線を俊輔から沖へ移しながら、「さっき来る途中聞いたよ」とつぶやいた。
――この人にはなんでも話すんだ。
そう思いながら、目で蓉子の姿を探す。また発作でも起こしていたら……。
遠い波音が耳によみがえる。ずっと鳴り続けていたはずなのに、いつの間にか江波の言葉しか耳に入っていなかった。
海藻の匂いがする。それもずっと匂っていたはずなのに……。
だいぶ離れたところに蓉子らしい姿が見える。小波が打ち寄せる浅瀬の端で、じっと沖を見つめている。まるで波打ち際に立つブロンズ像のようだ。背中しか見えないが、なにか祈りを捧げているかのようにも見える。
「先生は青磁にもお詳しいんですか」
ふと、あのことを確かめたくなった。
「まあ中世の日本には中国の青磁や白磁がずいぶん入ってきているからね。考古資料としては重要なアイテムだね」
「そうですか、じゃあ蓉子さ……、いえ曽賀さんに、後周の柴栄が青磁を作るよう命じた話ってされました?」
「雨過天青(ウカテンセイ)のこと?」とさらりと返ってくる。
――やっぱり。
「うーん、どうかなあ」と少し考えるような目をする。そして「まあ、市民講座なんかでも青磁の話はよくするけどね、青磁といえば『雨過天青雲破れる処の器を持ち来たれ』っていうあの話は有名だから、話したこともあったかもしれないな。はっきりとは覚えてないけど。それがどうかしたの?」
「いえ、曽我さんが話してくれたんで」とまで言い、先生がお話しされたのかな、と思って、という言葉は飲みこんだ。
江波のほうは忘れていても彼女の心には焼きついていたのかもしれない。
江波が俊輔をじっと見ている。今のことで、また何か言葉の剣を投げつけてくるのかと身構える。と、
「たしか……」と俊輔の卒年をつぶやいて言葉を止め、なにかを思い出そうとする目をする。やがて「そのころだったな。史学科に陸上部の選手がいたよな。たしか竜崎……」とつぶやく。
どうやら気づかれてしまったようだ。
――なんであんたがそんなこと……。
たしかに史学科は文学部の中でも小所帯だった。
「そうか。君が、あのときの竜崎君か」
ふと江波の目が少しだけ柔らかくなったような気がした。俊輔はそのまま黙っていた。だが、無言でいることは肯定することになる。
「史学科で体育会の学生なんて珍しかったからね」
俊輔を見つめながら、どこか遠くのあのころに想いを馳せるかのような目をしている。
――知られたくなかった。
俊輔はいたたまれない気持になった。
頭の中に、あのときの絶叫が聞こえてくる。
四年生の俊輔は選手のサポート役で復路の鶴見中継所に待機していた。
落胆の悲鳴が飛び交う中、合図の号砲とともに城山学院の選手がひとりスタートしていった。
トップのチームが中継所を通過してから二十分が経過しても中継所に到着できなかったチームは襷を受け渡しすることなく繰り上げスタートしなければならない。それまで走ってきた選手の汗が滲みつき、想いのこもった襷を繋げられないのは駅伝においては無念このうえない。勝敗よりもそこに意味を見出すむきもある。その繰り上げスタートから十秒と経たぬうちに、ふらふらと今にも倒れそうになりながら選手が近づいてくる。絶叫のような声援で中継所が騒然となる。
「頑張ってー!」
今にも泣きだしそうな女性の声が飛ぶ。
俊輔はタオルを持って迎えに出た。前のめりになりながら入ってくる三年生を俊輔はタオルで包みこむように受け止めた。が、ランナーの勢いを受け止めきれずそのままいっしょに倒れこんでしまった。硬く冷たいアスファルトに背中を打ちつける。
「すいません。すいません……」
ぜいぜいと荒い息で喉を鳴らしながら、ようやく声を出す選手。意識も朦朧としているようだ。目から涙があふれている。
俊輔はその三年生の顔を見ながら、やはり涙がこぼれた。慰めてやりたかったわけではない。よくやったと褒めてやりたかったからでもない。
――なんだよ、おまえ、まだ声を出す元気があるじゃねえか。
悔しさ。せつなさ。自分でも説明しようのない嫉妬にも似た感情がこみ上げてくる。
――俺だったら、俺だったら、血へど吐いてでも襷をつなげてやるぞ。そのまま死んでも、それが出来りゃあ本望だから。
箱根を走ることができたら死んでもいい。本気でそう思った。
だが、それが出来なかった。そのチャンスももうない。
そんな想いをずっと引きずっている。
あの時の情景が脳裏に浮かび、消えてゆく。
つづく
次回(5)最終回はコチラ
<ご参考>
■和賀江島のドローンによる空撮動画(Youtube)