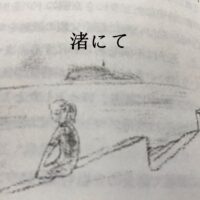第一話のあらすじ
坂本浩一は、一粒の蓮の種を窓から投げ捨てた。それは幼いころ、二宮初江と蓮池で遊んだ想い出の標(しるし)であるとともに、妻、洋子への裏切りの証でもあった。初江への想いは清算したはずなのに、病の心痛からか、初江との思い出が抑えがたくよみがえってくるのだった。
第一話はコチラ
開け放った窓から、黒い松林が見えていた。その松原に覆いかぶさるように低く垂れこめた雲が浩一の気持を滅入らせる。今日も水平線は見えない。
ずいぶんと長い間、罪深い関係を続けたものだ、と思った。会っているときは、まるで真(じつ)の夫婦のようだった。だが八年前にそれは終わった。初江とはきっぱり別れた。それからは一度も会っていない。けじめはつけなければならない。初江の方からも連絡をしてくることはなかった。彼女の決意も堅かったのだろう。
ただひとつうしろめたいのは、あの黒いドングリのような想い出の標(しるし)、それを持ち続けていたことだ。しかしそれも、数日前に捨てた。黒い種が、放物線を描いて窓から落ちてゆくのを、しっかりと見届けた。すべてを捨て去り 清算したと思っていた。なのに胸の奥に潜む記憶、想い出だけはいつまでも消し去ることができないでいる。弱い軟弱な人間という自覚はあったものの、自分がこれほどだらしない男だということを、あらためて思い知らされた。
「看護婦さん」
ベッドからはみ出したシーツを直しに来たのに気づいて浩一が声をかけた。
「坂本さん、誰に言ってるの?」
「ああ、ごめん、ごめん、また言ってしまった。看護師さんだったね」
まったく困った人だ、という顔をされた。
「今日は何曜日だったかな?」
「金曜日です」
少し面倒そうな顔で応える。
「ああ、じゃあ明後日(あさって)だな」
「はいはい、待ちどおしいわね」
首を傾げて微笑み、まるで子供をあやすような言い方だ。
「そんなんじゃないよ。俺たちはもう」と笑う。
照れ笑いと思われただろう。だが、本当は少し違う。妻の見舞は嬉しい。それでも夫婦の愛情というものとは少し違う。友人、かつての戦友が訪ねてくるような気持ちだった。妻の浩一にたいする接し方もどこかそんな匂いがする。強い者が弱い者をいたわる。強い女が軟弱な男を励ましている。しっかりしなさいよ、と。じつに情けない、が、それはそれで慰めにはなった。
そう、妻、洋子は浩一にとって戦友だった。
浩一はうしろめたい想いを抱えながらそう思った。ベッドに横になったまま顔を窓のほうへ向けた。
雲間から薄日が射している。死を受け入れる覚悟をしてからか、しきりと昔のことが想い出される。
野球部の野次が犬の遠吠えのように聞こえる。サッカー部のゴールキーパーが味方に指示する声は番犬が吠えているようだ。付近の住民から、放課後の中学校はまるで動物園のようだと言われていた。
木造の旧校舎と鉄筋の新校舎が並んで立つ。黒ずんだ旧校舎と白い新校舎のコントラストが浩一の記憶に残る湘北中学の風景だった。校庭は広く、サッカー部は半面コートだが野球部と同時に練習していた。バレー部は体育館。軟式テニス部は校舎の裏にある市営テニスコートを使っていた。
浩一は金網越しにテニスコートを見ていた。
女子の軟式テニス部員が素振りの練習をしている。男子のそれとは違い、甲高く柔らかな掛け声でみな一斉にラケットを振る。ひとりの女子がラケットを落とした。一年生でまだ握力がないのか、振る力も弱々しくラケットに振り回されている。それは初江だった。
上級生がネット越しに野球のノックの要領でボールを出す。一年生が順番に走り出て打つ。初江の番だ。何とかラケットに当たったものの、お手玉を叩き落としたような鈍い音がしてボールが地面を転がった。何度やっても前に飛ばない。
「ボール良く見て! 芯に当てれば飛ぶんだから」
上級生の声が飛ぶ。だが浩一が見るかぎり、か細い初江の腕では無理のように思えた。
初江は額の汗を手の甲で拭って息をつく。肩を落としてうつむく。とても楽しんでいるようには見えない。可哀そうだったが浩一は何もできなかった。
あのころJリーグはまだなく、社会人の日本サッカーリーグが人気を集めていた。ヤンマーの釜本や三菱の杉山に憧れて浩一はサッカー部に入った。練習が終わり、みんなと一緒に下駄箱まで来たときだった。靴のゴムと饐えた汗の匂いが入り混じった薄暗い下駄箱のすみに初江が立っていた。一年生の女子がおおかたそうなように、セーラー服が大きめで丈も少し長めだ。いつものように左手首を右手で覆い、もじもじしたような姿でたたずんでいる。自分を待っているのだな、と浩一は思った。小学校のころはほとんど毎日、初江といっしょに下校していた。蓮池へ寄ることもあった。まわりからはやっかみ半分に囃したてられたが、それほど気にはならなかった。というのは初江も浩一もひとりっ子で家が近いとあって幼いころから兄妹のように育ったからだ。年子の兄妹がいっしょに家へ帰る。それはごく自然なことだった。
だが、セーラー服姿の初江を見たとき、もう妹ではないような気がした。それにサッカー部の仲間と帰りに今川焼を買って食おう、ということになっていた。ごめん、と胸の中でつぶやき、初江には目くばせでいっしょに帰れないと伝えた。胸がちくりと痛んだ。横に小学生のころから二人のことを知っている友人がいて「いいのかよ」とわき腹を小突かれたが、「いいのいいの」とへらへら笑った。
夕食のまえだった。「初江ちゃんが来てるわよ」と母に言われて玄関の外へ出ると、夕暮の中にぽつんと立っていた。ふだん着に着替えている。以前よりスカートのすそが少し長くなって大人びて見えた。歩いて二分とかからない近くの小公園へ行くことにした。滑り台とブランコのある小さなスペースにベンチがひとつだけある。その小公園を奥に入るといくつかある蓮池のひとつに繋がっていた。
二人でベンチに座る。と、青みの残るみかんのような匂いがした。初江のそばでそんな匂いを感じたのは初めてだった。
「ちょっと相談したいことがあったの」
初江がそう切り出した。が浩一にはわかっていた。
「あたし、テニス部やめようかと思って」
少しうつむいて小さく言った。
「いいんじゃないの、自分でそう思うんだったら」
突き放すような言い方になってしまった。気持はそうではなく、無理することないさ、という意味だった。
「白いテニスウェア着て、ぽーんぽーんて、やれたら楽しいだろうな、て思ってたんだけど」
ふっと小さく笑う。
浩一は昼間の練習風景を思い出した。ラケットに振り回されるようなか細い体では無理だろうな、と思ったがそれは言えない。
「本当はまえから絵描くのが好きだったから、美術部にしようか迷ったんだけど、テニスもいちどはやってみたくて」
テニス部の顧問教師にも相談したが、一年だけでも続けてみては、ということだったらしい。
「やめりゃいいじゃん」と飛んできた虫を払いながら言った。
またきつい言い方になってしまった。やりたくもないことをいつまでも続けているより好きなことをやったほうがいい、と言いたかっただけなのだが。
「本当にそう思う?」
「ああ、俺もサッカー部やめようかな」
しまりのない声でぼやくように言った。
昨日も外回りのランニング中に気持ちが悪くなって吐きそうになった。試合では走りどおしのサッカーだ。練習が厳しいことはわかっていた。だが、こんな苦しい思いをしてもレギュラーになれる見込みはないだろうと思い始めていた。同じ一年生に木村栄治というのがいて、足が速くキック力もある。見ていると自分にはとても追いつけない気がしてきた。ゴールキーパーならば走る必要もない、と思ったが、これも同級生に体が大きくて横っ跳びもできるのがいて、一人しかないポジションはすでに決まっているようなものだった。
「なんで? やめてどうするの?」
「俺も美術部入ろうかな」
絵は好きでもなく得意でもない。口から出まかせだった。
「なんで?」
「楽(らく)そうだし」
「楽? あたしは楽だからじゃないよ。本当に本当に、絵が好きだから……」
終わりのほうは声がつまっていた。
「じゃ、なんで最初っから美術部入んなかったんだよ」
「だから、さっき、いちどはテニスも……」、と言いかけて「もういい」と怒ったような声になった。
「浩一くんは、浩一くんはやめないほうがいいと思う」
毅然とした顔で前を見る。
浩一は呆けたような顔をして夕暮の空を仰いだ。怒らせたかったわけではない。無理なものは無理。苦しい思いをしてまでやることはない。そう思っただけだ。それにしても、このごろ初江が少々鬱陶しくなることがある。嫌いになったというのとは少し違うのだが。
数日後のことだった。廊下で初江が二人の女子に詰め寄られていた。初江の視界には入らないようにしてようすを窺った。
「……先輩が、同学年から落後者を出すなって。私達が……」
きつい言葉が漏れ聞こえてくる。
初江は何も言えずにうつむいている。また左手首を握ってもじもじしている。可哀そうだった。助けてやりたいようにも思った。が、ひとりで女子の中に入ってゆくのが躊躇(ためら)われた。と、そのとき、
「なによ、べつにいいじゃない」
三人に割って入ってきた少女がいた。同じ一年生でバレー部の工藤洋子だ。小学校は別だったので話したことはない。だが体育館で大きな声を響かせて目立っている女の子だった。あのころ、数年前にあった東京オリンピックで、東洋の魔女と言われた日本の女子バレーチームが金メダルを獲ったことからバレーボール人気は高く、湘北中でも女子バレー部の入部者は多かった。その中でも工藤洋子は小柄ながら気合いの入った回転レシーブを見せ、おおすっげえ、と見ている男子を唸らせていた。
「人にはそれぞれ得意不得意があるんだから。二宮さんが自分で決めたんだったら傍からとやかく言うことないじゃないの」
両手を腰にあて、まるでスピッツが吠えているようだ。その工藤洋子の剣幕に押されて二人はたじろいだ。
浩一はこのとき、工藤洋子が少年ドラマのヒーローのように思えた。
大きく開いた美術室の窓から初夏の風が吹き込み、野球部の遠吠えやサッカー部の番犬の声が聞こえていた。
「楽しそうじゃん」
浩一は初江のスケッチブックを覗きこみながら怠惰に言った。
「部活は?」
スケッチブックに濃い4Bの鉛筆を走らせながら初江が空ろに聞き返す。荒い画用紙に石膏のヴィーナス像がデッサンされてゆく。
「うん、今日は休みにした。風邪気味なんだ」
「じゃあ、うつさないでよ」
浩一から体を離しながら言う。
「あたし、これがやりたかったんだ。美術部に変わってよかった」
ほころんだ顔が瑞々しく輝いていた。
浩一のほうは気分が浮かなかった。風邪というのは嘘で、校庭から聞こえる運動部の声がうしろめたかった。本当はサッカー部をやめたかったのだが、顧問の先生に相談するのが躊躇われ、なんとなく続けていた。そして今日は河原までの外回りランニングがありそうだな、と思った日は風邪になったり下痢になったりしていた。そういう日を嗅ぎつける勘というか、難題、難敵が近づくのを察知するアンテナは働く方だった。
「洋子、って優しいのよ」
突然、初江がぽつりと言った。
「洋子って、あの湘北中の魔女と言われてる工藤洋子?」
「うん、彼女、勉強もできて女子にも人気あるの」
じつは男子でも密かに工藤洋子に片想いしている者はいた。勝気な女の子だが、睨みつけるような目がどきりとするくらいかわいいときがある、と浩一も思っていた。
「運動もできて勉強もできて、羨ましい。でも洋子みたいになろうとも思わないけど……、絶対無理だし……」
どうやら初江は工藤洋子のことを同級生ながら姉のように思っている口ぶりだった。
その工藤洋子はレギュラーのセッターとなり、バレー部の司令塔的存在になっていった。そしてサッカー部のエース、木村栄治はスポーツ推薦でサッカーの強豪校へ進学した。
浩一は結局三年間サッカー部にいたものの、それは退部したり他の部に途中から入るのが億劫だったからにすぎない。二軍のゴールキーパーをやらされたり、練習中にいっとき空いたポジションの代役をやったりしながら渋々と続けていた。
そんな浩一が高校へ入ってから少し変わった。
初江は私立の女子高へ行き、浩一は共学の県立へ行くことになった。工藤洋子と同じ高校になったのはたんなる偶然にすぎない。
そして初江の一家は市内のマンションに引っ越しすることになった。それまでは道を隔ててはす向かいの家どうしだったので、兄妹の部屋が少し離れている程度にしか感じていなかった。だから引っ越しは、同じ市内とはいえ兄妹が離れ離れになるような心の揺れがあったのはたしかだ。けれどそれはヤゴがトンボに羽化するように、幼友達から脱皮する時だったのかもしれない。
高校は青春ドラマのような世界だろうと胸を膨らませていた。サッカーやラグビーは中学の苦い経験でやめておこうと思ったが、今度こそ何か夢中になれるものを探そう、と浩一は思っていた。
ところが当時の高校は青春ドラマとはまったく違う状況になっていた。大学紛争が高校にも飛び火し、浩一の高校もその火中にあった。
入学式でアジビラがまかれ、式の最中にもシュプレッヒコールが飛んでいた。一学期が始まっても授業はほとんどなく、全校集会が毎日のように続いた。制服問題に端を発した校則の見直しや成績評価のあり方が問題になっていた。男子の詰襟制服はもともと軍服であって学生個人の自由を奪うもの。成績評価は大学や社会の要請で学生を序列づけするもの、というのが高校生たちの主張だった。青春ドラマの何かに夢中になる、が形を変えて浩一の目の前に現れたといってよい。あるいは問題意識という背のびした感覚に惹かれて目覚めたのかもしれない。浩一は時代の風に吹かれ、改革という渦潮に飛び込んでいった。工藤洋子もまた同じだった。だが、このころはまだお互い言葉を交すことも稀だった。
浩一たちが二年生になったころ、高校紛争にも転機が訪れた。校則は少しだけ見直され、制服は標準服と名を変えて強制ではなくなった。詰襟の学生服を愛してやまず汗と埃にまみれたそれを頑なに着続ける者。洗濯に出している間だけ私服で来る者。自由を束縛する制服は絶対に着ないと言う者。校内はまちまちの服装になった。一定の改革を勝ちとると、進学のための勉学がそろそろ不安になり始めた多くの学生が改革から離れてゆき、校内の紛争は収束に向かっていた。
だが、本当の改革はまだ終わっていないと思う者たちもいた。教育問題は社会の問題に端を発している。したがって個々の学校の中で取り組んでいても限界がある。そう考える者たちが社会問題研究会、通称〈社研〉という同志会を立ち上げた。その中に浩一がいて洋子がいた。
最初は読書会から始まった。浩一もマルクスの『賃労働と資本』の文庫本がよれよれになるまで繰り返し読み込んだ。図書館へ行って関連する本も読んだ。労働問題も教育問題も戦争も、全て資本主義社会の矛盾と関連している、と思い始めたころだった。
「坂本君、大学生のサークルに行ってみない」
洋子が浩一に声をかけてきた。中学は同じでも社研の活動をするまでほとんど口を利いたことはなかった。それが読書会で熱い議論を交わすようになり、このとき声をかけられたのも同志会の仲間からの何げない提案、と浩一は思った。
それが……。
まるで映画でも見に行くように駅で待ち合わせする。来るだろうか、と時計が気になる。雑踏の中に彼女の姿を見つけてほっとし、着ている服が学校にいるときとは少し違うな、などと思ったりする。
二人、という初めての状況であまり行くことのなかった東京へ向かう電車に揺られていると、まるでデートでもしているような気恥かしさがあった。
大学までの並木道を肩を並べて歩いた。大きな銀杏の木が路の両端に整然と並んでいる。新緑の若葉が瑞々しい。木漏れ日がまだら模様を描く路だった。浩一がふだん暮らしているあたりにはない風景で、胸の奥が少しだけ踊っていた。けれど、それを洋子に悟られたくなくてわざと冷めた顔をしていた。
これから行く大学のサークルがどんなところなのか、というような洋子の説明がひと段落し、わずか数歩の沈黙が流れたときだった。
「全然関係ないけどさ、バレーボールは最近やってないの?」
じつに唐突な話題の転換だった。
「えっ? ああ、そういえば同じ湘北中だったよね、浩一くん……」
言葉がつまった。言われた浩一のほうもだ。
「あっ、いやごめん。坂本くん……」
何か失敗でもやらかしたように言いなおす。
不思議な沈黙が一瞬流れた。なぜ工藤洋子は浩一を下の名で呼んだのだろう。浩一も茫然とした。
「ああ、白状しちゃうね。じつは、あたし初江、知ってるでしょ、あなたの幼友だち、二宮初江とあのころよく話すことあったから……。彼女、坂本くんのこと、いつも浩一くん、って言ってたから、なんか私もあなたの顔見ると、つまり浩一くんという識別記号になっちゃうのよ」
「識別記号?」
「そう、名前ってそういうものじゃない。ドストエフスキーの小説みたいに同一人物にその識別記号がいくつもあったり、変化したりすると何が何だかわからなくなるでしょ? だから、初江との会話であなたが登場するときは浩一くんと決まってたのよ。だから……」
ずいぶんと風変わりな言いぶんだと浩一は思った。
「へえ、ドストエフスキーなんて読むんだ」
「まあ本はなんでも好きなの。でもドストエフスキーは疲れるわ。『罪と罰』のラスコーリニコフはラスコーリニコフで統一して欲しいわ、ほんと」
「名前が変わっちゃうの?」
「ファーストネームで呼ばれるときはロジオーンになって、それもお母さんが息子を呼ぶときはロージャってなったり。名前の一覧表でも作っておかないとストーリーも追えないわ」
「で、ぼくは浩一、か」
「ごめん、ごめん。坂本くんで統一するわ」
「いや、浩一でいいよ」
なぜか、かえってすっきりした気分になった。
「なんか恥ずかしい」
急にくだけて甘えるような言い方になった。浩一はこのとき工藤洋子と初めてうちとけることができたような気がした。
「いや識別記号と思えばなんでもないさ。だから、これから俺も工藤のこと洋子って呼ばせてもらう。いいよね」
いつも、工藤さんと言ったり工藤と呼び捨てたりしながら、じつは言う寸前にいつも迷っていたのだ。
ヨーコ、か。
胸の内で言ってみて、いい響きだな、と浩一は思った。
社研の仲間であり同志であった間柄が友だちにもなった瞬間だった。
大学の門が正面に見えてきた。だが門の石組みよりも癖のある大文字で書かれた立て看板のほうが目立っていた。
〈沖縄返還協定調印阻止!〉〈米帝から日帝への沖縄移譲粉砕!〉といった大きな赤文字が怒鳴るような字体で書かれている。浩一は体の血が騒ぐのを覚えた。
大学のキャンパスがいくつもの建物から成るひとつの街のようになっているのを浩一は初めて知った。が、そんなことに驚いているのを洋子に悟られたくなくて顔に出さないようにした。
緑青に覆われた銅板に〈学生館〉と浮き彫りされていた。その古びた建物に洋子が入ってゆく。まるでここの学生であるかのように馴れた振る舞いに内心驚きながら浩一もあとをついて行った。
廊下は薄暗く、壁はお世辞にもきれいとは言えない。もとはおそらく白壁だったようだが黄色を越えて茶色になり、さらに道路についたタイヤのブレーキ跡のような黒ずみもあちこちにある。その壁に〈沖縄返還粉砕〉のスローガンを掲げたポスターがずらりと並んで貼られていた。同じポスターなのになんで何枚も同じところに貼るのだろう、などと思いながらも口には出さなかった。
〈ロシア文化研究会〉と貼り紙されたドアの前で洋子が立ち止った。
「ここよ。さっき言ったとおり〈ロシア文化〉といっても活動の内容は私達と同じ社会問題研究」
言ってドアを開ける。中に溜っていた煙草のヤニ臭い空気が溢れ出てきた。
「こんにちは、赤城です」
工藤洋子が言った。
アカギ? いったいどういうことだ。
「アカギ……って?」
これには驚いた顔を隠すことなく洋子を見た。
「ごめん。言ってなかったっけ。ここじゃあ訳あってみんな偽名を使ってるの。浩一もすぐに名前考えておいて」
あとで教えてくれたその訳とは、大学当局や公案警察など体制側のスパイが身近に潜んでいるやもしれないので、みな偽名で呼び合っている、ということだった。
「青木君。そういうことにしておこう。なんでもいいのよ、偽の識別記号なんだから」
小声で耳打ちしてくる。浩一が面喰っているのを察して洋子がとっさに、じつに押しつけがましく浩一の偽名を決めてしまった。 いったいここはどういうところなのだろう。なにやら危い場所の匂いがした。
部屋の角に旗と思しき赤い布を巻きつけた竹竿が何本も立てかけられ、机のあちこちに土木工事で使うようなヘルメットがいくつも重ねて置かれていた。まるで工事現場の仮設事務所のようにも見える。
これが分派(セクト)のアジトなのだ、と思った。
「赤城さん、こっちこっち」
部屋の奥に黒ぶちの眼鏡をかけた大学生らしき男が手を振っている。その手は白い軍手をしていた。
「今、ビラ切ってたとこなんだ。あとで印刷手伝ってね」
優しそうなふつうの学生に見えた。偽名で呼び合う危なげな人間とは思えない。軍手をした手で鉄筆を持ち、謄写版の油紙原紙に書きものをしている最中だったようだ。浩一もガリ版刷りはするが鉄筆を持つときに軍手などしない、が確かに下敷きのヤスリ板の抵抗で指にはけっこうな負担がかかるものだ。軍手とはいいアイデアかもしれない、と感心した。
黒ぶち眼鏡の学生が軍手をとり、講師のような立場になって読書会が始まった。レーニンの『国家と革命』を抜粋したガリ版刷りが配られる。正直言って浩一には難解だった。たとえレベルが低いと思われようと初めて参加した高校生という特権で質問してみようとしたとき、洋子が先に質問した。的を得た質問だったようだ。答える学生の間にも解釈をめぐって小さな議論がおきた。浩一は自分の質問しようとしたことが貧弱に思え、気遅れしてしまった。
皆が囲んだ机の宙空が霞んでいた。煙草の煙が雲のように澱んでいるのだ。洋子が手提げバックから青いパッケージを取り出す。ハイライトだ。パッケージを指ではじいて煙草の吸い口を出し、引き抜く。赤い百円ライターで火を点ける。どこか背のびしているように見えながらも慣れた手つきだった。その一連の動きを目で追う間、浩一はテキストの内容が頭からすっぽり抜けた。自分の知らない洋子がそこにいた。
読書会が終わると講師役の学生が洋子を呼んだ。ビラの印刷を手伝わせるつもりらしい。浩一は二人の姿を目で追った。学生が眼鏡をとった。近眼らしく目のあたりを顰めたが、その横顔が眼鏡をしているときよりずっと良く見えた。写真で見た若い時のゲバラに似ているような気がした。おそらくそれは浩一の一方的な思いこみだろう。しかしそのとき心が揺れるのを感じた。ゲバラに似た大学生。その顔を見上げるようにして見つめる洋子。二人が向き合った一瞬の横顔に、中学のころから知っていて今は同じ高校の仲間である洋子が、どこか遠い存在になったような気がした。
浩一が煙草を吸い始めたのは、このときからだった。
浩一と洋子は全共闘系学生の集会やデモに参加するようになった。そのときに歌う『インターナショナル』の歌詞は書いたものがあったが、メロディーはラジオの北京放送を聞いて憶えた。たいして良い曲には思えなかった。岡林信康の『友よ』のほうが好きだった。
ゲバラが葉巻を吸う姿を真似て煙草を吸ってみたりした。ヘルメットをかぶって咥え煙草をすると、目の上に溜まった煙が目に沁みて涙が出た。それでも、催涙ガスはこんなものではない、と煙草を咥えたまま我慢した。
初江とは会うことがなくなった。家が遠くなったからでも高校が違うからでもない。住んでいる世界が違ってしまった、と思った。会っても話すことがないだろう。共通の話題を見つけるのも難しい。やるせない気持ちが心の片隅にあった。が、これはいつかやって来ることだったのだ、と思いを閉ざした。
それでも黒いドングリのような想い出の標だけは捨てようとは思わなかった。小銭入れに入れたまま、取り出して見ることもなかったが、いつも持っていたい、いや、失くしてしまいたくなかった。もともと恋焦がれるような気持ちがあったわけではない。ただ、色褪せた想い出になろうとも、記憶から消えて欲しくなかった。古いアルバムを開いて見ることがなくとも、持っていることに意味があるように。
駅から明治公園までの間は、鈍く光るジュラルミンの盾が麻雀パイのように隙間なく列をつくり、紺色のヘルメットを被った機動隊員たちがその向こう側にいた。
敵でありながら、戦いのホイッスルが吹かれるまでは襲いかかってくることのない軍団。それを横目で見ながら、路地のブロック塀のようなジュラルミンの盾に沿って浩一は洋子と公園に向かった。
「いつもより多いね」
洋子が興奮を抑えるような笑みを浮かべた。
「荒れるかもね、今日は」
危険の匂いには敏感だった。
まだヘルメットは被っていない。それでも機動隊員たちの射るような視線を感じた。おかしなことだが、そこには花道を歩く役者が観客の視線を浴びるような昂揚した気分もあった。
公園内に入るとすぐに持ってきたヘルメットを被った。顔を覆うタオルはまだあごの下にずり下げたままでいい。
ヘルメットを被った集会参加者の中にはスキーのゴーグルや水中メガネをかけている者もいる。
「頭いい。あそこまでは気づかなかったわ」
洋子が感心したように言う。
「催涙ガスでよっぽど痛い目にあったんだろうな、あのひとたち」
このまえ浩一が催涙ガスを経験したときは、塩素消毒の強いプールの匂いくらいにしか感じなかった。少しだけ目に沁み、鼻にツンときた程度だったので、それほど恐れるにたらないものと思った。だがそのときはたまたま催涙弾が遠くで破裂し、薄いガスが漂っただけだったのだろう。
公園の演壇上では各派の代表がアジテーションを始めていた。
拡声器から流れてくる言葉はじつに聞きずらい。雑音ではなく癖のある喋り方のせいだろう。吠えて噛みつくようなアジ演説は内容に意味があるのではない。「イシッ!」と一斉に呼応する異議なしの間(あい)の手が気持を昂揚させ、今日予定されている沖縄返還協定調印を何としても阻止するという意思統一の儀式だった。
演壇の下でたむろする群衆の中に手を振っている者がいた。どうやら浩一たちに向かって合図しているようだ。ヘルメットに隠れてよく見えないが黒ぶち眼鏡の感じからしてロシア文化研究会のリーダーらしい。洋子が手を振って応える。
「よお、来たか」
眼鏡をとるとゲバラに似ているリーダーが髭面の笑顔を向けた。
「今日もよろしくお願いします」と、洋子。
まるでクラブ活動の集合場所で先輩に挨拶しているようだ。
「出発は夕方だけど、きっとまた遅れるだろうな」
デモ行進が始まると先頭グループが機動隊と小競り合いになり、ひと悶着起きるのが常だった。
案の定、出発を前にして機動隊との応酬が始まった。過激なグループが投石をする。機動隊の楯に当たる音がする。どっと青ヘルメットの軍団が公園内に押し寄せる。学生の集団が引き下がる。押したり引いたり。そのうち装甲車のようなグレイの放水車が現れ、機関銃のごとく水を噴射する。やがて催涙弾が打ちこまれる。最初のうちは、上方向四十五度の射角で撃たれ、頭上で花火のように破裂した催涙弾が霧雨のようなガスを降らす。
「まだ威嚇だな」
黒ぶち眼鏡のリーダーが落ち着きはらった顔でつぶやく。学生側が火炎ビンを投げはじめると催涙弾は水平方向に撃ち込まれ、まるで銃で狙い撃ちされているようになる。そうなると濃い塩素ガスが直に飛び散り、それこそ水中メガネが必要になってくる。
陽も落ち、街路灯が点くころだった。押したり引いたりの小競り合いが続いていたとき、突然耳を劈(つんざ)くような音がした。雷が落ちたかと思った。それまで聞こえていた催涙弾の発射音や破裂音とはまったく異質の音だった。夕闇の中でみなの顔がいっせいに同じ方向を向く。原宿口のほうだ。ジュラルミンの盾が将棋倒しのように崩れた。青ヘルメット軍団の一部が崩壊するように倒れる。そのまま動かない。騒乱の声が止み、真空のような静寂が一瞬辺りを包んだ。倒れた者に駈けよる隊員。青い軍団が巣を襲われた蜜蜂のように騒ぎだす。
爆弾! という声を浩一は聞いたような気がした。
機動隊がそれまでとは違う動きを始めた。いつもの乱闘とは何かが違う。危険な匂いがした。臆病者だけが持つ敏感なアンテナがそれを察知した。
「行こう」
洋子の手をとった。浩一が彼女の手を握ったのはこのときが初めてだったかもしれない。
「今の何? 何だったの?」
洋子は茫然としていた。それまでとは違う何かが起きたことは察したに違いない。肝の縮むような爆発音を聞き、人が倒れてそのまま動かない。そんな光景を目のあたりにしたのは生れて初めてだったのだろう。もちろん浩一もそうだった。
「とにかく行こう。ここにいたんじゃヤバいよ」
浩一は洋子の手を強く握って引いた。脚を踏ん張って動かない牛を強引にひっぱるような間があり、やがて洋子はのろのろと歩き始めた。
「早く!」
青ヘルメットの一部が重い防護服を持て余しながらもこちらに向かって走ってくる。おそらくみな柔道部や相撲部出身の猛者ぞろいだ。まともにやり合えば結果は目に見えていた。
逃げ足には自信があった。と言っても駈け足が早いわけではなく、追手の目の届かない場所(スペース)へ掛け込む感覚に長けていた。学生集団が逃げる方向とは九十度違う方向へ走った。機動隊が追うのは群衆だ。ならばその群衆とは違う方向へ行く。考えてそうしたわけではなく、浩一の体が無意識にとった行動だった。幼いころからそういうときの機転だけは利いた。
必死に逃げた。人とぶつかりながら走った。洋子が誰かに当たって倒され、踏みつけられて悲鳴を上げた。洋子の体に覆いかぶさって庇う。勝気で頑強と思っていた女の子が小鳥のようにひ弱に感じた。助け起こすとき、その体が思ったよりもずっと軽かった。
走れるだろ? 肩を抱いてそう聞いた。とにかく逃げなければならない。また走りだす。息が苦しくて、鼻から下を覆っていたタオルをずり下げた。
目のまえに塀が立ち塞がった。肩くらいの高さがある。そのまま助走をつけて飛びつき、片脚をかけてよじ登った。洋子が手間取るかと思ったら難なく飛びついてきた。中学のときバレー部だったのを頭のすみでふと思い出した。
公園の外へ出た。慣れない街で土地勘はまったくない。ただ機動隊がいそうもない方へあてずっぽうで行くしかなかった。車のまったく走っていない車道が街頭に冷たく照らされている。アスファルトの路面に石の欠片が散乱する。歩道の敷石が剥がされ、土がむき出しになっている。おそらくそれを割って投石にしたのだろう。子供が戯れたあとのようにズックの靴が転がり、ナップザックが落ちている。ふだん目にする都会の街とは様子が一変していた。
「あっちだ!」
浩一が指さす。当てがあったわけではない。きっとそっちには機動隊がいないという気がしただけだ。
走った。息が切れる。こんなに走ったのは中学のサッカー部以来だ。あのころは気持ちが悪くなって走るのをやめた。だが今は胃袋が口から飛び出しそうになっても走るのをやめなかった。
「さっきの、爆弾だったの?」
走る速度を緩め、やがて歩き出したとたん洋子が肩で息をしながら言った。
「たぶん、ね」
浩一も吐く息で返事するのがやっとだった。
「死んじゃうじゃない」
今にも泣きそうな言い方になった。
「どこのセクトだろうな。あんなことやるって情報入ってなかったよね」
「いくらなんでも……向こうだって人間じゃない」
洋子の声が震えた。泣いていた。
「もう投石や火炎ビンじゃ阻止できない、てことなんだろうな」
爆弾で機動隊員を殺せば阻止できるのか? そんな疑問が浩一の胸にも湧いた。
前方の歩道に数人の人影が見えた。機動隊ではないが制服警官のようだ。定かではない。目に入る人影がみな追手に思えたのだ。
「そこ曲がろう」
洋子の手を引いて脇の路地に入った。路地のどこをどう歩いているのかわからなかったが、ときどき目に入る街区標示からおそらく渋谷のほうへ向かっているようだ。ヘルメットを脱いで手に提げた。汗で濡れた髪が夜風に冷たかった。人影がみな警官に思え、それが目に入るたびに脇道を探した。
洋子はさっきの爆弾で人が倒れたことにショックを受けているようで、下を向いたままとぼとぼと歩いていた。
路地の雰囲気が何やら変わってきた。暗く細い路地だった。大きな看板はない。暗い足元をぼんやりと照らす小さな蛍光灯の看板。まるで雪洞(ぼんぼり)のようなそれが路地の両脇に並んでいる。白地の灯りに紫色の字で〈お気軽にお入りください〉と書かれていた。〈ホテル○○〉という字も目に入る。
妙なところに来てしまったな、と浩一は思った。ちらりと横目で洋子を見る。が、さっきと同じように下を向いたまま歩いている。
「へんなとこ来ちゃったね」
気まずさを茶化すように言ったときだった。洋子が前を見て目を凝らす。
「あれ、警官じゃない?」
足を止める。
二人いる。たしかに制服警官のような気がする。
「戻ろう」
そう言って浩一は今来た路を振り返った。すると戻ろうとした路の奥に、曲がり角から姿を現した人影があった。
「ちっくしょ……」
警官かどうかもわからない。だが不安が膨れ上がり、誰もかれもが警官に思えた。場所が場所なのだから、持っていたヘルメットを捨て、恋人どうしのように手を繋いで歩く、という手もあった。だが気が動転していて、そんな機転の利く余裕はなかった。一本道で前からも後からも警官に追い込まれ、挟み打ちされたと思った。絶体絶命、と胸の内でつぶやいたときだった。洋子が浩一の手を掴んで強く引いた。一瞬どういうことかわからずに立ちすくんだ。今度は洋子が牛の手綱を引くように浩一を引っ張る。
「早く!」
怒ったような顔、いや怒っていた。
浩一はよろよろと洋子に引かれて建物の中に入った。眩しい。暗い夜道を歩いてきた目には明るすぎた。
受付の窓口は低く小さかった。中にいる人の顔もよく見えない。
部屋の希望を聞かれたようだが、どう応えたか定かでない。が、番号の書かれた透明スティックのキーホルダーを渡された。
三〇四。キーホルダーの番号はそうなっていた。
「しょうがないよ。緊急事態だもの」
狭いエレベーターの中で洋子がつぶやくように言った。浩一の顔を見ないまま自分に言い聞かせているようにも見えた。そして、
「しまった。さっきメット見られたかもしれないわね」
洋子が手に提げたヘルメットを恨めしそうに見る。
「警察に通報するかな」
「かもね」
階数を表示する〈3〉が点灯し扉が開いた。薄暗く狭い廊下の片側に部屋の扉が並んでいた。
「三階か」
カーテンを開け、窓を開けた洋子がつぶやく。すぐ目のまえを塞ぐように建物の壁がある。それでも一メートルほどの隙間があった。
「二階だったら飛び降りても何とかなるんだけどな」
浩一も下を覗いた。暗くて下に何があるのかよく見えない。
「飛び降りたら死ぬかしら」
暗い下を見つめたままぽつりと言う。
「足の骨折るくらいですむかも」
「じゃあ、警官が突入してきたら飛び降りる?」
そう言って浩一の顔を見つめた。その目が催涙ガスで赤く充血していた。
浩一はすぐに応えられなかった。洋子の髪から塩素の匂いがした。プールの匂いと洋子の匂いが混じっていた。浩一自身のシャツにもジーパンにも催涙ガスの塩素が染みついているはずだ。だがその中に、たしかに洋子の匂いを感じた。
「飛び降りてもいいよ」
ひきずられるように応えた。二人で何かを誓い合ったような気がした。そのまま洋子を抱きしめたい気持に襲われた。そんなことは初めてのようでもあり、今までも意識の隠れたところにあったような気もする。
洋子の肩に手を伸ばす。心を決めて洋子の目を見つめた……。
その直後に何があったか、浩一の記憶は定かでない。ただ、厳しく拒絶されたことだけはたしかだ。
部屋の雰囲気に惑わされたのかもしれない。誰もいない二人だけの空間。狭い部屋にダブルベッドがあった。
洋子に言わせれば、緊急事態でやむなくこの部屋に来ただけ。吹雪の冬山で遭難し、避難小屋にたどり着いたようなものだ。勘違いするな、ということだった、と、あとになって浩一は思っている。
警官隊が突入してきたときは、窓から飛び降りるにしても時間稼ぎが必要だ。いきなり突入されたのでは飛び降りる間もない。うまく飛び降りることができて運よく片足骨折だけですめば片足けんけんで逃げることも可能だろう。それにしても時間稼ぎが必要だ。
「バリケード作ろう」
洋子の限りなく命令に近い提案で、ドアの内側にバリケードを築くことにした。ソファー、テーブル、椅子をドアの前に立て掛けて、電気スタンドのコードと引き裂いたタオルを繋げて縛りつけた。二人でああしたら、こうしたらと言い合いながらやっていると文化祭の準備をしているような雰囲気にもなった。
「よーし、これならドアぶち破られても、すぐには入ってこれないわね」
追いつめられた状況でも、小さな達成感に笑みがこぼれた。
部屋の中はダブルベッドだけになり、あとはみなバリケードに使ってしまった。
がらんとした部屋に二人肩を並べて体育座りし、壁にもたれかかった。
「爆弾じゃ阻止できないよ」
洋子がしんみりとなって言った。市民と一緒になって大きな力にしないと駄目だという。
沖縄の基地は無くならず、核もおそらく残る。返還協定に調印することは、アメリカと日本がそれに合意して契約すること。
「そういうことなんだ、って認識を、まず市民と共有することが必要なのに……」
「俺もそう思うよ」
自分の言おうとしていたことをみな先に言われた、と浩一は思った。
「今のままじゃ全共闘は孤立するわ」
ため息とともに胸ポケットからハイライトを出す。
浩一は灰皿を取り、洋子の前に置いた。そして自分も胸ポケットを探る。だがあったはずの煙草がない。どうやらどこかに落としたらしい。
「はい」
洋子がパッケージを指ではじいて吸い口を出し、浩一にさし出す。浩一はサンキューという仕草で煙草を抜き取り、また胸をまさぐってライターを探す、がそれも無い。
火のついた赤いライターが目のまえに現れた。
浩一は洋子の手を包み込むようにしてそれを受ける。と、灯りを燈したように煙草の先が燃えた。浩一の胸の中まで照らされ温められたような気がした。
狭い部屋に煙が漂う。二人それぞれの煙が絡み合い、混じり合ってゆく。やがて二人の体から出る催涙ガスの塩素臭と煙草の匂いも混じり溶けあっていった。
「夜明けは遠い、かもな」
浩一は好きだった『友よ』の歌詞を虚しく想った。
「そうだね。アジっても石投げても、すぐには変わらないよ」
そう言うと、洋子の頬を涙がひとすじ伝って落ちた。
浩一は洋子の肩を抱いてやりたかった。だけど、また拒絶されるかと思ってやめた。
ひと晩じゅう体育座りのまま話していた。どちらか一人がベッドに入ることもなかった。
うとうとと洋子の頭が浩一の肩に寄りかかりかけたとき、遠くで線路の軋む音がした。静まり返っていた街に始発電車がやってきた。
夜明けは遠い。それでも、現実の夜は明けていった。
窓の前を塞いでいる壁に、隙間から射し込んだ朝陽があたる。反射した薄明かりが部屋をぼんやり照らし始める。けっきょく警官隊が突入してくることはなかった。
二人でバリケードを解除する。ソファーをもとあった場所に戻し、テーブルと椅子を置きなおした。引き裂いたタオルだけはもとに戻らず、ゴミ入れに捨てた。
まるで新居に越してきたみたいだ、と小さく笑い合った。ダブルベッドの枕は乱れることなくシーツも来たときのままぴんと張っている。
部屋の明りを消し、二人でドアを出た。
狭い路地に人影はない。朝陽が眩しい。恥ずかしがるようなことはないはずなのに、浩一はうしろめたく恥ずかしかった。洋子もそんな顔をしていた。
前夜、沖縄返還協定は調印され、全国で千人を超える逮捕者が出た。
※作品中の挿絵は、写真及び著者の詳細指示に基づいてAIで作成した画像を加工編集したものです。