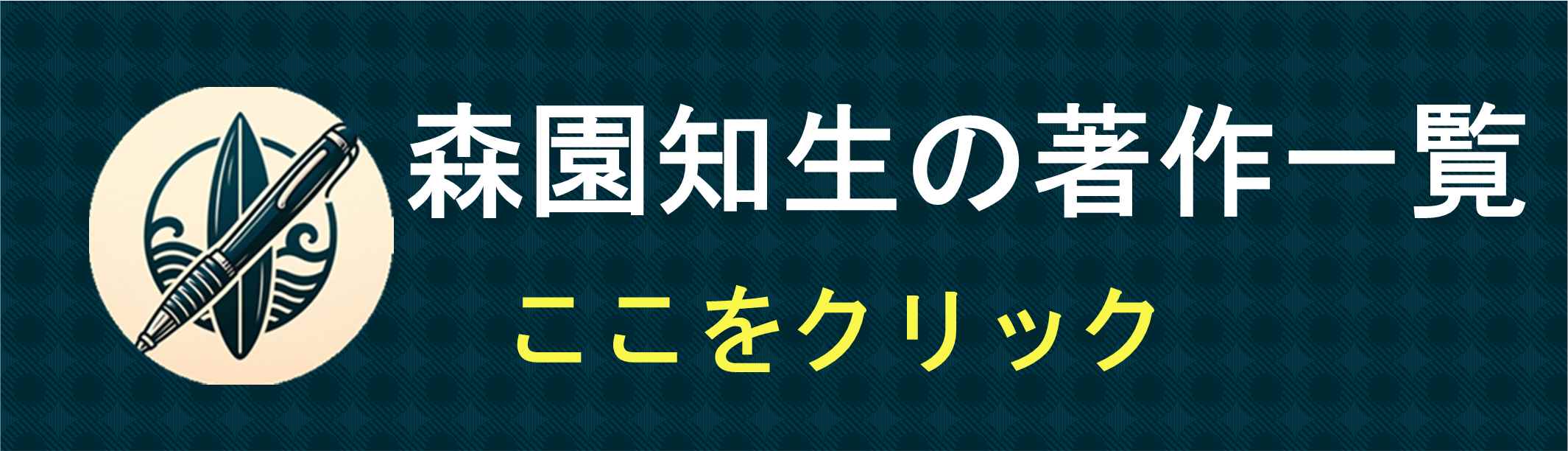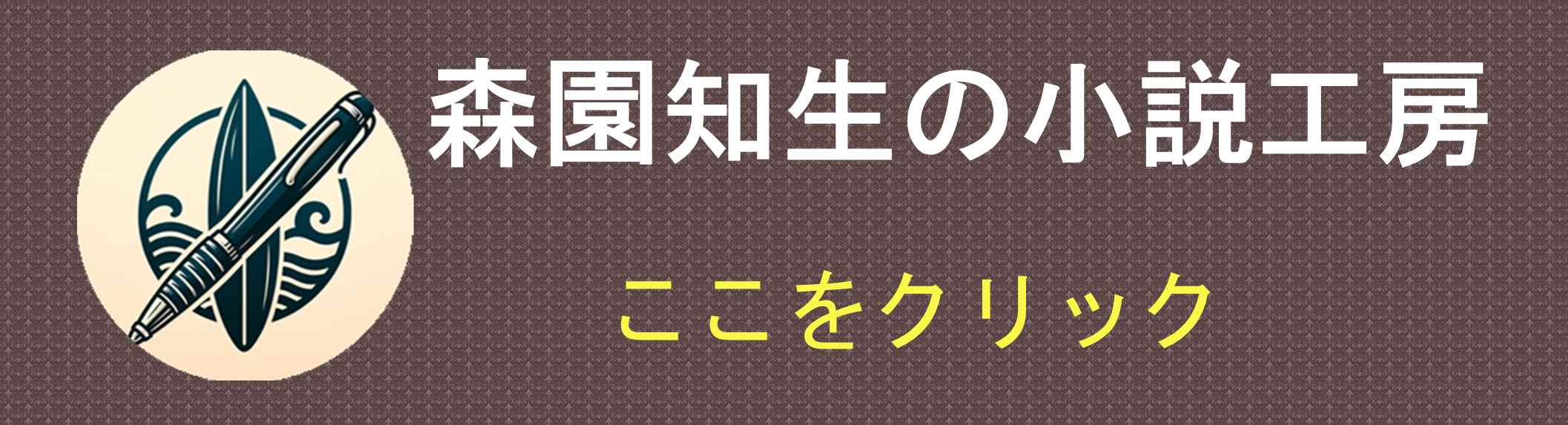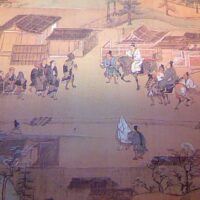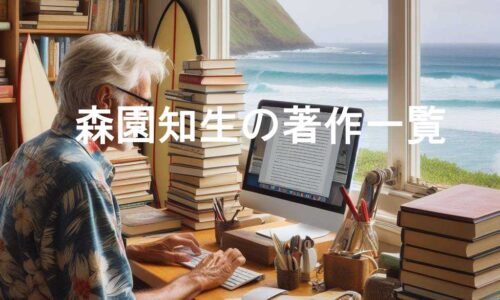古文献に、その名は登場すれど……
この「大仏坂切通し」は古文献に、その名称は登場するものの、現在「大仏隧道」の脇を通る古道(国指定史跡「大仏切通」)がそれに相当するものなのか、明確にはわかっていません。(発掘調査では「かわらけ(素焼きの皿)」が出土したことから中世鎌倉時代にすでにあった道であることは間違いなさそうです)
『新編鎌倉志』には「大佛切通」の項に、「大仏西の方なり。この切通を越えれば、常盤里へ出るなり。『吾妻鏡』に、治承五年(1181年)九月十六日に、足利俊綱が郎党、桐生六郎、主の首を持参して、梶原景時が許に案内を申す。しかるに鎌倉の中に入れられず。直ちに武蔵大路より深沢を経て腰越に向うとあり。深沢をへて行く道、この道筋ならんか。云々」とあ ります。(以上は訳文。原文全文はリンク先を参照方)
では、その『吾妻鏡』の治承五年(1181年)九月十六日の条を見てみますと、たしかにそのように書かれています。(全文はリンク先を参照方) しかし「武蔵大路より深沢を経て腰越に向う」といえば、今の湘南モノレールのルートに相当します。『新編鎌倉志』は「この道筋ならんか」と言ってますが、現在云われている大仏坂切通し(大仏隧道の脇を通る古道=国指定史跡「大仏切通」)とはだいぶ位置関係が違うように思え、首を傾げます。
また、『新編鎌倉志』より半世紀ほど前に書かれた『玉舟和尚鎌倉記』にも「大仏坂」の記述があるようですが、この文献は、今回確認できておりません。どうやら、作家の大仏次郎氏が持っていた文書が唯一のもので、写本等は残されていないとのことです。「大仏次郎(おさらぎじろう)」という筆名に、偶然にも今回のテーマとの関係性を感じ、何かの機会にぜひその文献を拝見したいと思っております。(詳細はリンク先をご参照方)
国指定史跡とされている「大仏切通」を歩いてみた
では、文献確認はこれくらいにして、現在「大仏坂切通し」と云われている道(国指定史跡「大仏切通」)を歩いてみましょう。

大仏隧道
大仏(高徳院)から新道を歩いて5分くらいのところにあります。(今回はワケあって徒歩時間も注意しておいてください)

旧道への入口
右横に見える石段が旧道への入口です。

石段を上ってゆきます。

道標があったのですが……。
私が来た道は長谷駅・高徳院。これから行こうとする「大仏切通し」の表示はなく、源氏山公園・銭洗弁天は全く方向違いです。しかし道標にない石段道が左方向に上って行ってます。「おそらくこの道だろう」と判断して左の石段を上ることにしました。
ところが、じつはこれが大間違い。(どうなったかお知りになりたい方はリンク先をご覧ください)
間違いとわかって、ようやく道標(上の写真)のあった所へ戻り、しかたなく、ためしに「源氏山公園・銭洗弁天」と指された方へ行ってみると、間もなく次の道標がありました。

ようやく「大仏切通」の表示が出てまいりました。ここで源氏山方向と大仏切通に分岐しているのです。
「この道標設定、おかしいでしょう!」
本来、最初の道標に「源氏山・銭洗弁天」に「大仏切通」も併記すべきです。そうすれば、とんでもない方へ行ってしまうことはなかったでしょう。ブチブチひとり文句を言いながら歩きます。

ようやく山道に入ってきました。でもまだ「切通し」の雰囲気はありません。

国指定史跡「大仏切通」の標柱
これで安心して進めます。

なんとなく「切通し」の気配がしてきました。第5回ともなると、嗅覚が鍛えられてくるのです。(だったら、さっきみたいなことにはならないだろう、て? 仰る通りです(>_<) )

おお! これ、これ。「切通し」の雰囲気が出てまいりましたね。

両脇の崖は、人が手で削ったものでしょう。(すみません。素人判断ですが……)

敵の馬の侵入を妨害するために置かれた石でしょう。
(その後「これらは落石である」というご指摘をいただきました。そうかもしれません)

これもそうでしょう。

うーむ。中世の匂いがしますね。旅人、なんてのんきなものではありません。ここを侵入してくる外敵がいれば、崖の上から矢が飛んでくるでしょう。侵入者たちは一網打尽。
(後にご指摘を受け、調べたところ、明治時代に人力車が通れるよう、開削工事が行われたとのことです。地形は時代と共に変わってゆくもの。しかし、私には、まだまだ中世の匂いが残っていると感じました)

じつはこの辺りで源氏山のほうからハイキングでやってきたという女性二人組と出会いました。
「シャッターを押して欲しい」とのことでしたので、岸壁をバックに二人を写してさしあげました。ここでお会いしたのも何かのご縁ですので、拙著『オリンポスの陰翳』と当ブログの紹介をしてお別れしました。(最初の道標から10分。この出来事を頭に置いておいてください)

また、狭い道を塞ぐように大きな置石があります。(落石かもしれませんが……)

おお! 「やぐら」です。

誰の墓かはわかりませんが、おそらく武士階級のものでしょう。

庶民は墓など作れず、遺体は遺棄されていたと思われます。遺体がそこかしこに放置されているのを想像すると、ちょっと気味悪いです。夕暮れ時に来るのはおやめになった方がよろしいかと……。

まんだら堂やぐら群を一人で訪れたときの経験ですが、夕暮れ時に着いて、見て回っているうちに、いつの間にか夕闇が迫ってきて……、まさにトワイライトタイムです。どんどん暗くなってきて……。(『千と千尋の神隠し』の最初の方に、そんなシーンがありましたでしょ。あんな感じでした) たまらず逃げるように立ち去ったのを憶えています。

鎌倉の外側から来ると、切通しの入口付近に「やぐら」や「刑場」があることは多いです。執権北条泰時の時代に鎌倉内に墓、法華堂を建てることが禁止されましたので、そうなって当然ですが、私は、もうひとつの理由があるように思います(得意の妄想ですが)。ジョニー・デップ主演の『パイレーツ・オブ・カリビアン』で船の入ってくる港の入口に、見せしめのような遺体(骸骨?)が吊るしてありましたよね。つまり、古今東西、集落の入口には「侵入者への警告」、「魔除け」のような意味合いで遺体を晒すのではないか? すいません、私のまったくの推測、妄想ではありますが……。

切通しの出口(外側からは入口)にあった注意書き。
ここで鎌倉(現在の行政区画ではありません)の外側へ出たことになります。
さて、今回の「大仏坂切通し」には番外編の「その2」があります。
題して『大仏坂切通し殺人事件』! よろしければココをクリック!